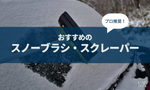「制限速度」「指定速度」「法定速度」は何が違うの?交通事故を防止しよう!
更新日:2025.11.05

※この記事には広告が含まれます
交通ルールの話題でよく目にする「制限速度」・「指定速度」・「法定速度」という言葉。それぞれ似たように思えますが、実は意味や使われ方に違いがあります。これらを正しく理解していないと、知らないうちにスピード違反を犯してしまう恐れもあります。今回は、速度表示について紹介していきます。
- Chapter
- 1. 制限速度・指定速度・法定速度の概要
- 2. 各用語の定義と違いの比較
- 3. 実際の道路標識やケーススタディでの違いの例
- 標識がある道路の場合
- 標識がない道路の場合
- 生活道路(住宅街)のケース
- 高速道路のケース
- 最低速度標識
- 4. 制限速度に違反した場合の罰則と注意点
- 注意点: 「+10km/h程度なら捕まらない」は危険な油断
- 5. よくある勘違いと正しい理解のポイント
- 「法定速度=いつでも出して良い速度」ではない
- 「追い越しなら制限速度を超えてOK」ではない
- 「メーター表示以上のスピードが出る車=出しても良い速度?」
- 「他の車も飛ばしているから自分も…」という誤解
- 最低速度違反にも注意
- 将来的な法改正の動向
- 6. まとめ:安全運転と速度管理の重要性
1. 制限速度・指定速度・法定速度の概要
まず最初に、3つの用語の概要を押さえておきましょう。いずれも車両の「出してよい最高の速度」に関する言葉ですが、指している内容が微妙に異なります。
- 制限速度(せいげんそくど)
- 指定速度(していそくど)
- 法定速度(ほうていそくど)
「制限速度」は広い意味で使われる俗称で、その中に「指定速度」(標識で指定された最高速度)と「法定速度」(法律で定められた最高速度)の2種類がある。
どちらも「最高速度」という言葉でひとまとめにされる概念ですが、標識で指定されているか否かがポイントです。2. 各用語の定義と違いの比較
それでは、制限速度・指定速度・法定速度をより詳しく定義し、その違いを比較してみましょう。以下にそれぞれの特徴を表にまとめます。
道路交通法で規定されているのはあくまで「最高速度」です。
つまり、制限速度・指定速度という呼び方は法律上の正式な言葉ではなく、運転者の間で便宜上使われている用語と言えます。
しかし一般にも広く浸透しているため、警察や行政の説明文でも「いわゆる法定速度」などと記載されることがあります。
| 用語 | 法律上の位置づけ | 意味・内容 |
| 制限速度 | 法律用語ではない(俗称) | その場における最高速度のこと。標識による指定速度・法定速度などを広く含む。日常的に「速度制限」「スピードリミット」といった意味で使われる。 |
| 指定速度 | 法律用語ではない(俗称) ※道路交通法第22条で言う「指定された最高速度」 | 標識や標示によって個別に指定された最高速度のこと。道路標識の数字で示される速度上限で、その道路区間で超えてはいけない速度を指す。制限速度標識で指定されている最高速度とも言える。 |
| 法定速度 | 法律用語 (正式には「法定最高速度」) | 法律(政令)で定められた最高速度。標識等の指定が無い場合に適用される速度上限。道路の種類や車両の種類ごとに決められており、普通乗用車は一般道60km/h・高速道路100km/hなど。これらを超えると速度超過違反となる。 |
つまり、制限速度・指定速度という呼び方は法律上の正式な言葉ではなく、運転者の間で便宜上使われている用語と言えます。
しかし一般にも広く浸透しているため、警察や行政の説明文でも「いわゆる法定速度」などと記載されることがあります。
守るべき最高速度には、道路標識で示される「指定速度」と、標識がない場合に適用される「法定速度」の2種類があります。
標識による「指定速度」は、常に「法定速度」に優先します。 例えば、法定速度が60km/hの一般道でも「40」の標識があれば40km/hが上限ですし、法定100km/hの高速道路で「120」の標識があれば、その区間は120km/hまで走行可能です。
標識による「指定速度」は、常に「法定速度」に優先します。 例えば、法定速度が60km/hの一般道でも「40」の標識があれば40km/hが上限ですし、法定100km/hの高速道路で「120」の標識があれば、その区間は120km/hまで走行可能です。
3. 実際の道路標識やケーススタディでの違いの例
標識がある道路の場合
写真のような「最高速度○○」標識(通称:速度制限標識)が設置されている道路では、その数字が指定最高速度(制限速度)となります。その道路区間では標識に表示された速度を超えて走行してはいけません。例えば「50」と表示されていれば最高速度50km/hの意味で、それまでは出してよいが50km/hを1km/hでも超えると違反になります。追い越しの際も例外ではなく、一時的であっても超過は違法です。
標識がない道路の場合
何らかの速度指定標識が見当たらない道路では、法定速度がそのまま適用されます。一般道で標識がなければ原則60km/h、高速自動車国道で標識がなければ100km/hが上限速度です。ただし、センターラインのない狭い道路では、安全上の理由から道路標識によって50km/hや40km/hなど、法定速度より低い最高速度が指定されていることが非常に多いです。標識がないことを確認した場合の法定速度は原則60km/hですが、道路状況に合わせて速度を落とすのが安全運転の基本です。
生活道路(住宅街)のケース
住宅街の細い道路など、いわゆる「生活道路」と呼ばれる区間では特に注意が必要です。見たところ速度標識が無いような道路でも、そうした生活道路は最高速度30km/hに指定されている場合があります。これは各地域の公安委員会がゾーン規制(ゾーン30など)によってエリア一帯を指定しているケースで、入口に小さな標識があるだけで中の道路には個別の標識が立っていないこともあります。したがって「標識が見当たらないから法定の60km/hまで出して良い」と考えるのは大変危険で、もし住宅街で飛ばせば重大事故につながる恐れがあるうえ違反にも問われます。狭い生活道路では標識の有無にかかわらず、30km/h以下の徐行を心掛けるのが安全です。
高速道路のケース
高速道路では法定速度が基本的に100km/h(大型貨物等は80km/h)ですが、実際にはカーブの多い区間やトンネル前後などで「80km/h」「50km/h」といった指定速度標識を見かけることがあります。こうした区間では当然ながら指定された数値(80や50など)が上限となります。
また、近年一部の高速道路区間では試験的に最高速度を110km/hや120km/hに引き上げる取組も行われています。例えば新東名高速道路のある区間では標識によって120km/hが指定されており、その区間に限っては乗用車は120km/hまで走行可能です(大型車等は除く)。このように高速道路でも道路環境や交通状況に応じて標識で速度指定が行われ、指定速度が法定速度より優先されます。なお、高速道路には最低速度(後述)もありますので、遅すぎる走行にも注意しましょう。
また、近年一部の高速道路区間では試験的に最高速度を110km/hや120km/hに引き上げる取組も行われています。例えば新東名高速道路のある区間では標識によって120km/hが指定されており、その区間に限っては乗用車は120km/hまで走行可能です(大型車等は除く)。このように高速道路でも道路環境や交通状況に応じて標識で速度指定が行われ、指定速度が法定速度より優先されます。なお、高速道路には最低速度(後述)もありますので、遅すぎる走行にも注意しましょう。
最低速度標識
高速道路や自動車専用道路には、最低速度を示す標識(丸い枠に青地の数字と下線)が設置されている場合があります。例えば高速道路の多くの区間では「最低速度50km/h」の標識があり、路面や交通が特に支障ない限り50km/h未満で走っては違反となります。これは安全走行のため、遅すぎる車両がかえって危険を生じないようにする規制です。最低速度違反も罰則がありますので、高速道路では極端に遅い走行は避け、状況に応じ適切な速度で走行しましょう。
4. 制限速度に違反した場合の罰則と注意点
速度超過(スピード違反)は交通違反の中でも特に検挙件数が多く、重大に扱われる違反です。規制速度を超えて走行すると、超過幅に応じて反則金(または罰金)と違反点数が科され、悪質な場合は刑事処分や免許停止・取消しにも繋がります。具体的な罰則の概要は以下の通りです(普通乗用車・一般道の場合)。
速度超過 ~14km/h: 違反点数1点、反則金9,000円
15~19km/h超過: 違反点数1点、反則金12,000円
20~24km/h超過: 違反点数2点、反則金15,000円
25~29km/h超過: 違反点数3点、反則金18,000円
30km/h以上超過(高速道路は40km/h以上超過): 違反点数6点(※一発で免許停止)、赤切符交付(刑事手続へ)。前歴がなくても30日間の免許停止処分となります。反則金制度の適用外となり、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金の対象です。一般道で30km/h、高速道で40km/hを超えると重い違反となることを覚えておきましょう。
50km/h以上超過: 違反点数12点(※前歴がなくても90日間の免許停止)。刑事罰は上記と同様に6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金の対象ですが、超過速度が大きいほど重い処分が科される傾向にあります。
※上記は普通車の一般道での例です。高速道路や、大型車・二輪車は反則金額が異なります。また速度超過以外に他の違反が重なると加点され処分も重くなります。
速度超過 ~14km/h: 違反点数1点、反則金9,000円
15~19km/h超過: 違反点数1点、反則金12,000円
20~24km/h超過: 違反点数2点、反則金15,000円
25~29km/h超過: 違反点数3点、反則金18,000円
30km/h以上超過(高速道路は40km/h以上超過): 違反点数6点(※一発で免許停止)、赤切符交付(刑事手続へ)。前歴がなくても30日間の免許停止処分となります。反則金制度の適用外となり、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金の対象です。一般道で30km/h、高速道で40km/hを超えると重い違反となることを覚えておきましょう。
50km/h以上超過: 違反点数12点(※前歴がなくても90日間の免許停止)。刑事罰は上記と同様に6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金の対象ですが、超過速度が大きいほど重い処分が科される傾向にあります。
※上記は普通車の一般道での例です。高速道路や、大型車・二輪車は反則金額が異なります。また速度超過以外に他の違反が重なると加点され処分も重くなります。
速度超過違反は6点以上で免許停止処分(前歴がない場合)が下るため、30km/h超過(高速で40km/h超過)なら1回で免停ラインに達します。
注意点: 「+10km/h程度なら捕まらない」は危険な油断
統計上、15km/h未満の微超過での検挙は少ない傾向にありますが、法律上は1km/hでも速度違反です。近年は可搬式オービスの導入で生活道路での取締りも強化されており、「少しだけなら大丈夫」という油断は禁物です。
加えて、たとえ検挙されなくても速度超過は事故のリスクを大幅に高めます。ブレーキの制動距離は速度が上がるほど急激に伸び、警察庁などのデータによれば、衝突時の歩行者の致死率も時速30kmを超えると飛躍的に上昇します。罰則を避けるためだけでなく、自分と周囲の安全を守るためにも、常に制限速度を意識した運転を心がけましょう。
加えて、たとえ検挙されなくても速度超過は事故のリスクを大幅に高めます。ブレーキの制動距離は速度が上がるほど急激に伸び、警察庁などのデータによれば、衝突時の歩行者の致死率も時速30kmを超えると飛躍的に上昇します。罰則を避けるためだけでなく、自分と周囲の安全を守るためにも、常に制限速度を意識した運転を心がけましょう。
5. よくある勘違いと正しい理解のポイント
「法定速度=いつでも出して良い速度」ではない
法定速度はあくまで上限であり、その速度までは常に安全に走行できるという意味ではありません。先述のように住宅街のような道路環境では、たとえ法定60km/h以下でも危険な場合があります。道路交通法第70条には「運転者は、道路や交通の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」との安全運転義務が規定されています。状況によっては法定速度より低い速度で走行しなければ安全を保てないことも多々あるのです。「制限速度内だから大丈夫」ではなく、常に周囲の状況に応じた安全な速度を意識しましょう。
「追い越しなら制限速度を超えてOK」ではない
前の車を追い越す際、「一時的にスピード超過しても大丈夫では?」と考える人がいます。しかし法律上、いかなる場合でも制限速度を超えることは許されません。追い越しは加速を伴うため難しいシーンですが、制限速度内で行える場所と方法でのみ追い越す必要があります。制限速度を守っている車を追い越したいがために違反速度で走るのは本末転倒ですし、追い越し自体が禁止されている場所もあります。どうしても前が遅い場合でも、焦らず制限速度内で機会を待つことが安全運転に繋がります。
「メーター表示以上のスピードが出る車=出しても良い速度?」
市販車のスピードメーターは180km/hや220km/hまで目盛りがあったり、高性能車では実際に200km/h以上出るものも存在します。しかし、これは車両の性能・試験基準上の仕様であって道路上でその速度を出して良いわけではありません。日本では高速道路でも法定100km/h(標識指定があってもせいぜい120km/h程度)です。メーカーが余裕を持って設計しているからといって法定速度以上を出せば当然違反となりますし、そのような超過速度域での走行は公共の道路では極めて危険です。車の性能と法定速度は別ということを認識し、メーターの限界までスピードを試すような行為は絶対にやめましょう。
「他の車も飛ばしているから自分も…」という誤解
交通の流れが速いと、自分も合わせてオーバースピードで走った方が安全なのでは?と感じる場面があるかもしれません。確かに周囲と極端に遅いと危険なこともありますが、だからといってみんなで制限速度を超えて良い理由にはなりません。速度違反は違反ですし、事故が起きた場合に過失が大きくなります。また、流れが速すぎる場合は警察が取締りを行う可能性も高いです。むしろ制限速度付近で走行する車が増えれば全体の流れも落ち着き、安全性が高まります。他車に煽られたり周りが速いからといって無理についていかず、自ら法定内の適切な速度を維持する勇気も大切です。
最低速度違反にも注意
先ほど触れた高速道路の最低速度について、「そんなに遅く走ることはないから関係ない」と思われがちです。しかし渋滞の先頭で漫然と低速走行を続けたり、故障でもないのに極端に低い速度で走ると交通の円滑を阻害し危険です。最低速度違反(高速自動車国道の本線車道で50km/h未満など)は違反点数1点、反則金6,000円(普通車)が科せられます。高速道路では車両故障ややむを得ない事情が無い限り、法定の最低速度を下回らないよう心がけましょう。
将来的な法改正の動向
今後のトピックとして、生活道路における法定速度を30km/hに引き下げる法改正が検討されており、2026年頃の施行を目指して準備が進められています。これが実現すると、現在は標識がなければ法定速度60km/hである特定の生活道路(中央線のない道路などが対象と見られる)でも、法定速度そのものが30km/hになります。そうなれば、該当エリアでは標識が無くても30km/hを超えると速度超過違反となります。背景には生活道路での事故防止があります。ドライバーの皆さんは、こうした規制の動きにも注目し、常に最新の交通ルールにアップデートしていくことが求められます。
6. まとめ:安全運転と速度管理の重要性
「制限速度」「指定速度」「法定速度」の違いと関連知識について解説してきました。制限速度=守るべき最高速度という大前提は共通ですが、その内訳として標識で指定された速度(指定速度)と法律で定められた速度(法定速度)があること、そして指定速度がある場合はそれが優先されることを理解いただけたかと思います。それぞれの意味を正しく把握していれば、道路状況に応じた適切なスピードコントロールが可能になり、知らず知らずの違反を防ぐことにもつながります。
最後に何より強調したいのは、安全運転のための速度管理の重要性です。速度違反の罰則は厳しく設定されていますが、それはドライバーへの「安全に走るための抑止」としての意味があります。制限速度を守ることは、罰金や点数のためだけでなく自分自身や周囲の生命を守る行為です。スピードを出しすぎないことで視野が広がり、突然の危険にも対応しやすくなります。逆に言えば、適切な速度を守ること自体が防衛運転とも言えるでしょう。
道路交通法第70条にあるように、運転者は常に「他人に危害を及ぼさないような速度と方法」で運転する義務があります。制限速度というルールを正しく理解し順守することは、その義務を果たす第一歩です。ぜひ今一度、自分の走行速度を見直し、標識や法定の速度を意識した運転を心掛けてください。
ゆとりある速度で走ることが、結果的に目的地への安全・確実な到着につながるのです。速度管理を徹底し、皆さんも安全で安心なドライブを楽しみましょう。
最後に何より強調したいのは、安全運転のための速度管理の重要性です。速度違反の罰則は厳しく設定されていますが、それはドライバーへの「安全に走るための抑止」としての意味があります。制限速度を守ることは、罰金や点数のためだけでなく自分自身や周囲の生命を守る行為です。スピードを出しすぎないことで視野が広がり、突然の危険にも対応しやすくなります。逆に言えば、適切な速度を守ること自体が防衛運転とも言えるでしょう。
道路交通法第70条にあるように、運転者は常に「他人に危害を及ぼさないような速度と方法」で運転する義務があります。制限速度というルールを正しく理解し順守することは、その義務を果たす第一歩です。ぜひ今一度、自分の走行速度を見直し、標識や法定の速度を意識した運転を心掛けてください。
ゆとりある速度で走ることが、結果的に目的地への安全・確実な到着につながるのです。速度管理を徹底し、皆さんも安全で安心なドライブを楽しみましょう。