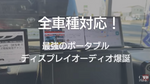ブレーキが効かなくなったら...!? 緊急時の対処法と原因・予防策【完全ガイド】
更新日:2025.12.08

※この記事には広告が含まれます
運転中に突然ブレーキペダルが利かなくなったら――想像するだけでゾッとしますよね。実際にブレーキが効かなくなったことで起きた事故は年間数十件にも上るとされ、誰にでも起こり得る危険です。たとえば山道でブレーキが利かなくなり、崖に車体をぶつけて辛うじて停車したというケースも報告されています。運転者はむち打ちや打撲などの怪我を負っており、車の欠陥による事故でした。こうした最悪の事態に備え、ブレーキが効かなくなった場合の原因や対処法、日頃からできる予防策を知っておきましょう。
- Chapter
- ブレーキが効かなくなる原因
- フェード現象(ブレーキの過熱による効力低下)
- ベーパーロック現象(ブレーキフルードの沸騰による気泡発生)
- ブレーキ部品の不具合・摩耗
- タイヤや路面状況によるもの
- 車両重量やその他の要因
- ブレーキの種類とそれぞれの特性
- フットブレーキ(サービスブレーキ)
- エンジンブレーキ
- パーキングブレーキ(サイドブレーキ)
- ブレーキが効かなくなったときの緊急対処法
- 1. 周囲に異常を知らせる
- 2. エンジンブレーキで減速する
- 3. パーキングブレーキで完全停止する
- 4. 最後の手段を講じる
- 5. 停車後の対応
- ブレーキトラブルの予防策と日常点検のポイント
- ブレーキの効き具合を定期チェック
- ブレーキオイル(フルード)の点検・交換
- 警告灯の監視
- タイヤの状態管理
- 走行中のブレーキ酷使を避ける
- 足元の整理整頓
- まとめ
ブレーキが効かなくなる原因
フェード現象(ブレーキの過熱による効力低下)
長い下り坂などでフットブレーキを踏み続けると、ブレーキパッドとディスクが過熱し摩擦係数が低下します。
その結果、どれだけ強く踏んでも減速できない状態になります。この一時的な制動力低下現象を「フェード現象」と呼びます。
その結果、どれだけ強く踏んでも減速できない状態になります。この一時的な制動力低下現象を「フェード現象」と呼びます。
ベーパーロック現象(ブレーキフルードの沸騰による気泡発生)
フェード現象が起きるほど過熱した状態でさらにブレーキを使い続けると、ブレーキフルード(オイル)にまで熱が伝わり沸騰してしまいます。
フルード内に気泡が生じるとペダルの踏力が油圧に伝わらず、ブレーキがまったく効かない状態になります。これを「ベーパーロック現象」と言い、フェード現象よりも危険な完全な制動喪失を招きます。
フルード内に気泡が生じるとペダルの踏力が油圧に伝わらず、ブレーキがまったく効かない状態になります。これを「ベーパーロック現象」と言い、フェード現象よりも危険な完全な制動喪失を招きます。
ブレーキ部品の不具合・摩耗
日常整備不足によるブレーキシステム自体のトラブルも原因になります。例えばブレーキオイル(フルード)の劣化や不足、エア混入による油圧低下、ブレーキパッドの極度の摩耗、ディスクローターの歪みやサビ、ブレーキキャリパーやマスターシリンダーの故障、ABSなど電子制御ブレーキの異常などです。
こうした不具合があるとブレーキの効きが悪くなったり、最悪全く効かなくなることがあります。特にブレーキオイルは吸湿性が高いため劣化すると沸点が下がり、ベーパーロック現象も起きやすくなります。定期的な交換を怠ると危険です。
こうした不具合があるとブレーキの効きが悪くなったり、最悪全く効かなくなることがあります。特にブレーキオイルは吸湿性が高いため劣化すると沸点が下がり、ベーパーロック現象も起きやすくなります。定期的な交換を怠ると危険です。
タイヤや路面状況によるもの
ブレーキ系統に問題がなくても、タイヤと路面の摩擦が失われれば車は止まりません。代表的なのがハイドロプレーニング現象で、高速走行中に路面の水膜に乗ってタイヤが滑ると、ブレーキもハンドルも効かなくなります。
大雨の高速道路や深い水たまりで発生しやすく、非常に危険です。また、凍結路や積雪路でもタイヤが空転して制動力が路面に伝わらず、「ブレーキが利かない」状態に陥ります。加えてタイヤの溝がすり減っていると路面排水性が悪化し、こうした滑走現象が起きやすくなるため日頃のタイヤ点検も重要です。
大雨の高速道路や深い水たまりで発生しやすく、非常に危険です。また、凍結路や積雪路でもタイヤが空転して制動力が路面に伝わらず、「ブレーキが利かない」状態に陥ります。加えてタイヤの溝がすり減っていると路面排水性が悪化し、こうした滑走現象が起きやすくなるため日頃のタイヤ点検も重要です。
車両重量やその他の要因
過積載(車に重い荷物を積みすぎた状態)では車体が重く惰性が大きくなるため、ブレーキを踏んでも減速距離が長くなり効きが悪く感じます。また運転席足元の異物も盲点です。
ペットボトルや荷物がブレーキペダルの裏に転がり込むとペダルが踏み込めず、重大事故につながるケースが毎年報告されています。運転前には足元に物が落ちていないか確認しましょう。
ペットボトルや荷物がブレーキペダルの裏に転がり込むとペダルが踏み込めず、重大事故につながるケースが毎年報告されています。運転前には足元に物が落ちていないか確認しましょう。
長い下り坂でフットブレーキを酷使するとブレーキが過熱し「フェード現象」を起こします。さらにフルード沸騰による「ベーパーロック」に発展すると完全にブレーキが効かなくなるため、長距離の下りではエンジンブレーキを併用しましょう。
ブレーキの種類とそれぞれの特性
フットブレーキ(サービスブレーキ)
いわゆるブレーキペダルを踏んで作動させる主制動装置です。
油圧式のディスクブレーキやドラムブレーキによって、車輪の回転を直接抑えます。乗用車の場合、フットブレーキは前後すべての車輪に作用します。ただし前輪と後輪ではかかる力の配分が異なり、減速時には車体の前方に荷重がかかるため前輪ブレーキに強い制動力が割り当てられています。そのため前輪には大径のディスクローターや強力なキャリパーが備えられ、車体を効率的に減速させることができます。
フットブレーキは減速力が高く扱いやすい一方、長時間連続で使うと過熱しやすいという特性があります。前述のフェード現象・ベーパーロック現象はフットブレーキの多用によって起こる典型的なトラブルです。安全のため、長い下り坂ではフットブレーキだけに頼らず後述のエンジンブレーキを併用することが大切です。
油圧式のディスクブレーキやドラムブレーキによって、車輪の回転を直接抑えます。乗用車の場合、フットブレーキは前後すべての車輪に作用します。ただし前輪と後輪ではかかる力の配分が異なり、減速時には車体の前方に荷重がかかるため前輪ブレーキに強い制動力が割り当てられています。そのため前輪には大径のディスクローターや強力なキャリパーが備えられ、車体を効率的に減速させることができます。
フットブレーキは減速力が高く扱いやすい一方、長時間連続で使うと過熱しやすいという特性があります。前述のフェード現象・ベーパーロック現象はフットブレーキの多用によって起こる典型的なトラブルです。安全のため、長い下り坂ではフットブレーキだけに頼らず後述のエンジンブレーキを併用することが大切です。
エンジンブレーキ
エンジンブレーキとは、エンジンの回転抵抗を利用して車を減速させる方法です。
アクセルペダルを離してエンジンへの燃料供給を絞ると、エンジンの回転数が落ちる際にタイヤの回転を引っ張るような抵抗力が生じ、車速が徐々に落ちていきます。これがエンジンブレーキの原理です。車種を問わずアクセルを緩めれば常に働きますが、低いギアほど強い減速力を得られるのが特徴です。AT車でもMT車でも、シフトダウン(ギアを下げる)するほどエンジンブレーキは強力に働きます。
エンジンブレーキはフットブレーキを補助する役割を持ち、特に長い坂道や高速走行からの減速時に有効です。
例えば下り坂ではあらかじめ低速ギアに入れておくことで、フットブレーキへの負担を減らしブレーキの過熱を防ぐことができます。ただしエンジンブレーキ単体で車両を完全停止させることはできないため、あくまで「減速用」と割り切り、停止にはフットブレーキや後述のパーキングブレーキを併用します。
アクセルペダルを離してエンジンへの燃料供給を絞ると、エンジンの回転数が落ちる際にタイヤの回転を引っ張るような抵抗力が生じ、車速が徐々に落ちていきます。これがエンジンブレーキの原理です。車種を問わずアクセルを緩めれば常に働きますが、低いギアほど強い減速力を得られるのが特徴です。AT車でもMT車でも、シフトダウン(ギアを下げる)するほどエンジンブレーキは強力に働きます。
エンジンブレーキはフットブレーキを補助する役割を持ち、特に長い坂道や高速走行からの減速時に有効です。
例えば下り坂ではあらかじめ低速ギアに入れておくことで、フットブレーキへの負担を減らしブレーキの過熱を防ぐことができます。ただしエンジンブレーキ単体で車両を完全停止させることはできないため、あくまで「減速用」と割り切り、停止にはフットブレーキや後述のパーキングブレーキを併用します。
パーキングブレーキ(サイドブレーキ)
パーキングブレーキは、駐車時に車輪を機械的にロックして車を動かないようにする装置です。
ハンドブレーキ、サイドブレーキとも呼ばれ、近年はレバーではなく足踏み式や電動式(スイッチ操作)の車両も増えています。いずれの方式でも通常は後輪のみに作用し、ワイヤーやモーターでブレーキパッド(またはブレーキシュー)を強制的に押し付けて車輪を固定します。
パーキングブレーキは本来、停車中に車が動き出さないよう保持するためのものですが、非常時には走行中の減速手段として使うことも可能です。ただしフットブレーキに比べると制動力は弱く、後輪のみを制動するためかけ方に注意が必要です。一気に強く引いたり踏み込んだりすると後輪がロックしてスピンする恐れがあるため、徐々に作動させるのがポイントです。
手動レバーなら「少しずつ引き上げる or 断続的に引く」、足踏み式なら「ゆっくり深く踏む」を意識しましょう。電動パーキングブレーキの場合も、スイッチを一定時間引き続けることで非常ブレーキとして作動する設計になっています(車種によりますが、多くの車で非常時に使用可能です)。
なお、走行中にパーキングブレーキを使う際はエンジンを絶対に停止しないことも重要です。エンジンを切ってしまうとパワーステアリングなどのアシストが失われ、ハンドル操作が極めて重くなります。非常時こそエンジンはかけたまま、ハンドルとブレーキの両方を効かせられる状態を保ってください。
ハンドブレーキ、サイドブレーキとも呼ばれ、近年はレバーではなく足踏み式や電動式(スイッチ操作)の車両も増えています。いずれの方式でも通常は後輪のみに作用し、ワイヤーやモーターでブレーキパッド(またはブレーキシュー)を強制的に押し付けて車輪を固定します。
パーキングブレーキは本来、停車中に車が動き出さないよう保持するためのものですが、非常時には走行中の減速手段として使うことも可能です。ただしフットブレーキに比べると制動力は弱く、後輪のみを制動するためかけ方に注意が必要です。一気に強く引いたり踏み込んだりすると後輪がロックしてスピンする恐れがあるため、徐々に作動させるのがポイントです。
手動レバーなら「少しずつ引き上げる or 断続的に引く」、足踏み式なら「ゆっくり深く踏む」を意識しましょう。電動パーキングブレーキの場合も、スイッチを一定時間引き続けることで非常ブレーキとして作動する設計になっています(車種によりますが、多くの車で非常時に使用可能です)。
なお、走行中にパーキングブレーキを使う際はエンジンを絶対に停止しないことも重要です。エンジンを切ってしまうとパワーステアリングなどのアシストが失われ、ハンドル操作が極めて重くなります。非常時こそエンジンはかけたまま、ハンドルとブレーキの両方を効かせられる状態を保ってください。
手で引くタイプのパーキングブレーキは、非常時には徐々に引き上げて使用することが大切です。急に強く引くと後輪がロックしスピンする危険があるため絶対に避けましょう。
ブレーキが効かなくなったときの緊急対処法
1. 周囲に異常を知らせる
ブレーキが効かないと気付いたら、まずハザードランプを点滅させて他車に異常事態を知らせます。夜間であればライトを上向きにしたり、必要に応じクラクションを鳴らすなどして周囲との衝突リスクを下げましょう。アクセルから足を離し、惰性で走行しながら次の行動に移ります。
2. エンジンブレーキで減速する
シフトダウンを順次行い、エンジンブレーキで車速を落とします。AT車の場合はDレンジから手動で「3 → 2 → 1(L)」と一段ずつギアを落としていきます。MT車でも同様に、高いギアから徐々にシフトダウンしてください。決して慌てて一気に低速ギアに入れないようにします。一段飛ばしで急激にシフトダウンすると駆動輪がロックして車が不安定になる恐れがあり危険です。基本は落ち着いて1段ずつギアを落とし、エンジンブレーキの効きを最大限利用しましょう。十分に減速できるとハンドルや車体の振動が落ち着き、停止の準備が安全に行えます。
3. パーキングブレーキで完全停止する
エンジンブレーキで速度がかなり落ちたら、パーキングブレーキを使って車両を停止させます。手引き式の場合は「少し引く→緩める」を繰り返すか、弱めの力でゆっくりと引き上げていきます。足踏み式の場合は段階的に何度かに分けて踏み込み、徐々に制動力を高めます。このとき絶対に一気に強く引いたり踏んだりしないことが肝心です。急激にパーキングブレーキを作動させると後輪がロックし、最悪の場合スピンして制御不能になります。あくまで慎重に、車体の安定を保ちながら止めましょう。幸い近くに緩やかな上り坂や避難帯(ランナウトエリア等)があれば、そちらに進んで自然減速させるのも有効です。
4. 最後の手段を講じる
エンジンブレーキ+パーキングブレーキでもなお減速が間に合わず衝突の危険が切迫している場合、やむを得ずガードレールや壁に車体を擦り付けて強制停止させる方法もあります。前方の車に追突しそうな時や、人身事故を起こす恐れが高い場合には、自車を犠牲にしてでも周囲への被害を最小限に抑える判断が必要です。実行する際はハンドルを切りすぎずに車体側面を接触させ、できるだけ減速してから行いましょう。乗員がいる場合は「つかまって!」と声をかけ、シートに身を預け頭と体を守る姿勢を取らせます。非常停止の覚悟を持って、被害を最小限に食い止めてください。
5. 停車後の対応
無事に車両が停止したら、速やかに安全な場所へ避難し二次事故を防止します。可能であれば三角表示板を設置し、ロードサービスや警察に連絡しましょう。ブレーキが故障した車を自走するのは大変危険です。レッカー移動を依頼し、しかるべき整備工場で原因を特定・修理してもらってください。原因が判明し解決するまでは絶対に自分で運転しないことが鉄則です。
ブレーキトラブルの予防策と日常点検のポイント
ブレーキの効き具合を定期チェック
普段からブレーキペダルの感触に注意し、違和感がないか確認しましょう。例えば駐車場など安全な場所で停車中にエンジンをかけ、思い切りブレーキを踏んでみます。踏み込み量に対して踏みごたえが異常に柔らかい、奥まで沈み込む、ポンプのように何度か踏まないと効かないといった症状があれば、ブレーキフルードのエア噛みや漏れ、マスターシリンダー不良などの可能性があります。すぐに整備工場で点検しましょう。
ブレーキオイル(フルード)の点検・交換
ボンネットを開けてブレーキフルードのリザーバータンクを確認します。液面が「MAX」と「MIN」の間にあるかチェックし、不足していれば漏れの有無も含めて原因を調べます。フルードの色が黄透明から茶色・黒に変色していたら劣化のサインなので交換時期です。ブレーキフルードは通常2年ごと程度の定期交換が推奨されます。水分を吸収して沸点が低下し性能が落ちるため、古いままではベーパーロックの原因にもなります。必ず指定の規格品に交換しましょう。
警告灯の監視
走行中にメーターパネル内のブレーキ警告灯が点灯したら注意が必要です。ブレーキ系統の何らかの異常やブレーキオイル不足の場合、赤や黄色の警告ランプが点きます(※パーキングブレーキを引いた状態でも赤ランプが点灯しますが、その場合は解除すれば消えます)。警告灯が消えない、もしくは走行中に点灯した場合は速やかに安全な場所へ停車し、原因を点検してください。ABSやブレーキアシストの警告灯が点いた場合も同様です。電子制御の異常は自力で対処できないため、整備工場に連絡しましょう。
タイヤの状態管理
ブレーキ性能はタイヤのグリップ力によっても左右されます。タイヤの空気圧を適正に保ち、溝(トレッド)が十分残っているか定期的に点検しましょう。溝が極端に摩耗していると、雨天時にハイドロプレーニングを起こしやすく制動距離が大幅に伸びてしまいます。またスタッドレスタイヤでも溝が減ると氷雪路で効かなくなるので、寿命を過ぎたタイヤは早めに新品に交換してください。
走行中のブレーキ酷使を避ける
日頃からエンジンブレーキを上手に活用し、フットブレーキの連続使用をできるだけ避けましょう。特に長い下り坂ではDレンジのまま惰性で下るのではなく、適宜シフトダウンして低速ギアで走行します。こまめにギアを落として速度を調整すればフットブレーキを踏む回数も減り、フェード現象の予防につながります。また高速道路でも減速時にいきなりブレーキに頼らず、アクセルオフでじわじわ減速する癖をつけると良いでしょう。
足元の整理整頓
車内にペットボトルや小物を放置しない習慣も大切です。運転席足元に物が転がってブレーキペダルを踏めなくなる事故が毎年のように起きています。マットのずれやめくれがペダルに干渉する例もあります。乗車前と運転中、足元に違和感がないか常に注意を払いましょう。
万全を期すなら、プロの整備士による定期点検も欠かせません。ブレーキパッドの厚みやディスクの状態、各部の動作などを定期的に点検・整備してもらうことでトラブルを未然に防げます。ブレーキの効きが悪いと感じたら早めに工場に相談し、必要に応じて部品交換を検討してください。安全を守るブレーキだけに、異常を感じたままの運転は厳禁です。
まとめ
ブレーキが効かなくなる原因には、熱によるフェード・ベーパーロック現象から部品の故障や摩耗、タイヤの滑走など様々なものがあります。
日頃からメンテナンスを心がけ、長い下り坂ではエンジンブレーキを併用するなど予防策を徹底しましょう。それでも万が一走行中にブレーキが効かなくなった場合は、落ち着いてエンジンブレーキとパーキングブレーキで減速・停止させることが肝要です。
周囲への合図や最終手段も含め、本記事で紹介した対処法を頭に入れておけば、いざというとき必ず役立つはずです。日頃から緊急時をイメージトレーニングしつつ、安全運転を心掛けてくださいね。大切な命を守るためにも、ブレーキの異常には決して油断せず、常に万全の準備をしておきましょう。
日頃からメンテナンスを心がけ、長い下り坂ではエンジンブレーキを併用するなど予防策を徹底しましょう。それでも万が一走行中にブレーキが効かなくなった場合は、落ち着いてエンジンブレーキとパーキングブレーキで減速・停止させることが肝要です。
周囲への合図や最終手段も含め、本記事で紹介した対処法を頭に入れておけば、いざというとき必ず役立つはずです。日頃から緊急時をイメージトレーニングしつつ、安全運転を心掛けてくださいね。大切な命を守るためにも、ブレーキの異常には決して油断せず、常に万全の準備をしておきましょう。