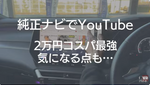Rolling 40's vol.54 原風景を超えて
更新日:2024.09.09

※この記事には広告が含まれます
古いモノが大好きだというと、どうしてか少し「辛気臭く」思われることもある。乗り物に関して言うと、確かに私も20代前半は時代的な背景もあるが、最新鋭のモノしか興味がなかった。
text:大鶴義丹 [aheadアーカイブス vol.124 2013年3月号]
text:大鶴義丹 [aheadアーカイブス vol.124 2013年3月号]
- Chapter
- vol.54 原風景を超えて
vol.54 原風景を超えて
古いモノは新しいモノの登場と同時に消えるべきであり、それが森羅万象全ての運命であるとさえ思っていた。自分の前に広がる時間が全ての価値観のデフォルトであり最先端だと奢り昂った。
だが、数年もすると、自分自身の価値観があっという間に時代遅れになっていくという現実に突き当たった。あがけばあがくほどに、次から次へと湧き出る新しいモノに呑み込まれていく。
だがそれでも人間は生きていかなくてはならないし、それが嫌でも生きてしまうのが人間の強さである。そんな時間の中で知ることができたのは、最新鋭とは素晴らしくもあるが同時にとても脆いということだった。若き自分の価値観を駆逐した最新の価値観も、登場と同時に滅びのタイムスイッチが押されることになる。
すると最新鋭のモノに対する視線が大きく変わった。だが、安っぽい懐古主義ではない。最先端ゆえの素晴らしいスペックや新しい価値観を否定するのではなく、自分に必要なモノ、イコール最新鋭ではないと気が付いたことだ。
乗り物に関してのみの話だが、技術的な進歩はエコ以外は大体出尽くしているというのが現状だ。ターボという言葉に意味もなく興奮したり、毎年ごとに発売されるクルマのエンジン出力が10馬力ずつ上がっていくような時代とはわけが違う。
そういう進化を5年前くらいまでは執拗に期待していたが、もうその高出力高性能というベクトルでの進化というものはないと思って良いだろう。現実的な領域では全て出尽くしているのだから、更なる進化を期待しても何の意味もない。
とくにバイクに関しては、本当に高性能化が著しい進歩を遂げてしまった。世界クラスのライダーしか乗りこなせないような高性能なものが150万円も出せば買えてしまうような、少し特異な状況になってしまっている。電子制御の進化とローコスト化も著しく、10年前には数千万円したテクノロジーも当たり前のようにデフォルトの値段の中に含まれている次第だ。
当然そんなマシンをアマチュアが安全に乗りこなせる訳もなく、その性能の一部を「つまみ食い」しては自己満足しているというのが、今の最新高性能バイクの現状である。
そういうバイクを所持して満足していたこともある。またこれからも衝動買いすることもあるだろう。だが、そんなマシンが本当に自分を満足させてくれるとは思ってもいない。
バイクに何を求めるか。バイクメディアに関わる仕事をしているので、当然そんな質問をされることが多々ある。しかし実は自分が一番わかっていないことなので、それを聞かれるととても困ってしまう。
限界性能の追求。笑止、バイクレーサーに憧れ真似事をしてみたこともあるが、本職の連中の真の才能を目の当たりにすると、そんなことは口にするのも恥ずかしいことだと分かってしまう。
旅の友。バイクで関西くらいまでのロングツーリングはたまにするが、本当の意味でロングツーリングを敢行している人たちからしたら、私など素人同然だろう。
でも、それでも二輪を乗り続けてきた気持ちだけは「玄人レベル」だと自負している。では一体その原動力とは何なのだろう。
最近、某バイク雑誌のトークライブに出演した。まさにバイクマニアと呼ばれるに相応しい「羅漢150人」の前で自分のバイクライフやバイク観を話させて貰った。ずっと乗り続けてきた気持ちを堂々と語らせてもらった。すると思った以上に歓迎されている気がして嬉しかった。
そんな空間にいると、自分のバイクの原風景を改めて思い出すことができた。
中学の校庭に卒業した先輩が乗りつけてきたホンダの四気筒の音だ。マフラーを改造して無駄に音を大きくしてあるモノだった。
そのバイクに跨らせてもらい、アクセルを初めて捻ったときに自分を突き抜けていった音。激しいようでどこか柔らかい高音が、アクセルの動きに合わせて響いていく。まるで巨大な楽器だと思った。それがどうしても忘れられず、その手の四気筒のバイクばかり乗り続けている。
今の時代、もっと色々なエンジン形式が高性能を誇っているというのに、どうしてもその手のものに触手が伸びない。何だかんだと理由を付けては、四気筒の音を求めてしまう。メカニカルな話ではあるが、今の時代は四気筒のバイクの優位性というのは過去の遺物だ。
しかしそれでも四気筒が奏でる音を求め続けてしまう。それが聞こえないとバイクに乗っている気がしないのだ。悪く言えば心的外傷・トラウマだ。そのときに知ってしまったバイクの存在感を今でも忘れられないのだろう。
結局、性能だの旅だのはどうでも良くて、あのときの音を聞き続けたいがためにバイクに乗り続けているのかもしれない。でもそんな小さなことだけで、これだけの長い間情熱を保てるのだから、出てきた答えがそれでも私は構わない。
だが、数年もすると、自分自身の価値観があっという間に時代遅れになっていくという現実に突き当たった。あがけばあがくほどに、次から次へと湧き出る新しいモノに呑み込まれていく。
だがそれでも人間は生きていかなくてはならないし、それが嫌でも生きてしまうのが人間の強さである。そんな時間の中で知ることができたのは、最新鋭とは素晴らしくもあるが同時にとても脆いということだった。若き自分の価値観を駆逐した最新の価値観も、登場と同時に滅びのタイムスイッチが押されることになる。
すると最新鋭のモノに対する視線が大きく変わった。だが、安っぽい懐古主義ではない。最先端ゆえの素晴らしいスペックや新しい価値観を否定するのではなく、自分に必要なモノ、イコール最新鋭ではないと気が付いたことだ。
乗り物に関してのみの話だが、技術的な進歩はエコ以外は大体出尽くしているというのが現状だ。ターボという言葉に意味もなく興奮したり、毎年ごとに発売されるクルマのエンジン出力が10馬力ずつ上がっていくような時代とはわけが違う。
そういう進化を5年前くらいまでは執拗に期待していたが、もうその高出力高性能というベクトルでの進化というものはないと思って良いだろう。現実的な領域では全て出尽くしているのだから、更なる進化を期待しても何の意味もない。
とくにバイクに関しては、本当に高性能化が著しい進歩を遂げてしまった。世界クラスのライダーしか乗りこなせないような高性能なものが150万円も出せば買えてしまうような、少し特異な状況になってしまっている。電子制御の進化とローコスト化も著しく、10年前には数千万円したテクノロジーも当たり前のようにデフォルトの値段の中に含まれている次第だ。
当然そんなマシンをアマチュアが安全に乗りこなせる訳もなく、その性能の一部を「つまみ食い」しては自己満足しているというのが、今の最新高性能バイクの現状である。
そういうバイクを所持して満足していたこともある。またこれからも衝動買いすることもあるだろう。だが、そんなマシンが本当に自分を満足させてくれるとは思ってもいない。
バイクに何を求めるか。バイクメディアに関わる仕事をしているので、当然そんな質問をされることが多々ある。しかし実は自分が一番わかっていないことなので、それを聞かれるととても困ってしまう。
限界性能の追求。笑止、バイクレーサーに憧れ真似事をしてみたこともあるが、本職の連中の真の才能を目の当たりにすると、そんなことは口にするのも恥ずかしいことだと分かってしまう。
旅の友。バイクで関西くらいまでのロングツーリングはたまにするが、本当の意味でロングツーリングを敢行している人たちからしたら、私など素人同然だろう。
でも、それでも二輪を乗り続けてきた気持ちだけは「玄人レベル」だと自負している。では一体その原動力とは何なのだろう。
最近、某バイク雑誌のトークライブに出演した。まさにバイクマニアと呼ばれるに相応しい「羅漢150人」の前で自分のバイクライフやバイク観を話させて貰った。ずっと乗り続けてきた気持ちを堂々と語らせてもらった。すると思った以上に歓迎されている気がして嬉しかった。
そんな空間にいると、自分のバイクの原風景を改めて思い出すことができた。
中学の校庭に卒業した先輩が乗りつけてきたホンダの四気筒の音だ。マフラーを改造して無駄に音を大きくしてあるモノだった。
そのバイクに跨らせてもらい、アクセルを初めて捻ったときに自分を突き抜けていった音。激しいようでどこか柔らかい高音が、アクセルの動きに合わせて響いていく。まるで巨大な楽器だと思った。それがどうしても忘れられず、その手の四気筒のバイクばかり乗り続けている。
今の時代、もっと色々なエンジン形式が高性能を誇っているというのに、どうしてもその手のものに触手が伸びない。何だかんだと理由を付けては、四気筒の音を求めてしまう。メカニカルな話ではあるが、今の時代は四気筒のバイクの優位性というのは過去の遺物だ。
しかしそれでも四気筒が奏でる音を求め続けてしまう。それが聞こえないとバイクに乗っている気がしないのだ。悪く言えば心的外傷・トラウマだ。そのときに知ってしまったバイクの存在感を今でも忘れられないのだろう。
結局、性能だの旅だのはどうでも良くて、あのときの音を聞き続けたいがためにバイクに乗り続けているのかもしれない。でもそんな小さなことだけで、これだけの長い間情熱を保てるのだから、出てきた答えがそれでも私は構わない。
----------------------------------------
text:大鶴義丹/Gitan Ohtsuru
1968年生まれ。俳優・監督・作家。知る人ぞ知る“熱き”バイク乗りである。本人によるブログ「不思議の毎日」はameblo.jp/gitan1968
text:大鶴義丹/Gitan Ohtsuru
1968年生まれ。俳優・監督・作家。知る人ぞ知る“熱き”バイク乗りである。本人によるブログ「不思議の毎日」はameblo.jp/gitan1968