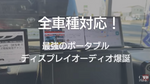ピラーの種類と役割とは?AピラーからDピラーまで徹底解説【豆知識あり】
更新日:2025.09.02

※この記事には広告が含まれます
車の解説記事やカタログで「Aピラー」や「Bピラー」という言葉を目にしたことはありませんか? これは車の柱部分を指す用語ですが、具体的にどの部位でどんな役割を果たしているのでしょうか。
ピラー(pillar)は車の構造に欠かせない重要パーツであり、安全性やデザインにも大きく関わっています。本記事では、ピラーの種類(Aピラー、Bピラー、Cピラー、Dピラー)を分かりやすく紹介し、その位置や役割、安全性への影響、進化の歴史、車種ごとの違い、素材の違いなどを豆知識を交えて解説します。
ピラー(pillar)は車の構造に欠かせない重要パーツであり、安全性やデザインにも大きく関わっています。本記事では、ピラーの種類(Aピラー、Bピラー、Cピラー、Dピラー)を分かりやすく紹介し、その位置や役割、安全性への影響、進化の歴史、車種ごとの違い、素材の違いなどを豆知識を交えて解説します。
この記事をざっくり言うと
- ピラーはクルマのボディとルーフをつなぐ柱状の部分であり、前方から順にA、B、C、Dと名付けられている
- ピラーは単に屋根を支えるだけでなく、ボディの強度を保つ重要な役割を果たしており、クルマのデザインにも大きな影響を与えている
- 各ピラーはそれぞれ異なる役割と特徴を持っており、メーカーごとに工夫を凝らしている部分である
- Chapter
- ピラーとは?車の柱の種類と役割を解説
- Aピラーとは|フロントガラス両脇を支える安全支柱
- Bピラーとは|車体中央で側面衝突を守る柱
- Cピラーとは|リアサイドを支える柱とデザイン性
- Dピラーとは|SUV・ワゴンの後端を補強する柱
- ピラーレス車のメリットと安全対策|Bピラーなしの仕組み
- 車種別ピラー本数の違い|セダン・SUV・バスまで比較
- セダン・クーペのピラー本数
- ハッチバック・SUVのピラー本数
- ステーションワゴン・ミニバンのピラー本数
- ピックアップトラックのピラー構成
- リムジン・バスの複数ピラー
- ピラー素材の種類と最新技術|ハイテン鋼・アルミ・カーボン
- 高張力鋼板(ハイテン鋼)ピラー
- アルミニウム合金ピラー
- カーボンファイバー製ピラー
- ピラーに関する豆知識Q&A|死角対策から透明ピラーまで
- Q1: 乗用車のピラーは何本ある?
- Q2: ピラー名称がアルファベットの理由は?
- Q3: ピラーレス車は実在した?
- Q4: ピラーが生む運転中の死角とは?
- Q5: 昔の車のアンテナはどこに刺さっていた?
- まとめ|ピラー種類を知って安全で快適なカーライフを
ピラーとは?車の柱の種類と役割を解説
ピラー(pillar)とは英語で「柱」を意味し、車においてはボディ(車体)とルーフ(屋根)をつなぐ柱部分を指します。車を真横から見たときに立っている柱状のフレーム部分で、車の骨格を形作る重要な構造部品です。
ピラーにはアルファベットの名前が付けられており、最も前方の柱から順にA、B、C、D…と呼ばれます。
一般的な乗用車では、前からAピラー、Bピラー、Cピラーまで(セダンの場合)またはA~Dピラーまで(ワゴンやミニバンの場合)存在します。例えば、セダンは通常3本(A~Cピラー)、ステーションワゴンやミニバン、SUVは4本(A~Dピラー)のピラーがあります。さらに車種によってはピラーの数が増えることもあり、大型バスやリムジンではH~Jピラー(アルファベットのHからJ)まで存在する例もあります。
つまり非常に車体が長い車では、Aから始まる柱の呼び名がアルファベット順に後方まで増えていくわけです。
ピラーは単に屋根を支えるだけでなく、車体剛性(ボディの強度)を保つための重要部品です。現代の多くの車はモノコック構造(骨格と外板が一体となった構造)を採用していますが、その中でピラーは乗員を守る頑丈なフレームとして機能し、衝突時に乗員の生存空間を確保する役割も担っています。
また、ピラーは位置ごとに役割が異なり、車のデザインにも大きな影響を与える部分です。各メーカーは視界確保やデザイン性のためにピラー形状にさまざまな工夫を凝らしています。
では、ピラーには具体的にどのような種類があり、それぞれどこにあって何をしているのでしょうか。以下、Aピラーから順に各ピラーの特徴と役割を見ていきましょう。
ピラーにはアルファベットの名前が付けられており、最も前方の柱から順にA、B、C、D…と呼ばれます。
一般的な乗用車では、前からAピラー、Bピラー、Cピラーまで(セダンの場合)またはA~Dピラーまで(ワゴンやミニバンの場合)存在します。例えば、セダンは通常3本(A~Cピラー)、ステーションワゴンやミニバン、SUVは4本(A~Dピラー)のピラーがあります。さらに車種によってはピラーの数が増えることもあり、大型バスやリムジンではH~Jピラー(アルファベットのHからJ)まで存在する例もあります。
つまり非常に車体が長い車では、Aから始まる柱の呼び名がアルファベット順に後方まで増えていくわけです。
ピラーは単に屋根を支えるだけでなく、車体剛性(ボディの強度)を保つための重要部品です。現代の多くの車はモノコック構造(骨格と外板が一体となった構造)を採用していますが、その中でピラーは乗員を守る頑丈なフレームとして機能し、衝突時に乗員の生存空間を確保する役割も担っています。
また、ピラーは位置ごとに役割が異なり、車のデザインにも大きな影響を与える部分です。各メーカーは視界確保やデザイン性のためにピラー形状にさまざまな工夫を凝らしています。
では、ピラーには具体的にどのような種類があり、それぞれどこにあって何をしているのでしょうか。以下、Aピラーから順に各ピラーの特徴と役割を見ていきましょう。
Aピラーとは|フロントガラス両脇を支える安全支柱
Aピラーはフロントガラスの左右両脇に位置する柱で、運転席・助手席の前方両側にあるため「フロントピラー」とも呼ばれます。
車の最前部を支える柱であり、正面衝突や横転事故の際にルーフの崩壊を防ぎ、乗員の生存空間を守るという大切な役割があります。頑丈なAピラーによってキャビン(乗員空間)の形状が保たれることで、万一の事故時にも乗員を衝撃から守る構造になっています。
Aピラーは安全のため強度が求められる一方で、太く頑丈にすると運転席から斜め前の視界を遮り「死角」を増やしてしまうという欠点があります。運転中、Aピラーが太いとカーブで歩行者や自転車がピラーの陰に隠れて見えにくくなるなど、安全運転上の課題となります。
そのため自動車メーカーは、必要な強度を確保しつつ運転視界をなるべく妨げないAピラーの設計に知恵を絞っています。具体例として、Aピラー付け根に小さな三角窓を設けて視界を補助する車(トヨタ・プリウス、ノア/ヴォクシーなど)や、Aピラー自体を2本に分割して間に隙間を設け視界を確保する車(ホンダ・フリード、N-BOXなど)もあります。こうした工夫により、頑丈さと視界確保の両立を図っているのです。
さらにAピラーの角度(傾き)は車の空気抵抗や室内空間にも影響します。ピラーを前方に寝かせて角度を緩くすれば空気の抵抗が減り高速走行や燃費に有利ですが、その分フロントガラスが寝て車内の頭上空間は狭くなります。逆にピラーを立てて角度を垂直に近づければ、室内空間(特に頭上や前方のゆとり)を広く取れますが、空気抵抗は増えがちです。
そのため、スポーツカーやエコカーではAピラーを寝かせて流線型のフォルムにし(空気抵抗低減を重視)、ミニバンやワゴン車ではAピラーを立てて室内の居住空間を広く確保する(居住性重視)といった設計の違いが見られます。
車の最前部を支える柱であり、正面衝突や横転事故の際にルーフの崩壊を防ぎ、乗員の生存空間を守るという大切な役割があります。頑丈なAピラーによってキャビン(乗員空間)の形状が保たれることで、万一の事故時にも乗員を衝撃から守る構造になっています。
Aピラーは安全のため強度が求められる一方で、太く頑丈にすると運転席から斜め前の視界を遮り「死角」を増やしてしまうという欠点があります。運転中、Aピラーが太いとカーブで歩行者や自転車がピラーの陰に隠れて見えにくくなるなど、安全運転上の課題となります。
そのため自動車メーカーは、必要な強度を確保しつつ運転視界をなるべく妨げないAピラーの設計に知恵を絞っています。具体例として、Aピラー付け根に小さな三角窓を設けて視界を補助する車(トヨタ・プリウス、ノア/ヴォクシーなど)や、Aピラー自体を2本に分割して間に隙間を設け視界を確保する車(ホンダ・フリード、N-BOXなど)もあります。こうした工夫により、頑丈さと視界確保の両立を図っているのです。
さらにAピラーの角度(傾き)は車の空気抵抗や室内空間にも影響します。ピラーを前方に寝かせて角度を緩くすれば空気の抵抗が減り高速走行や燃費に有利ですが、その分フロントガラスが寝て車内の頭上空間は狭くなります。逆にピラーを立てて角度を垂直に近づければ、室内空間(特に頭上や前方のゆとり)を広く取れますが、空気抵抗は増えがちです。
そのため、スポーツカーやエコカーではAピラーを寝かせて流線型のフォルムにし(空気抵抗低減を重視)、ミニバンやワゴン車ではAピラーを立てて室内の居住空間を広く確保する(居住性重視)といった設計の違いが見られます。
Bピラーとは|車体中央で側面衝突を守る柱
Bピラーは車体の中央部分に位置する柱で、前席ドアと後席ドアの間にあります。4ドア車の場合、ちょうど前後ドアの境目に立つ柱であり、**「センターピラー」**とも呼ばれます。運転席のすぐ後ろ、後部座席の前方にあたる柱ですね。
Bピラーは側面衝突事故の際に乗員を守る重要な役割を果たします。
車の真横からの衝突では、この中央の柱が衝撃を受け止めて乗員スペースへの侵入を防ぐ壁となります。また、Bピラーにはシートベルトの上部アンカー(固定金具)が取り付けられている車種も多く、シートベルトをしっかり支える強度も求められます。そのため、Bピラーも衝突安全性の観点から非常に頑丈に作られている部分です。
ところで、1970~80年代にはBピラーが存在しない車(ピラーレス車)も市販されていました。これは「ハードトップ」と呼ばれるスタイルで、ドアの窓枠にもフレームが無く全てのサイドウインドウを開けると開放的な空間が生まれるデザインです。
見た目のスタイリッシュさから日本でも一時期流行しましたが、車体剛性や安全性の問題があったため現在では市販車では見られなくなりました。Bピラーが無いと側面から見たデザインはすっきりしますが、衝突時の強度不足やボディの歪みが生じやすい欠点があり、90年代以降の安全基準強化に伴い姿を消したのです。
Bピラーは側面衝突事故の際に乗員を守る重要な役割を果たします。
車の真横からの衝突では、この中央の柱が衝撃を受け止めて乗員スペースへの侵入を防ぐ壁となります。また、Bピラーにはシートベルトの上部アンカー(固定金具)が取り付けられている車種も多く、シートベルトをしっかり支える強度も求められます。そのため、Bピラーも衝突安全性の観点から非常に頑丈に作られている部分です。
ところで、1970~80年代にはBピラーが存在しない車(ピラーレス車)も市販されていました。これは「ハードトップ」と呼ばれるスタイルで、ドアの窓枠にもフレームが無く全てのサイドウインドウを開けると開放的な空間が生まれるデザインです。
見た目のスタイリッシュさから日本でも一時期流行しましたが、車体剛性や安全性の問題があったため現在では市販車では見られなくなりました。Bピラーが無いと側面から見たデザインはすっきりしますが、衝突時の強度不足やボディの歪みが生じやすい欠点があり、90年代以降の安全基準強化に伴い姿を消したのです。
Cピラーとは|リアサイドを支える柱とデザイン性
Cピラーは車体後部、後席のさらに後ろ側に位置する柱です。
セダンであれば後部座席の後ろ、トランクと後席窓の間にある柱がCピラーにあたります。車のリア部分を支える構造材であり、車体全体の強度を保つ上で重要な役割を担っています。特にルーフ後端を支える支柱として、リアガラスやトランク周りの剛性を高めています。
車種によってはCピラーが非常に太く設計されている場合もあります。
例えば一部の高級セダンではCピラーを極端に太くし、後席の窓面積を小さめにすることで後部座席の乗員のプライバシーを高める工夫をしていることがあります。外から見えにくくするためにあえて柱部分を厚くデザインしているわけです。
またCピラーの太さや形状は車のサイドから見た印象(プロポーション)を決定づける要素でもあります。クーペスタイルの車ではCピラーを長く傾斜させて滑らかなルーフラインを描き、逆にボックス型の車では短く立てて実用性重視のシルエットにするなど、デザイン上のバリエーションも豊富です。
セダンであれば後部座席の後ろ、トランクと後席窓の間にある柱がCピラーにあたります。車のリア部分を支える構造材であり、車体全体の強度を保つ上で重要な役割を担っています。特にルーフ後端を支える支柱として、リアガラスやトランク周りの剛性を高めています。
車種によってはCピラーが非常に太く設計されている場合もあります。
例えば一部の高級セダンではCピラーを極端に太くし、後席の窓面積を小さめにすることで後部座席の乗員のプライバシーを高める工夫をしていることがあります。外から見えにくくするためにあえて柱部分を厚くデザインしているわけです。
またCピラーの太さや形状は車のサイドから見た印象(プロポーション)を決定づける要素でもあります。クーペスタイルの車ではCピラーを長く傾斜させて滑らかなルーフラインを描き、逆にボックス型の車では短く立てて実用性重視のシルエットにするなど、デザイン上のバリエーションも豊富です。
Dピラーとは|SUV・ワゴンの後端を補強する柱
Dピラーは、ステーションワゴンやミニバン、SUVなど後部にもう一枚窓がある車種に存在する柱です。
セダンは後席窓の後にすぐトランク部分となるため通常Cピラーまでですが、ワゴンやSUV、大型ミニバンなどでは後席窓の後ろにも荷室用のサイドウインドウがあり、その区切りにDピラーが立ちます。言い換えれば、後部座席のさらに後方、車体の最後尾近くにある柱がDピラーです。
Dピラーは車体の後端の剛性を担う重要な柱であり、視界への直接的な制約が他の主要ピラーに比べて少ない場合があるため、デザイナーにとって特徴的なデザイン処理を施しやすい部分とも言えます。
車種によってDピラーの形状は様々で、傾斜をつけてスタイリッシュでスポーティな印象を与えることもできますし、垂直に近い角度で立てて荷室空間を目一杯確保する実用的なデザインにもできます。例えばSUVではルーフ後端を絞り込むように傾けて躍動感を出すケースもあれば、ワンボックス車では箱型に近い形状で車内スペースを優先するケースもあります。
なお、Dピラーよりさらに後ろのピラー(Eピラー以降)は一般的な乗用車ではあまり登場しません。
乗用車でDピラーまであるのは主にステーションワゴン、ミニバン、SUVですが、車体の長い車(リムジンやバスなど)ではE、Fと増えてアルファベット順に命名され、超大型車両もあります。
セダンは後席窓の後にすぐトランク部分となるため通常Cピラーまでですが、ワゴンやSUV、大型ミニバンなどでは後席窓の後ろにも荷室用のサイドウインドウがあり、その区切りにDピラーが立ちます。言い換えれば、後部座席のさらに後方、車体の最後尾近くにある柱がDピラーです。
Dピラーは車体の後端の剛性を担う重要な柱であり、視界への直接的な制約が他の主要ピラーに比べて少ない場合があるため、デザイナーにとって特徴的なデザイン処理を施しやすい部分とも言えます。
車種によってDピラーの形状は様々で、傾斜をつけてスタイリッシュでスポーティな印象を与えることもできますし、垂直に近い角度で立てて荷室空間を目一杯確保する実用的なデザインにもできます。例えばSUVではルーフ後端を絞り込むように傾けて躍動感を出すケースもあれば、ワンボックス車では箱型に近い形状で車内スペースを優先するケースもあります。
なお、Dピラーよりさらに後ろのピラー(Eピラー以降)は一般的な乗用車ではあまり登場しません。
乗用車でDピラーまであるのは主にステーションワゴン、ミニバン、SUVですが、車体の長い車(リムジンやバスなど)ではE、Fと増えてアルファベット順に命名され、超大型車両もあります。
ピラーレス車のメリットと安全対策|Bピラーなしの仕組み
前述のように、かつてはハードトップと呼ばれるBピラーのない車が存在しました。
近年では構造上の理由から乗用車で完全なピラーレス車はほとんど見られませんが、現代の技術で「ピラーがないように見える」工夫をした車も登場しています。代表例がスライドドアを持つ一部の軽自動車やミニバンです。
例えばダイハツ・タントが採用する「ミラクルオープンドア」という機構では、本来ボディ側に固定されているはずの助手席側Bピラーを前席ドア後端と後席スライドドア前端に内蔵し、ドアを開けたときにBピラーが無い大開口部になるよう設計されています。
これにより最大約1,490mmもの広い開口幅を実現し、ベビーカーや大きな荷物も積み降ろししやすい利便性を確保しています。ホンダのN-VANという軽バンでも同様に助手席側をピラーレス構造とし、商用車として側面から荷物を積み込みやすいよう工夫されています。
これらの車ではドアを閉めた状態でしっかりピラー相当の構造が組み合わさり、通常のBピラー付き車と同等の強度・安全性を確保しています。
つまり、開けたときだけ柱が消えたように見える仕組みで、安全面との両立を図っているのです。
近年では構造上の理由から乗用車で完全なピラーレス車はほとんど見られませんが、現代の技術で「ピラーがないように見える」工夫をした車も登場しています。代表例がスライドドアを持つ一部の軽自動車やミニバンです。
例えばダイハツ・タントが採用する「ミラクルオープンドア」という機構では、本来ボディ側に固定されているはずの助手席側Bピラーを前席ドア後端と後席スライドドア前端に内蔵し、ドアを開けたときにBピラーが無い大開口部になるよう設計されています。
これにより最大約1,490mmもの広い開口幅を実現し、ベビーカーや大きな荷物も積み降ろししやすい利便性を確保しています。ホンダのN-VANという軽バンでも同様に助手席側をピラーレス構造とし、商用車として側面から荷物を積み込みやすいよう工夫されています。
これらの車ではドアを閉めた状態でしっかりピラー相当の構造が組み合わさり、通常のBピラー付き車と同等の強度・安全性を確保しています。
つまり、開けたときだけ柱が消えたように見える仕組みで、安全面との両立を図っているのです。
車種別ピラー本数の違い|セダン・SUV・バスまで比較
セダン・クーペのピラー本数
車体前部から後部までAピラー~Cピラーの3本が基本です(2ドアクーペの場合、構造上Bピラーが存在しないか非常に小さいことがあります)。
クーペやスポーツカーではルーフをなだらかに落とすためCピラーが長めです。
クーペやスポーツカーではルーフをなだらかに落とすためCピラーが長めです。
ハッチバック・SUVのピラー本数
荷室と客室が繋がった2ボックス型の車ではAピラー~Dピラーの4本があります。後部にテールゲート(バックドア)があるため、リアサイドの最後尾にDピラーが立ちます。
ステーションワゴン・ミニバンのピラー本数
Aピラー~Dピラーの4本構成が一般的です。特にミニバンは車高が高く車体が大きいため、すべてのピラーが比較的太めでしっかりした作りになっています。
ピックアップトラックのピラー構成
2列シートのダブルキャブなどではA~Cピラー、シングルキャブ(2人乗り)の場合はA~Bピラーと車体長に応じて本数が異なります。
リムジン・バスの複数ピラー
車体長が極端に長い車両ではEピラー、Fピラー…と柱が追加されていきます。大型バスやストレッチリムジンではHピラーやIピラー、さらにはJピラーまであるケースも存在します。窓の区切りが増えるごとにアルファベット順で名称が付与されるためです。
ピラー素材の種類と最新技術|ハイテン鋼・アルミ・カーボン
高張力鋼板(ハイテン鋼)ピラー
現在の多くの車では、ピラー部分に高張力鋼板と呼ばれる特別な高強度スチール素材が使われています。通常の鋼板よりも引張強度が高く、薄くしても十分な剛性を確保できるのが利点です。
例えばスズキの新型車では1470MPa級の超ハイテン材をAピラーに用い、5つに分割していた部品を一体成形することで軽量化と強度向上を両立した例もあります。高強度鋼によってピラーを過度に太くせず安全性を高める工夫がなされています。
例えばスズキの新型車では1470MPa級の超ハイテン材をAピラーに用い、5つに分割していた部品を一体成形することで軽量化と強度向上を両立した例もあります。高強度鋼によってピラーを過度に太くせず安全性を高める工夫がなされています。
アルミニウム合金ピラー
一部の高級車や電気自動車、スポーツカーでは、車体の軽量化のためにアルミニウム合金製のピラーやフレームを採用することがあります。
アルミは鉄より軽く腐食しにくい反面、剛性確保のため断面を大きく取る必要があるため、ピラー自体の太さが増す場合もあります。例えばアウディやジャガーの一部モデルではアルミ製ボディ構造を採用し、ピラーもアルミで作られています。
アルミは鉄より軽く腐食しにくい反面、剛性確保のため断面を大きく取る必要があるため、ピラー自体の太さが増す場合もあります。例えばアウディやジャガーの一部モデルではアルミ製ボディ構造を採用し、ピラーもアルミで作られています。
カーボンファイバー製ピラー
最先端の素材として、ごく一部の車(主にスーパーカーや特殊な車)ではカーボンファイバー製のモノコックを採用する例もあります。カーボン製の車体は非常に軽くて強度も高いのが特徴です。
市販車ではBMWの電気自動車「i3」が乗員セル(ピラーを含む車体骨格)に炭素繊維強化樹脂を使用したことで話題になりました。コストは高いですが、将来的にはピラー部分にもこうした軽量高強度素材が広まる可能性があります。
市販車ではBMWの電気自動車「i3」が乗員セル(ピラーを含む車体骨格)に炭素繊維強化樹脂を使用したことで話題になりました。コストは高いですが、将来的にはピラー部分にもこうした軽量高強度素材が広まる可能性があります。
ピラーに関する豆知識Q&A|死角対策から透明ピラーまで
Q1: 乗用車のピラーは何本ある?
A: セダンなら3本(A/B/Cピラー)、ワゴンやSUVなら4本(A~Dピラー)が基本です。車種によって異なりますが、多くの乗用車はこの範囲に収まります。
Q2: ピラー名称がアルファベットの理由は?
A: 特別な略語ではなく、車の前方から順にアルファベットを振っているだけです。Aから始まり、柱が後方に追加されるごとにB、C、D…と続きます。つまり記号的な呼称で、例えば5番目の柱があればEピラーとなります。
Q3: ピラーレス車は実在した?
A: 存在しました。1970~80年代には「ピラーレスハードトップ」と呼ばれるBピラーのない車が存在し、日本でも人気がありました。しかし衝突安全性の問題から現在では新車でこのスタイルは見られません。最近ではドア開口部拡大のためにピラーを隠した設計の車がありますが、ドアを閉めればピラー付きと同等の剛性を持つよう工夫されています。
Q4: ピラーが生む運転中の死角とは?
A: 視界の死角です。特にAピラー付近は斜め前を見る際に厚みで視界が遮られ、歩行者やオートバイが見えづらいことがあります。各メーカーは三角窓の追加や細いピラーの採用で死角を減らそうとしていますが、構造上ゼロにはできません。
そのため昨今ではAピラーを“透明”にしてしまう技術も研究されています! カメラ映像をAピラー内側のディスプレイに映し出し、外の景色が透けて見えるようにする試みで、例えばイギリスのジャガー・ランドローバー社などが技術コンセプトを発表し、開発を進めています。将来はピラーによる死角ゼロも夢ではないかもしれません。
そのため昨今ではAピラーを“透明”にしてしまう技術も研究されています! カメラ映像をAピラー内側のディスプレイに映し出し、外の景色が透けて見えるようにする試みで、例えばイギリスのジャガー・ランドローバー社などが技術コンセプトを発表し、開発を進めています。将来はピラーによる死角ゼロも夢ではないかもしれません。
Q5: 昔の車のアンテナはどこに刺さっていた?
A: 古い車のラジオアンテナは車体のピラーに取り付けられていたことがあり、「ピラーアンテナ」と呼ばれていました。Aピラー付近からニョキっと伸びるアンテナです。しかし現在はルーフ(屋根)上のアンテナやガラス埋め込み式アンテナが主流となり、ピラーアンテナを見る機会はほとんどなくなりました。細かいですが、車好きには懐かしい用語です。
まとめ|ピラー種類を知って安全で快適なカーライフを
普段あまり意識しない車のピラー(柱)ですが、実は安全性にもデザインにも欠かせない重要パーツです。各ピラーがあるおかげで車は衝突時にも形を保ち、私たち乗員の命が守られています。一方で視界の妨げやスタイリング上の課題も生むため、メーカーは素材開発や設計工夫によって常に改良を重ねてきました。
最近は透明ピラー技術など未来のクルマを見据えた研究も進んでおり、さらに安全で画期的なピラーが登場する日も近いでしょう。車を眺める際はぜひ各ピラーの位置や太さにも注目してみてください。きっと車選びやドライブが今までとは違った視点で楽しめるはずです。
最近は透明ピラー技術など未来のクルマを見据えた研究も進んでおり、さらに安全で画期的なピラーが登場する日も近いでしょう。車を眺める際はぜひ各ピラーの位置や太さにも注目してみてください。きっと車選びやドライブが今までとは違った視点で楽しめるはずです。