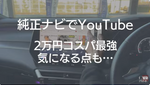トヨタ センチュリーが20年以上の時を経てフルモデルチェンジ!皇族も愛用する日本の最高級を解説
更新日:2024.09.09

※この記事には広告が含まれます
イギリスは「ロールスロイス」、ドイツでは「メルセデス・ベンツ」、アメリカなら「キャデラック」や「リンカーン」、そして中国では「紅旗」。
主要な自動車生産国はそれぞれが、その国を代表するセダンを持っている。果たして日本で該当するのはどのモデルか?
「レクサスLS」という人もいるかもしれない。しかし“格式と伝統”でいえば、間違いなく「トヨタ・センチュリー」だろう。
文・工藤 貴宏/写真・CarMe編集部
主要な自動車生産国はそれぞれが、その国を代表するセダンを持っている。果たして日本で該当するのはどのモデルか?
「レクサスLS」という人もいるかもしれない。しかし“格式と伝統”でいえば、間違いなく「トヨタ・センチュリー」だろう。
文・工藤 貴宏/写真・CarMe編集部
皇族も愛用するトヨタ センチュリー。その高貴さに身が引き締まる
理由は他でもない、日本の象徴である皇族が愛用しているからだ。レクサスLSも日本を代表するセダンの1台だが、格式でいえばセンチュリーにはかなわない。いっぽうのセンチュリーは、“御料車”と呼ばれる皇族専用モデルとしてスペシャルメイドの「センチュリーロイヤル」が存在するほどである。
また、10月22日には天皇陛下の即位を披露するパレード「祝賀御列(おんれつ)の儀」がおこなわれるが、そこで使われる、新たに作られたオープンカーのベースもセンチュリー。日本にはセンチュリーあり、なのだ。
また、10月22日には天皇陛下の即位を披露するパレード「祝賀御列(おんれつ)の儀」がおこなわれるが、そこで使われる、新たに作られたオープンカーのベースもセンチュリー。日本にはセンチュリーあり、なのだ。
センチュリーのどこが他の国産セダンと違うのか? 答えは簡単だ「運転する人を主」とするか「後席に座る人を主」とするかの違いである。たとえばレクサスLSは後席に人を座らせることも重視しているけれど、レクサスは「あくまでドライバーズカー」と説明する。しかしセンチュリーの場合、ドライバーズシートに座る人は単なる運転手に過ぎない。
メインとなるのはあくまで後席(それも助手席の後ろ)であり、その場所を中心にすべてが設計されているのだ。「誰のために存在するクルマなのか」というのは、クルマ作りにおける前提といっていい。だから、後席を中心とする設計なのか否か、という違いはとても大きいのだ。
ちなみに専属の運転手が運転しオーナーが後席に座るタイプのクルマは「ショーファードリブン」とか「ショーファーカー」などと呼ばれる。
メインとなるのはあくまで後席(それも助手席の後ろ)であり、その場所を中心にすべてが設計されているのだ。「誰のために存在するクルマなのか」というのは、クルマ作りにおける前提といっていい。だから、後席を中心とする設計なのか否か、という違いはとても大きいのだ。
ちなみに専属の運転手が運転しオーナーが後席に座るタイプのクルマは「ショーファードリブン」とか「ショーファーカー」などと呼ばれる。
センチュリーには1台への塗装作業約40時間。クラフトマンシップのなせる技が随所に現れる
21年ぶりにフルモデルチェンジして3代目となったセンチュリーを目の前にすると、そのエクステリアデザインは、初代から2代目への変更よりも大きいと感じられる。
初代から2代目への変化は「伝統」を重視して大きな変化を避けていたように思えるが、3代目は「格式」を重視しつつシルエットや面の張り方からバンパーやヘッドライトの処理などすべてにおいて洗練された。
初代から2代目への変化は「伝統」を重視して大きな変化を避けていたように思えるが、3代目は「格式」を重視しつつシルエットや面の張り方からバンパーやヘッドライトの処理などすべてにおいて洗練された。
しかし、大胆な変化をしつつもセンチュリーだとひとめでわかるデザインとしているのはさすがとしか言いようがない。クラシックかつモダンであり、そのバランス感覚がなんとも素晴らしい。威風堂々とした雰囲気は格段に上がり、あのロールスロイスと並べても引けを取らない重厚さを感じさせるオーラが漂う。
そんなセンチュリーは、製造過程も特別だ。新型も、トヨタ自動車東日本(かつての関東自動車工業)の東富士工場において生産される。一般的な量産車組み立てとは異なり、ベルトコンベア式ラインのない工場で、クラフトマン(職人)と呼ばれる熟練の作業者が匠の技を織り込みながら手作業で組み立てるのである。
ボディ組み立ては、プレス機で加工されたパネルをただ組み付けるのではなく、表面の歪みやわずかな凹凸を微調整しながら、時間をかけて繊細に仕上げていく。一般的な市販車では考えられないことである。
ボディ組み立ては、プレス機で加工されたパネルをただ組み付けるのではなく、表面の歪みやわずかな凹凸を微調整しながら、時間をかけて繊細に仕上げていく。一般的な市販車では考えられないことである。
写真:人工太陽灯による検査
センチュリーのボディカラーは4色設定されているが、代表する色は「神威(かむい)エターナルブラック」という黒である。この塗装方法もまた特別。一般的な車の塗装は4層仕上げだが、神威エターナルブラックはなんと7層。黒染料入りのカラークリアなどを吹き付けて深みを作り出すためである。
さらに塗装と塗装の間に合計3回、「水研ぎ」と呼ばれる下地塗装面の細かな凹凸を研いで表面を整えていく工程まであるのだから、とにかく手間をかけているのだ。さすがとしか言いようがない。
最終仕上げとして塗装面を磨いて鏡面のようにしていくのだが、特にこだわるのがCピラー。これはオーナーが乗り込む際に、ここへ映る姿をさりげなくチェックして身だしなみを確認できるようになのだという。
1台仕上げるのに、塗装に関する作業時間だけで約40時間。なにもかもが、一般の市販車とは異なる世界なのだ。
さらに塗装と塗装の間に合計3回、「水研ぎ」と呼ばれる下地塗装面の細かな凹凸を研いで表面を整えていく工程まであるのだから、とにかく手間をかけているのだ。さすがとしか言いようがない。
最終仕上げとして塗装面を磨いて鏡面のようにしていくのだが、特にこだわるのがCピラー。これはオーナーが乗り込む際に、ここへ映る姿をさりげなくチェックして身だしなみを確認できるようになのだという。
1台仕上げるのに、塗装に関する作業時間だけで約40時間。なにもかもが、一般の市販車とは異なる世界なのだ。
すべての組み立てが終わった後に完成検査がおこなわれるのは他のクルマと同様だが、センチュリーが違うのは、製造した1台1台、すべての車両が走行テストをしてから工場を後にすること。それだけでも普通のクルマでは考えられないことだが、約50kmもの走行テストをするというのだから凄い。
実走テストは、まずはごく低速から走り始め、時には日本の制限速度を大きく超える領域まで速度を上げる。そこで音、振動、乗り心地、フィーリングなどをチェックしたうえで工場から出荷されるのだ。
トヨタにとってセンチュリーは単に「高い量産車」ではなく、工業製品として最高品質を極める技術を磨くために欠かせないモデルなのかもしれない。
実走テストは、まずはごく低速から走り始め、時には日本の制限速度を大きく超える領域まで速度を上げる。そこで音、振動、乗り心地、フィーリングなどをチェックしたうえで工場から出荷されるのだ。
トヨタにとってセンチュリーは単に「高い量産車」ではなく、工業製品として最高品質を極める技術を磨くために欠かせないモデルなのかもしれない。
ついにハイブリッド化がなされたセンチュリー。さらに静粛性に磨きがかかる
新型センチュリーのスペックは、ボディサイズが全長5335mm×全幅1930mm。ホイールベースは3090mmだ。車両重量は2370kgとかなりの重量級である。
そして新型の特徴と言えば、ついにハイブリッド化されたことだろう。先代は国産車唯一のV型12気筒エンジンを積んでいたが、新型は5.0LのV型8気筒エンジンを組みあわせたハイブリッドシステムに刷新されている。ついにセンチュリーにもハイブリッドの時代が訪れたのだ。
現時点では国産車唯一となるV8エンジンのハイブリッドシステムだが、実は先代レクサスLSに使われていたものをリファインして組み込む。さらにいえば、プラットフォームも先代LS用をベースに設計されている。
「特別なセンチュリーなのだから新設計するべきではないか」と言いたい気持ちはわからなくない。しかしこれは、完成度の高いベースをさらに熟成させることで、より高い仕上がりを実現するという意味もある。何より大切なのは、単なる新旧ではなく、仕上がりなのだ。
そして新型の特徴と言えば、ついにハイブリッド化されたことだろう。先代は国産車唯一のV型12気筒エンジンを積んでいたが、新型は5.0LのV型8気筒エンジンを組みあわせたハイブリッドシステムに刷新されている。ついにセンチュリーにもハイブリッドの時代が訪れたのだ。
現時点では国産車唯一となるV8エンジンのハイブリッドシステムだが、実は先代レクサスLSに使われていたものをリファインして組み込む。さらにいえば、プラットフォームも先代LS用をベースに設計されている。
「特別なセンチュリーなのだから新設計するべきではないか」と言いたい気持ちはわからなくない。しかしこれは、完成度の高いベースをさらに熟成させることで、より高い仕上がりを実現するという意味もある。何より大切なのは、単なる新旧ではなく、仕上がりなのだ。
センチュリーの後席はどことなく感じる昭和の応接間。だがそれがいい
さて、後席に乗り込んでみよう。センチュリーには本革シート仕様も用意されているが、今回の試乗車両は「瑞響(すいきょう)」と呼ぶウールファブリックシート。
そこへディーラーオプションで用意されるレースのハーフカバーがかかっている。そのハーフカバーが前後席シートの1台分で税抜き15万5500円もするのはさすがとしかいいようがないが、雰囲気を盛り上げる。どんな雰囲気かといえば、昭和の応接間だ。センチュリーの後席は、言うなれば応接間にある立派なソファーなのである。
そんな応接間のような仕立ては、ロールスロイスともSクラスとも、そしてLSとも違う独自の世界。これこそ日本が誇るセンチュリーのオリジナリティあふれる世界観なのである。日本以外では決して通じないだろうけれど、センチュリーは日本専用車だからそれでいいのだ。いやむしろ、それがいいのだ。
リヤシートは3人掛けも可能。しかしセンターアームレストを倒せばそれが大型のセンターコンソールとなり、左右が独立した状態となる。
左側には電動で大きくリクライニングする機能をはじめ、エアで膨らむ袋を10個組み込んだ本格的なマッサージ機能(パナソニックのマッサージ機の技術が生かされている)、そして助手席の背中が開くタイプの電動式オットマンなど、を採用。
快適装備は至れり尽くせりだ。
運転席と助手席の間には11.6インチのモニターが組み込まれ、移動中はゆっくりと休息するのもいいし、ニュースを見みて社会の動きを感じたり、映画(Blu-rayプレーヤー付き)でヒマつぶしをするのもいいだろう。
一般的なクルマの後席が飛行機のエコノミークラスだとしたら、ミニバンはビジネスクラス、センチュリーはファーストクラス。
ここに座れば、極上の快適とリラックスを約束できる。
ラゲージスペースは、ゴルフバッグ4個収納できる484Lの容量を確保している
センチュリーは像のようにゆったりとどっしりと走る・曲がる・止まる
動き始めて感じるのは、静かすぎるほど静かな静粛性だ。外の世界と完全に隔離されたかのような感覚で、皮肉なことに普段乗っているクルマはいかにノイズが入ってくるのかを理解することになる。乗り心地も別次元。
車体とタイヤが路面からの入力を驚くほど緩和するから、不快な衝撃がないし、かといってサスペンションが柔らかすぎて船のようにグラグラするといった嫌な挙動もなく驚くほどのフラットライド感。
そこにはエアサスペンションも効いているのだろうが、今どきの大径タイヤとは思えないほどサイド面に厚みがあり、たっぷりと空気が入ってたわむタイヤも効いているに違いない。
車体とタイヤが路面からの入力を驚くほど緩和するから、不快な衝撃がないし、かといってサスペンションが柔らかすぎて船のようにグラグラするといった嫌な挙動もなく驚くほどのフラットライド感。
そこにはエアサスペンションも効いているのだろうが、今どきの大径タイヤとは思えないほどサイド面に厚みがあり、たっぷりと空気が入ってたわむタイヤも効いているに違いない。
まるでハンモックか魔法のじゅうたんにでも乗っているような錯覚になってくる。レクサスLSとの最大の違いは、この乗り心地。これが味わえるのはセンチュリーだけなのだ。言い換えれば、センチュリーを選ぶ理由、センチュリーでなければいけない理由がここにある。
今度は運転席に座って走らせてみる。何を隠そう、運転感覚も独特だ。
381馬力のエンジンと224馬力のモーターを組み合わせたハイブリッドだから、車両重量が2トンを超えると言っても動力性能はかなり高い。
しかし、アクセルを踏み込んでもググッとくるような鋭さはなく、あくまでおっとり動く。それでいて、しっかりと車速は上がる不思議な加速感。穏やかなのに速いのだ。
旋回も同じ。俊敏さはまるでなく、像のように安定して穏やかに曲がる。とはいえ車体に無駄な動きはなく、フラフラするようなそぶりは微塵も見せない。そんな穏やかな走行特性の理由は言うまでもないだろう。後席の人に不快さを与えないためだ。どっしり構えた安定感こそがセンチュリーの乗り味は、運転感覚から作り上げられているのである。
昨今、総理大臣が公用車をレクサスLSとしている(次はぜひセンチュリーに戻してほしいと心から思う)のをはじめ、室内の広さを求めてアルファードを愛用するVIPが増えるなど政財界の重鎮からも「センチュリー離れ」が進んでいる。
しかし、こうしてセンチュリーに触れてみると、その特別な位置づけをせざるを得ない。イギリスにロールスロイス「ファントム」があるように、日本にはセンチュリーがあるのだ。
しかし、こうしてセンチュリーに触れてみると、その特別な位置づけをせざるを得ない。イギリスにロールスロイス「ファントム」があるように、日本にはセンチュリーがあるのだ。
ところで、センチュリーのリヤドア&リヤウインドウにはプライバシーを守るためにカーテン(税抜き15万円のメーカーオプション)が用意されている。そしてリヤドアガラス部分は中央から左右(車体でいえば前後)方向へ開く仕掛けになっているのだが、なぜ高級車で一般的なブラインドではないのか?
その理由は、必要に応じて開くことで、皇族をはじめする後席に乗る人が、お見送りの人や沿道の人に対して顔を見せられるようになのだという。日本のセダンの頂点になるモデルは、ブラインド代わりのカーテンの構造ひとつとっても作りが特別なのだ。
その理由は、必要に応じて開くことで、皇族をはじめする後席に乗る人が、お見送りの人や沿道の人に対して顔を見せられるようになのだという。日本のセダンの頂点になるモデルは、ブラインド代わりのカーテンの構造ひとつとっても作りが特別なのだ。