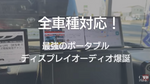マルチリンク式サスペンションのデメリットとは?
更新日:2025.06.30

※この記事には広告が含まれます
マルチリンク式サスペンションは、自動車のサスペンション形式の一つです。高級車やスポーツカーで採用されることが多く、乗り心地や走行安定性を向上させる目的で導入されています。
ダブルウィッシュボーン式に似た構造を持ちながら、複数のアーム(リンク)を用いてタイヤと車体を連結することで、より精密なホイールアライメント制御を可能にするのが特徴です。 その分タイヤの動きを細かく制御できるため、コーナリング時の安定性向上や路面追従性の向上、さらにはロードノイズの低減など多くのメリットがあります。
では、このマルチリンク式サスペンションにはどのようなデメリット(欠点)があるのでしょうか。
本記事ではマルチリンク式サスペンションの主なデメリットについて解説し、他の方式との比較や車選びのポイントも紹介します。
ダブルウィッシュボーン式に似た構造を持ちながら、複数のアーム(リンク)を用いてタイヤと車体を連結することで、より精密なホイールアライメント制御を可能にするのが特徴です。 その分タイヤの動きを細かく制御できるため、コーナリング時の安定性向上や路面追従性の向上、さらにはロードノイズの低減など多くのメリットがあります。
では、このマルチリンク式サスペンションにはどのようなデメリット(欠点)があるのでしょうか。
本記事ではマルチリンク式サスペンションの主なデメリットについて解説し、他の方式との比較や車選びのポイントも紹介します。
マルチリンク式サスペンションのデメリット4選【費用・重量・複雑性】
製造コストが高い|高価格化の原因
部品の数が多いため製造コストが嵩み、そのぶん車両価格の上昇につながります。精密な部品と組み立て精度が求められることもコスト増の要因となります。
複雑構造が生む設計・調整の難易度
リンクや可動部が増える分、サスペンション全体の構造が非常に複雑になります。各リンクの長さや配置、ブッシュの特性など、設計・調整すべき要素が多岐にわたるため、最適なセッティングを見出すには高度な設計思想と多くのテストが必要です。セッティングを誤ると思わぬ挙動変化や性能低下が生じる可能性もあります。メーカーにとっては開発に時間と高度な技術・ノウハウを要し、生産ラインでの組み付けにも高い精度が求められます。
そのため、依然として比較的高級な車種や走行性能を重視するモデルで採用されることが多い傾向にありますが、近年では設計技術の進化や部品のモジュール化などにより、より幅広い車種(例えば、一部のCセグメントFF車の上級グレードやAWDモデルのリアサスペンションなど)でも見られるようになってきています。
ただし、構造のシンプルさやコスト面で有利な他のサスペンション形式(マクファーソンストラット式やトーションビーム式など)に比べると、採用は依然として限定的と言える側面もあります。
そのため、依然として比較的高級な車種や走行性能を重視するモデルで採用されることが多い傾向にありますが、近年では設計技術の進化や部品のモジュール化などにより、より幅広い車種(例えば、一部のCセグメントFF車の上級グレードやAWDモデルのリアサスペンションなど)でも見られるようになってきています。
ただし、構造のシンプルさやコスト面で有利な他のサスペンション形式(マクファーソンストラット式やトーションビーム式など)に比べると、採用は依然として限定的と言える側面もあります。
メンテナンス費用が嵩む|維持管理のハードル
複雑な構造ゆえにメンテナンス性が低い点もデメリットです。リンクやブッシュ、ボールジョイントなど交換・点検箇所が多く、整備に手間がかかり維持費が高くつく場合があります。「部品点数が多く、メンテナンスが難しい点」と指摘する声もあります。
経年劣化によるブッシュ類の交換も複数箇所で必要になるなど、シンプルなサスペンションに比べ維持管理に注意が必要です。アライメント調整も、調整箇所が多い分、より専門的な知識と設備が求められることがあります。
経年劣化によるブッシュ類の交換も複数箇所で必要になるなど、シンプルなサスペンションに比べ維持管理に注意が必要です。アライメント調整も、調整箇所が多い分、より専門的な知識と設備が求められることがあります。
重量増のデメリット|燃費と運動性能への影響
多数のアームや部品を備えることでサスペンション自体の重量(特にばね下重量)が増加し、車両全体としても重量増につながりやすいです。重量が増えれば燃費への悪影響や、ハンドリングの軽快感が損なわれるなど運動性能への影響も無視できないため、徹底した軽量化が求められる車種には不利となる場合があります。
ただし、近年ではアルミ合金などの軽量素材の採用により、重量増を抑制する設計も進んでいます。
ただし、近年ではアルミ合金などの軽量素材の採用により、重量増を抑制する設計も進んでいます。
サスペンション方式比較|マルチリンクvsストラット・トーションビーム
ストラット式サスペンションの特徴と評価
最もシンプルで一般的な独立懸架サスペンション形式の一つです。ダンパー(ショックアブソーバー)とスプリングを一体化したストラット自体が上側の支持部となり、これとロアアーム(通常は1本ですが、形状は様々です)、そして操舵輪の場合は操舵用のタイロッドによってホイールを支持する構造で、部品点数が比較的少なく省スペースかつ低コストなのが魅力です。
軽量なため多くの乗用車のフロントサスペンションに採用されていますが、構造上、タイヤの動き(特にキャンバー角など)の制御自由度はダブルウィッシュボーン式やマルチリンク式に比べて限定的であり、剛性確保や高度な走行性能を追求する点では劣る面もあります。
軽量なため多くの乗用車のフロントサスペンションに採用されていますが、構造上、タイヤの動き(特にキャンバー角など)の制御自由度はダブルウィッシュボーン式やマルチリンク式に比べて限定的であり、剛性確保や高度な走行性能を追求する点では劣る面もあります。
トーションビーム式サスペンションの特徴と評価
左右のトレーリングアーム(またはそれに準じるアーム)を、ねじれ(トーション)を許容するビーム(梁)で連結した車軸懸架の一種(半独立懸架式とも呼ばれます)です。部品点数が少なく低コストかつ省スペースなため、主にコンパクトカーや軽自動車などの後輪に多く採用されています。
構造がシンプルで軽量なため整備も比較的容易ですが、左右の車輪がある程度連結されている構造上、純粋な独立懸架サスペンションに比べて、片輪ずつ異なる動きをする際の路面追従性や乗り心地、そしてコーナリング時のタイヤの接地安定性などで不利になる傾向があります。
構造がシンプルで軽量なため整備も比較的容易ですが、左右の車輪がある程度連結されている構造上、純粋な独立懸架サスペンションに比べて、片輪ずつ異なる動きをする際の路面追従性や乗り心地、そしてコーナリング時のタイヤの接地安定性などで不利になる傾向があります。
後悔しない車選び|サスペンション形式チェックリスト
用途別に最適なサスペンションを選ぶコツ
高級車やスポーツモデルには、より理想的なタイヤの動きを実現しやすいマルチリンク式サスペンションなどが採用され、高いレベルでの静粛性、乗り心地、そして操縦安定性が追求されています。
一方、コンパクトカーなどコストやスペース効率が重視される車種では、シンプルなストラット式やトーションビーム式が、その目的に対して最適な選択となる場合もあります。
ご自身が車に求める性能(例えば、快適性やスポーティーな操縦性なのか、経済性や室内空間の広さなのか)に応じて、サスペンション形式にも目を向けてみましょう。
一方、コンパクトカーなどコストやスペース効率が重視される車種では、シンプルなストラット式やトーションビーム式が、その目的に対して最適な選択となる場合もあります。
ご自身が車に求める性能(例えば、快適性やスポーティーな操縦性なのか、経済性や室内空間の広さなのか)に応じて、サスペンション形式にも目を向けてみましょう。
カタログと試乗で分かる乗り味の違い
気になる車種があれば、公式カタログの主要諸元表にある「サスペンション形式」の欄をチェックしてみてください。「フロント:マクファーソンストラット式 / リア:トーションビーム式」などと明記されています。
また、カタログ情報だけでなく、実際に試乗して乗り心地やハンドリング、路面からの振動の伝わり方などを確かめ、ご自身にとって快適か、許容できる範囲かを感じてみることが非常に大切です。必ずしも高価で複雑なサスペンションを搭載した車だけが良い車とは限りません。
その車のキャラクターや価格、そしてご自身の使い方とのバランスが重要です。
また、カタログ情報だけでなく、実際に試乗して乗り心地やハンドリング、路面からの振動の伝わり方などを確かめ、ご自身にとって快適か、許容できる範囲かを感じてみることが非常に大切です。必ずしも高価で複雑なサスペンションを搭載した車だけが良い車とは限りません。
その車のキャラクターや価格、そしてご自身の使い方とのバランスが重要です。
長期維持コストを左右するメンテナンス性
購入後のメンテナンス費用も、車を長く維持する上では重要なポイントです。マルチリンク式サスペンションは構造が複雑で部品点数(特にブッシュやアーム類)が多いため、将来的にこれらの部品が劣化した際の交換費用やアライメント調整費用などが、シンプルなストラット式やトーションビーム式に比べて高くなる可能性があります。
長く乗るつもりであれば、この点にも留意しておくと、後々の維持管理計画が立てやすくなります。
長く乗るつもりであれば、この点にも留意しておくと、後々の維持管理計画が立てやすくなります。