なぜポルシェとフェラーリのエンブレムは似ているの?隠された意外なストーリーとは。
更新日:2025.08.12
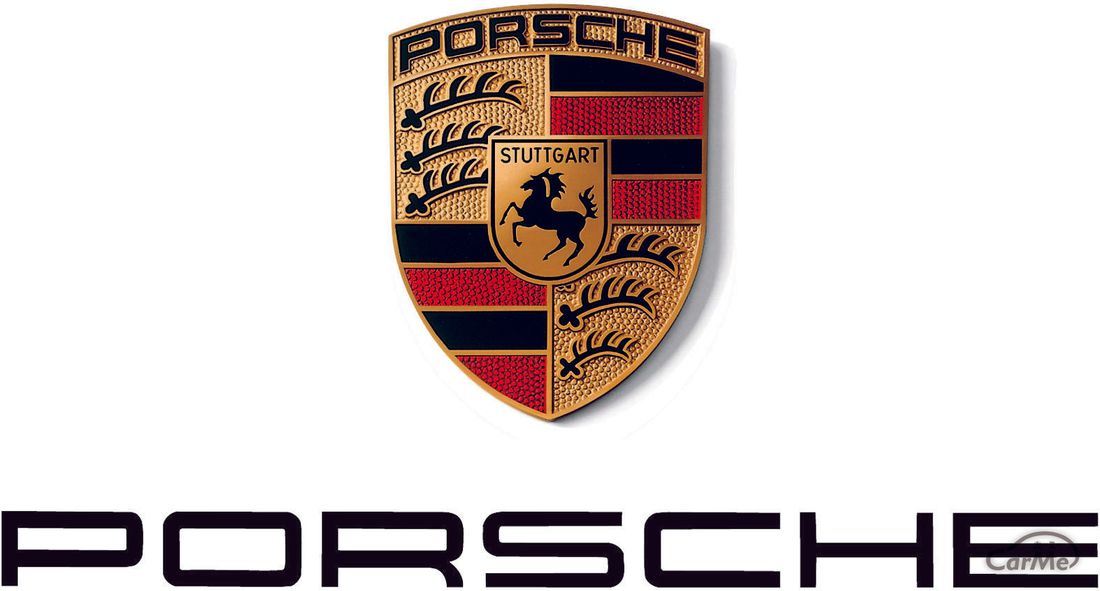
※この記事には広告が含まれます
ポルシェのエンブレムの由来とフェラーリの跳ね馬の意味には、実は意外な共通点があります。ドイツの名門ポルシェとイタリアの名門フェラーリ──国も歴史も異なる両者ですが、エンブレムに描かれた馬のマークには深い繋がりが隠されているのです。今回は、その知られざるストーリーに迫ってみましょう。
確かに似ている…ポルシェとフェラーリのエンブレム
フェラーリのエンブレムに描かれている「跳ね馬」は、その勇ましい姿が印象的で、世界中で愛されています。
実はこの馬のマーク、ポルシェのエンブレムにも登場することをご存知でしょうか。
二つのスポーツカーメーカーのロゴマークを見比べると、「どちらも馬が描かれていてそっくりじゃないか!」と思ったことがある方もいるかもしれません。
ドイツのポルシェとイタリアのフェラーリ、一見関係のない両社が同じ馬をシンボルにしているのはなぜなのでしょうか?
その疑問を解くために、まずはポルシェのエンブレム誕生の背景から見ていきましょう。
実はこの馬のマーク、ポルシェのエンブレムにも登場することをご存知でしょうか。
二つのスポーツカーメーカーのロゴマークを見比べると、「どちらも馬が描かれていてそっくりじゃないか!」と思ったことがある方もいるかもしれません。
ドイツのポルシェとイタリアのフェラーリ、一見関係のない両社が同じ馬をシンボルにしているのはなぜなのでしょうか?
その疑問を解くために、まずはポルシェのエンブレム誕生の背景から見ていきましょう。
ポルシェのエンブレムの由来は本拠地シュトゥットガルト市の紋章にあり
ポルシェのエンブレムは盾型の紋章になっており、中央に黒い跳ね馬が描かれているのが特徴です。
この馬のデザインこそが、ポルシェの本拠地であるドイツ・シュトゥットガルト市の紋章から取られたものです。
ポルシェといえば創業者のフェルディナンド・ポルシェ博士が有名ですが、会社の拠点はドイツ南西部の都市シュトゥットガルトでした。
そのシュトゥットガルト市の公式紋章には、金色の盾の中に黒い馬が前脚をあげた姿で描かれています。この馬こそ、ポルシェのエンブレムのベースとなったものなのです。
この馬のデザインこそが、ポルシェの本拠地であるドイツ・シュトゥットガルト市の紋章から取られたものです。
ポルシェといえば創業者のフェルディナンド・ポルシェ博士が有名ですが、会社の拠点はドイツ南西部の都市シュトゥットガルトでした。
そのシュトゥットガルト市の公式紋章には、金色の盾の中に黒い馬が前脚をあげた姿で描かれています。この馬こそ、ポルシェのエンブレムのベースとなったものなのです。
シュトゥットガルトという地名は、実はドイツ語で「馬の園(Stuotgarten)」を語源とし、もともと王侯の馬の牧場があった土地だとされています。
シュトゥットガルト市の紋章が黒い馬をあしらっているのも、そうした歴史に由来します。
この黒い馬の意匠に、周囲を囲む赤と黒の縞模様や鹿の角のモチーフを組み合わせて、現在のポルシェのエンブレム「クレスト」が完成しました。
実際にポルシェのクレストには、中央の馬の周りをバーデン=ヴュルテンベルク州の紋章由来の角飾りや赤黒の模様が取り囲んでおり、下部には「PORSCHE」の文字が刻まれています。
ポルシェ社はこのデザインを1952年に正式なエンブレムとして採用し、それ以来すべてのポルシェ車のボンネットを飾る象徴となりました。
シュトゥットガルト市の紋章が黒い馬をあしらっているのも、そうした歴史に由来します。
この黒い馬の意匠に、周囲を囲む赤と黒の縞模様や鹿の角のモチーフを組み合わせて、現在のポルシェのエンブレム「クレスト」が完成しました。
実際にポルシェのクレストには、中央の馬の周りをバーデン=ヴュルテンベルク州の紋章由来の角飾りや赤黒の模様が取り囲んでおり、下部には「PORSCHE」の文字が刻まれています。
ポルシェ社はこのデザインを1952年に正式なエンブレムとして採用し、それ以来すべてのポルシェ車のボンネットを飾る象徴となりました。
では、なぜイタリアのフェラーリも同じ馬を使っているのか?
ポルシェのエンブレムにシュトゥットガルト市の馬が使われていることが分かりました。
それでは、遠く離れたイタリアの名門フェラーリも同じ馬をエンブレムに使用しているのは一体なぜなのでしょうか。
実を言えば、フェラーリの跳ね馬マークも起源をたどればシュトゥットガルト市の紋章の馬に行き着くとされます。
つまりフェラーリは結果的に、ドイツ・シュトゥットガルトのシンボルを自社のエンブレムに取り入れていることになります。
しかし、なぜイタリアを代表するスポーツカーメーカーがドイツの都市の紋章と関係を持つことになったのでしょうか? その謎を解くカギは、今から約100年前の第一次世界大戦にまで遡ります。
それでは、遠く離れたイタリアの名門フェラーリも同じ馬をエンブレムに使用しているのは一体なぜなのでしょうか。
実を言えば、フェラーリの跳ね馬マークも起源をたどればシュトゥットガルト市の紋章の馬に行き着くとされます。
つまりフェラーリは結果的に、ドイツ・シュトゥットガルトのシンボルを自社のエンブレムに取り入れていることになります。
しかし、なぜイタリアを代表するスポーツカーメーカーがドイツの都市の紋章と関係を持つことになったのでしょうか? その謎を解くカギは、今から約100年前の第一次世界大戦にまで遡ります。
フェラーリの「跳ね馬」は伝説のパイロット、フランチェスコ・バラッカの紋章だった!?
では続いて、フェラーリのエンブレムの由来をひも解いてみましょう。
フェラーリのシンボルマークである「跳ね馬」(カヴァリーノ・ランパンテ)は、イタリアの第一次大戦の英雄パイロット、フランチェスコ・バラッカ伯爵が自らの戦闘機に描いていた個人マークに由来すると言われています。
バラッカ伯爵は第一次世界大戦において「撃墜王」と称されるほど活躍した伝説的エースで、幾多の敵機を撃墜した国民的英雄でした。
彼の愛機には黒い跳ね馬の紋章が描かれており、それが後にフェラーリのエンブレムとなる馬の原型になったのです。
1918年にバラッカは戦場で命を落としてしまいますが、戦後になって彼の両親がエンツォ・フェラーリ氏と出会い、「息子が使っていたあの馬の紋章をぜひあなたの車にも付けてはどうか」と提案したと言われています。
バラッカ家の母パオリーナ夫人の願いもあり、エンツォ・フェラーリはこの跳ね馬のエンブレムを幸運のお守りとして自分のマシンに付けることになりました。
こうしてフェラーリのエンブレムの馬は、元々バラッカが遺した個人紋章を受け継いだものとなったのです。
実際、エンツォ・フェラーリがこの跳ね馬マークを最初にレース車両に掲げたのは1920年代と言われ、以降フェラーリの象徴として定着していきました。
フェラーリのシンボルマークである「跳ね馬」(カヴァリーノ・ランパンテ)は、イタリアの第一次大戦の英雄パイロット、フランチェスコ・バラッカ伯爵が自らの戦闘機に描いていた個人マークに由来すると言われています。
バラッカ伯爵は第一次世界大戦において「撃墜王」と称されるほど活躍した伝説的エースで、幾多の敵機を撃墜した国民的英雄でした。
彼の愛機には黒い跳ね馬の紋章が描かれており、それが後にフェラーリのエンブレムとなる馬の原型になったのです。
1918年にバラッカは戦場で命を落としてしまいますが、戦後になって彼の両親がエンツォ・フェラーリ氏と出会い、「息子が使っていたあの馬の紋章をぜひあなたの車にも付けてはどうか」と提案したと言われています。
バラッカ家の母パオリーナ夫人の願いもあり、エンツォ・フェラーリはこの跳ね馬のエンブレムを幸運のお守りとして自分のマシンに付けることになりました。
こうしてフェラーリのエンブレムの馬は、元々バラッカが遺した個人紋章を受け継いだものとなったのです。
実際、エンツォ・フェラーリがこの跳ね馬マークを最初にレース車両に掲げたのは1920年代と言われ、以降フェラーリの象徴として定着していきました。
バラッカが撃墜した敵機から持ち帰った「跳ね馬」の秘密
では、伝説のパイロットであるバラッカは、なぜ自分の戦闘機に馬のマークを描いていたのでしょうか。
その背景には当時の戦場での興味深いエピソードがあります。
第一次大戦当時、撃墜した敵の機体の紋章やマークを自分の機体に貼り付けるという習慣がパイロットたちの間にあったそうです。
バラッカも例にもれず、自らの戦果の証として撃ち落とした敵軍機のマークを戦闘機に描いていたといいます。そしてバラッカが撃墜したドイツ軍の戦闘機こそ、偶然にもドイツ・シュトゥットガルト市の所属部隊の機体だったのです。
そのドイツ軍機に描かれていたのが黒い跳ね馬の紋章、つまりシュトゥットガルト市の紋章でした。
バラッカはこの馬のマークを戦利品として自分の機体に持ち帰り、自らのシンボルとしたのだという説があります。これこそが、フェラーリとポルシェのエンブレムに共通の馬が描かれることになった意外な由来なのです。
ちなみに、現在フェラーリのエンブレムをよく見ると、跳ね馬の背景部分は鮮やかなカナリアイエロー(黄色)になっています。
この黄色はフェラーリ創業の地であるモデナ市のカラーを採用したものです。さらにエンブレム上部にはイタリア国旗の緑・白・赤のストライプも配されており、フェラーリが誇るイタリアンブランドとしての誇りが表現されています。
エンブレム全体として見ると、跳ね馬というモチーフにイタリアの魂と歴史が込められていることがわかります。
その背景には当時の戦場での興味深いエピソードがあります。
第一次大戦当時、撃墜した敵の機体の紋章やマークを自分の機体に貼り付けるという習慣がパイロットたちの間にあったそうです。
バラッカも例にもれず、自らの戦果の証として撃ち落とした敵軍機のマークを戦闘機に描いていたといいます。そしてバラッカが撃墜したドイツ軍の戦闘機こそ、偶然にもドイツ・シュトゥットガルト市の所属部隊の機体だったのです。
そのドイツ軍機に描かれていたのが黒い跳ね馬の紋章、つまりシュトゥットガルト市の紋章でした。
バラッカはこの馬のマークを戦利品として自分の機体に持ち帰り、自らのシンボルとしたのだという説があります。これこそが、フェラーリとポルシェのエンブレムに共通の馬が描かれることになった意外な由来なのです。
ちなみに、現在フェラーリのエンブレムをよく見ると、跳ね馬の背景部分は鮮やかなカナリアイエロー(黄色)になっています。
この黄色はフェラーリ創業の地であるモデナ市のカラーを採用したものです。さらにエンブレム上部にはイタリア国旗の緑・白・赤のストライプも配されており、フェラーリが誇るイタリアンブランドとしての誇りが表現されています。
エンブレム全体として見ると、跳ね馬というモチーフにイタリアの魂と歴史が込められていることがわかります。
まとめ:偶然の一致が生んだ深い歴史のロマン
ポルシェとフェラーリという二つのスーパーカーメーカーが同じ馬のシンボルをエンブレムに使用している裏には、このような驚くべき歴史の繋がりがありました。
ドイツとイタリア、第一次世界大戦という過酷な時代を経て受け継がれた馬のマークは、現在ではそれぞれポルシェとフェラーリのブランドを象徴する誇り高きエンブレムとなっています。
偶然の一致から生まれたこのストーリーには、車好きでなくともロマンを感じずにはいられません。
普段何気なく目にしている車のエンブレムも、由来や背景を紐解いてみると今回のように意外な発見があるものです。
ぜひ皆さんも愛車のエンブレムの意味を調べて、そこに隠された物語に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。
ドイツとイタリア、第一次世界大戦という過酷な時代を経て受け継がれた馬のマークは、現在ではそれぞれポルシェとフェラーリのブランドを象徴する誇り高きエンブレムとなっています。
偶然の一致から生まれたこのストーリーには、車好きでなくともロマンを感じずにはいられません。
普段何気なく目にしている車のエンブレムも、由来や背景を紐解いてみると今回のように意外な発見があるものです。
ぜひ皆さんも愛車のエンブレムの意味を調べて、そこに隠された物語に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。
実は... エンブレムとブランディング戦略の関係
クルマのエンブレムは、わずか数センチ四方でブランドの歴史・価値・性能を雄弁に語る「走る名刺」です。
とくにポルシェとフェラーリは、エンブレムを“レースで勝つ姿”とワンセットで世界に刷り込み、強大なブランド資産へと育ててきました。
とくにポルシェとフェラーリは、エンブレムを“レースで勝つ姿”とワンセットで世界に刷り込み、強大なブランド資産へと育ててきました。
1. ポルシェ:勝利とともに“クレスト”が拡大
- 1952年、クレスト誕生
- 1951年ル・マン初優勝が後押し
- 現代のリブランディング
2. フェラーリ:F1を“広告塔”にした跳ね馬
- 1952年 F1初タイトル
- マーケティング予算=ほぼF1参戦費
- “速さ+希少性”の二重構造
3. モータースポーツ露出からデジタル時代へ
60年代はサーキット観戦とモータースポーツ専門誌、80〜90年代は地上波中継と衛星放送。
そして今世紀に入り、SNSやストリーミングが「ロゴの再生産装置」となりました。
近年では Netflix『Drive to Survive』効果 でF1の視聴層が拡大し、跳ね馬やクレストをファッションに取り込むコラボが続出。モータースポーツとライフスタイルが地続きになっています。
そして今世紀に入り、SNSやストリーミングが「ロゴの再生産装置」となりました。
近年では Netflix『Drive to Survive』効果 でF1の視聴層が拡大し、跳ね馬やクレストをファッションに取り込むコラボが続出。モータースポーツとライフスタイルが地続きになっています。
4. CIガイドラインで守られる“聖域”
名刺のように使われるゆえに、エンブレムは改変厳禁の聖域です。
たとえばポルシェは「クレストとロゴタイプを一定比率で組み合わせる“マルク”以外は認めない」「登録商標マーク®を必ず付す」とCIガイドラインで徹底管理。
ブランドの一貫性と法的保護を両立させています。
たとえばポルシェは「クレストとロゴタイプを一定比率で組み合わせる“マルク”以外は認めない」「登録商標マーク®を必ず付す」とCIガイドラインで徹底管理。
ブランドの一貫性と法的保護を両立させています。
おまけ:EV時代のエンブレムはどう進化する?
電動化が進むいま、エンブレムは単なるブランドバッジから“発光するインターフェース”へと急速にアップデートされています。
従来の金属プレスに代わり、導光性ポリカーボネートや再生アルミをベースに LED/マイクロLEDユニット を組み込み、視認性・空力・エネルギー効率を同時に満たす設計へ――その最前線を覗いてみましょう。
従来の金属プレスに代わり、導光性ポリカーボネートや再生アルミをベースに LED/マイクロLEDユニット を組み込み、視認性・空力・エネルギー効率を同時に満たす設計へ――その最前線を覗いてみましょう。
1. 市販車で加速する「光るロゴ」採用例
- 日産アリア(2023〜)
2019年のコンセプト段階からイルミネーテッドロゴが採用されており、量産車ではディーラー/JDMオプションとして「フロントグリルLEDイルミネーション」が設定されるなど、アフター需要も活況を呈しています。
- BMW iX(2025年LCI)
オプション選択でM70 xDriveグレードは標準装備となり、深夜の充電スタンドでも一目で識別できるブランドサインへ昇華しています。
- GMC Hummer EV(2025年モデル)
大型ピックアップでも視認距離を確保するため、LED素子には高輝度・低消費電力タイプを採用しています。
- メルセデス・ベンツ EQシリーズ(イルミネーテッド・スター)
サブライセンス生産ながら厳格なCIガイドで光度・色温度を統一し、どの市場でも同じ“ベンツの輝き”を保証しています。
これらの事例が示す通り、イルミネーテッドバッジは「EVらしい未来感」+「ブランド即時認知」+「センサー統合」という三位一体の価値を提供し、市販車レベルで急速に普及しています。
2. テクノロジーの裏側――レーダー透過と熱マネジメント
サプライヤー各社は「光る+通信する+測る」三位一体 を掲げます。
たとえば Valeo の量産モジュールはライト部に透過率50%以上のPC樹脂を用い、背面にレーダー・カメラを一体パッケージ。
光源部には氷結防止ヒーターを組み込み、霜取り→自動運転センサー視界確保という“縁の下の機能”まで織り込まれています。
EVはグリル開口が小さく冷却風が限られるため、LEDの廃熱はヒートパイプ+導光板で外気に逃がす手法が主流です。
たとえば Valeo の量産モジュールはライト部に透過率50%以上のPC樹脂を用い、背面にレーダー・カメラを一体パッケージ。
光源部には氷結防止ヒーターを組み込み、霜取り→自動運転センサー視界確保という“縁の下の機能”まで織り込まれています。
EVはグリル開口が小さく冷却風が限られるため、LEDの廃熱はヒートパイプ+導光板で外気に逃がす手法が主流です。
3. 法規制が鍵:UNECE R48/R148改正と「75 mmルール」
欧州では2023年1月改正の UNECE R48/R148 で 『発光ロゴは車幅灯もしくはDRLの一部としてのみ許可』 と明記されました。
さらに両灯間距離600mm、ロゴと外板端400mm以内、ロゴ分割部の間隔75mm以下――という細かな寸法制限が課され、実装にはデザイナーと法規担当の“知恵比べ”が必要です。
北米は FMVSS108/SAE J3098 で比較的自由度が高い一方、中国では走行中点灯を許可せず“停車中のみOK”など、市場ごとの適合開発が不可欠となっています。
さらに両灯間距離600mm、ロゴと外板端400mm以内、ロゴ分割部の間隔75mm以下――という細かな寸法制限が課され、実装にはデザイナーと法規担当の“知恵比べ”が必要です。
北米は FMVSS108/SAE J3098 で比較的自由度が高い一方、中国では走行中点灯を許可せず“停車中のみOK”など、市場ごとの適合開発が不可欠となっています。
4. サステナブル素材と「軽量バッジ」
EVにおける航続距離はわずかな重量差でも大きく左右されるため、エンブレムの世界でも軽量化と環境負荷低減が急務となっています。
近年は従来の真鍮や鋳鉄を避け、リサイクルアルミやマグネシウム合金を薄肉ダイカストで成形したフレームが主流となりました。
さらに、基材にはトウモロコシ由来のPLA樹脂といったバイオベース素材が用いられ、水系PVD(物理蒸着)によるクロームレス仕上げで鏡面光沢を確保しながら有害物質を排除する動きが広がっています。
こうした組み合わせにより、最新バッジは従来品比で30〜40%の軽量化とCO₂排出量の大幅削減を同時に達成。1kgの車重低減で約2 kmの航続距離延伸が見込めるとされる電動車の世界では、“走り”と“地球環境”の双方を支える小さな部品として、サステナブルなバッジが大きな付加価値を生み出しています。
近年は従来の真鍮や鋳鉄を避け、リサイクルアルミやマグネシウム合金を薄肉ダイカストで成形したフレームが主流となりました。
さらに、基材にはトウモロコシ由来のPLA樹脂といったバイオベース素材が用いられ、水系PVD(物理蒸着)によるクロームレス仕上げで鏡面光沢を確保しながら有害物質を排除する動きが広がっています。
こうした組み合わせにより、最新バッジは従来品比で30〜40%の軽量化とCO₂排出量の大幅削減を同時に達成。1kgの車重低減で約2 kmの航続距離延伸が見込めるとされる電動車の世界では、“走り”と“地球環境”の双方を支える小さな部品として、サステナブルなバッジが大きな付加価値を生み出しています。
5. 次フェーズは「インタラクティブ&OTA」
ソフトウェア定義車(Software-Defined Vehicle)の潮流は、エンブレムを静的な飾りから動的なインターフェースへと変貌させつつあります。
たとえばドアロック解除時に発光アニメーションで乗員を迎える“ウェルカムライト”や、バッテリー残量を光のバーグラフで示す“ステータスインジケーター”など、車両情報をリアルタイムに可視化するエンブレムが登場。
将来的にはマイクロLEDの高密度アレイによりピクセル単位で絵柄を描写し、V2X通信と連動して歩行者や他車にメッセージを送ることも構想されています。
しかも発光パターンや表示内容は OTA(Over-the-Air)アップデートで季節イベントや新機能に合わせて書き換え可能となり、物理バッジがデジタルサインへ進化。
実際、ポルシェ・タイカン後期型ではソフト更新によってエンブレムの光り方を追加できるテストプログラムが進行しており、インタラクティブかつ継続的に進化する“光る跳ね馬”競争がいよいよ現実味を帯びてきました。
たとえばドアロック解除時に発光アニメーションで乗員を迎える“ウェルカムライト”や、バッテリー残量を光のバーグラフで示す“ステータスインジケーター”など、車両情報をリアルタイムに可視化するエンブレムが登場。
将来的にはマイクロLEDの高密度アレイによりピクセル単位で絵柄を描写し、V2X通信と連動して歩行者や他車にメッセージを送ることも構想されています。
しかも発光パターンや表示内容は OTA(Over-the-Air)アップデートで季節イベントや新機能に合わせて書き換え可能となり、物理バッジがデジタルサインへ進化。
実際、ポルシェ・タイカン後期型ではソフト更新によってエンブレムの光り方を追加できるテストプログラムが進行しており、インタラクティブかつ継続的に進化する“光る跳ね馬”競争がいよいよ現実味を帯びてきました。
ポイント:EVならではの静寂とクリーンイメージを、発光エンブレムが動的に補完。法規制・サステナビリティ・ソフトウェアの三要素をクリアしたブランドだけが、次世代の“光る跳ね馬”競争を制すると言えそうです。


































