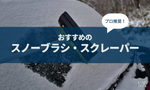隣の車にドアをぶつけてしまった時の正しい対処法と予防策
更新日:2025.07.31

※この記事には広告が含まれます
駐車場で車のドアを開けた際に、うっかり隣の車にドアをぶつけてしまったことはありませんか?
初心者ドライバーの方は特に焦ってしまうかもしれません。しかし、落ち着いて正しい手順で対応すれば大丈夫です。
ここでは事故直後にやるべき対応と、よくある不安点、法律上の注意点、さらに再発防止の簡単な予防策について、ゆっくり丁寧に解説します。スマホで読む方にも理解しやすいよう、ポイントを整理して短めにまとめました。
初心者ドライバーの方は特に焦ってしまうかもしれません。しかし、落ち着いて正しい手順で対応すれば大丈夫です。
ここでは事故直後にやるべき対応と、よくある不安点、法律上の注意点、さらに再発防止の簡単な予防策について、ゆっくり丁寧に解説します。スマホで読む方にも理解しやすいよう、ポイントを整理して短めにまとめました。
【緊急対応】ドアパンチ直後の正しい手順
1. まずは相手への謝罪と連絡先交換で誠実に対応
まずは被害に遭われた車の持ち主(運転手)を探し、誠心誠意、真摯に謝罪することが最も重要です。
その場で氏名・住所・電話番号・可能であれば加入している保険会社名など、お互いの連絡先を正確に確認・交換しましょう。商業施設などの駐車場であれば、相手の車のナンバープレートを施設の管理事務所やインフォメーションカウンターに伝えて、館内アナウンスなどで呼び出してもらえる場合もあります。
また、相手の車の傷やへこみがついた箇所、自分の車のドアが当たった箇所などを、さまざまな角度からスマートフォンなどで写真に撮っておくことも大切です。これらの写真は、後々保険会社への状況説明や、万が一相手との認識に食い違いが生じた際のトラブル防止に役立ちます。
その場で氏名・住所・電話番号・可能であれば加入している保険会社名など、お互いの連絡先を正確に確認・交換しましょう。商業施設などの駐車場であれば、相手の車のナンバープレートを施設の管理事務所やインフォメーションカウンターに伝えて、館内アナウンスなどで呼び出してもらえる場合もあります。
また、相手の車の傷やへこみがついた箇所、自分の車のドアが当たった箇所などを、さまざまな角度からスマートフォンなどで写真に撮っておくことも大切です。これらの写真は、後々保険会社への状況説明や、万が一相手との認識に食い違いが生じた際のトラブル防止に役立ちます。
2. どんな些細な事故でも警察への届出は必須
ドアをぶつけて相手の車に傷をつけてしまった場合、これは負傷者がいない「物損事故」という交通事故にあたります。どんなに小さな傷やへこみであっても、事故の当事者には道路交通法により警察へ報告する義務があります。
相手が見つからない場合や、相手から「これくらい大丈夫ですよ」と言われた場合でも、必ず警察(110番)に連絡しましょう。
警察に届け出ることで、事故があったことを公的に証明する「交通事故証明書」を後日発行してもらうことができます。この証明書は、自動車保険を使って修理費用を補償してもらう際に、保険会社から提出を求められることが一般的です。 警察への報告を怠ると、この報告義務違反自体が道路交通法違反となり、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金に処される可能性があります。
一方で、ドアをぶつけたという物損事故そのものに対しては、基本的に運転免許の違反点数が加算されることはありません。したがって、警察に適切に報告することは、報告義務違反という罰則を避け、後の保険手続きなどを円滑に進めるために不可欠な対応なのです。
相手が見つからない場合や、相手から「これくらい大丈夫ですよ」と言われた場合でも、必ず警察(110番)に連絡しましょう。
警察に届け出ることで、事故があったことを公的に証明する「交通事故証明書」を後日発行してもらうことができます。この証明書は、自動車保険を使って修理費用を補償してもらう際に、保険会社から提出を求められることが一般的です。 警察への報告を怠ると、この報告義務違反自体が道路交通法違反となり、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金に処される可能性があります。
一方で、ドアをぶつけたという物損事故そのものに対しては、基本的に運転免許の違反点数が加算されることはありません。したがって、警察に適切に報告することは、報告義務違反という罰則を避け、後の保険手続きなどを円滑に進めるために不可欠な対応なのです。
3. 事故直後にご自身の保険会社へ連絡・相談
警察への連絡が終わったら、ご自身が加入している自動車保険会社にも速やかに事故の報告をしましょう。相手の車にできてしまった傷やへこみの修理費用については、加入中の任意保険(対物賠償責任保険など)で補償してもらえる可能性があります。
保険会社に連絡すれば、その場で今後の対応や手続きの流れについて具体的な指示を受けられます。
また、契約内容によっては保険会社の担当者が相手方との交渉の窓口になってくれることもあり、当事者同士の精神的な負担を軽減できます。
保険会社に連絡すれば、その場で今後の対応や手続きの流れについて具体的な指示を受けられます。
また、契約内容によっては保険会社の担当者が相手方との交渉の窓口になってくれることもあり、当事者同士の精神的な負担を軽減できます。
4. 即決での示談は危険!その場で金銭の約束はしない
たとえ相手から「修理代として○○円払ってくれればそれでいい」と示談を持ちかけられたり、逆にこちらから「○○円払うのでこれで」と提案したりしても、その場で当事者同士だけで示談を成立させるのは絶対に避けましょう。
見た目以上に修理費用が高額になるケースや、後から「別の箇所にも傷が見つかった」などと言われ、追加の請求を受けて深刻なトラブルに発展する可能性があります。必ず警察と保険会社を通じて、正式な手続きで対処するようにしてください。
見た目以上に修理費用が高額になるケースや、後から「別の箇所にも傷が見つかった」などと言われ、追加の請求を受けて深刻なトラブルに発展する可能性があります。必ず警察と保険会社を通じて、正式な手続きで対処するようにしてください。
当て逃げは違法!逃げた場合の罰則とリスク
「ドアを軽くぶつけただけだし、逃げてもバレないだろう...」そう考えてそのまま立ち去ってしまうのは絶対にやめましょう。
相手の車に損害を与えたにもかかわらず、危険防止の措置や警察への報告をせず無断で現場を離れる行為は「当て逃げ」と呼ばれ、道路交通法上の「危険防止措置義務違反」と「報告義務違反」にあたる違法行為です。
これらには懲役刑や罰金刑が科される可能性があるほか、行政処分として違反点数も加算されます。点数の内訳は、「危険防止措置義務違反」として5点、さらに事故の原因となった「安全運転義務違反」として2点が加わり、合計7点となる可能性があります。
これは一度で免許停止処分(行政処分前歴がない場合で30日間)となる重いペナルティです。近年は駐車場に防犯カメラが設置されていることも多く、目撃者がいなくても後日特定されるケースは少なくありません。
万が一パニックになってその場から逃げてしまった場合は、できるだけ早くご自身から警察に連絡して名乗り出ることが重要です。
後日になってからでも正直に警察に申告すれば、悪質な逃走ではないと判断され、その後の手続きが比較的円滑に進む可能性があります。(被害者が警察に届け出る前に自ら申告することで、「当て逃げ」として厳しく処罰されるのを避けられる可能性が高まります。)「気が動転して現場から離れてしまいました」と正直に、そして誠実に事情を説明すれば、報告が遅れたことに対する処分も、情状酌量により考慮される可能性があります。
相手の車に損害を与えたにもかかわらず、危険防止の措置や警察への報告をせず無断で現場を離れる行為は「当て逃げ」と呼ばれ、道路交通法上の「危険防止措置義務違反」と「報告義務違反」にあたる違法行為です。
これらには懲役刑や罰金刑が科される可能性があるほか、行政処分として違反点数も加算されます。点数の内訳は、「危険防止措置義務違反」として5点、さらに事故の原因となった「安全運転義務違反」として2点が加わり、合計7点となる可能性があります。
これは一度で免許停止処分(行政処分前歴がない場合で30日間)となる重いペナルティです。近年は駐車場に防犯カメラが設置されていることも多く、目撃者がいなくても後日特定されるケースは少なくありません。
万が一パニックになってその場から逃げてしまった場合は、できるだけ早くご自身から警察に連絡して名乗り出ることが重要です。
後日になってからでも正直に警察に申告すれば、悪質な逃走ではないと判断され、その後の手続きが比較的円滑に進む可能性があります。(被害者が警察に届け出る前に自ら申告することで、「当て逃げ」として厳しく処罰されるのを避けられる可能性が高まります。)「気が動転して現場から離れてしまいました」と正直に、そして誠実に事情を説明すれば、報告が遅れたことに対する処分も、情状酌量により考慮される可能性があります。
修理費は誰が払う?保険使用の損得と負担割合
「自分の保険を使うと翌年以降の保険料が上がるし…修理代は自腹で払うべき?」と悩む方もいるでしょう。
基本的に、駐車中に停止している車にドアをぶつけて傷つけた場合、事故の過失割合は10:0(加害者:被害者)となり、修理費用は全て加害者が負担する責任があります。相手の車の修理代金が高額になる場合は、ご自身が加入している任意保険(対物賠償責任保険)を使って補償してもらうことを検討しましょう。
保険を使えば、ご自身の直接的な出費は契約時に設定した免責金額(自己負担額)で済み、その後の相手方との交渉や修理工場への支払いなどは、保険会社が対応してくれます。
ただし、保険を使うと翌年度以降は等級が3等級ダウンし(事故有係数適用期間も加算され)、保険料が上がる点に注意が必要です。修理代を保険で支払う場合と、自腹で支払う場合とで、将来の保険料アップ分も含めてどちらが経済的に得かはケースバイケースです。
例えば数万円程度の軽微な修理であれば、保険を使わずに自費で支払った方が、結果的に総支払額は安く済む場合もあります。迷ったときは、まず保険会社に事故の報告をした上で、「もし保険を使った場合、翌年度以降の保険料はどのくらい上がるか」という試算をしてもらい、修理費用の見積額と比較して慎重に判断すると良いでしょう。
いずれにせよ、保険を使うかどうかにかかわらず、事故対応の初期段階で保険会社へ連絡だけは必ずしておき、今後の手続きについて指示を仰ぐようにしてください。
基本的に、駐車中に停止している車にドアをぶつけて傷つけた場合、事故の過失割合は10:0(加害者:被害者)となり、修理費用は全て加害者が負担する責任があります。相手の車の修理代金が高額になる場合は、ご自身が加入している任意保険(対物賠償責任保険)を使って補償してもらうことを検討しましょう。
保険を使えば、ご自身の直接的な出費は契約時に設定した免責金額(自己負担額)で済み、その後の相手方との交渉や修理工場への支払いなどは、保険会社が対応してくれます。
ただし、保険を使うと翌年度以降は等級が3等級ダウンし(事故有係数適用期間も加算され)、保険料が上がる点に注意が必要です。修理代を保険で支払う場合と、自腹で支払う場合とで、将来の保険料アップ分も含めてどちらが経済的に得かはケースバイケースです。
例えば数万円程度の軽微な修理であれば、保険を使わずに自費で支払った方が、結果的に総支払額は安く済む場合もあります。迷ったときは、まず保険会社に事故の報告をした上で、「もし保険を使った場合、翌年度以降の保険料はどのくらい上がるか」という試算をしてもらい、修理費用の見積額と比較して慎重に判断すると良いでしょう。
いずれにせよ、保険を使うかどうかにかかわらず、事故対応の初期段階で保険会社へ連絡だけは必ずしておき、今後の手続きについて指示を仰ぐようにしてください。
二度と繰り返さない!ドアパンチを防ぐ5つの予防策
1. 車間に余裕のある駐車枠を選ぶ
可能な限り隣に車がいない場所や、駐車枠の幅にゆとりのある場所に駐車し、ドアを開けてもぶつかりにくい環境を選びましょう。特に高級車や大切にされていることがうかがえる車の隣は、万が一の際のリスクを考え、避けた方が無難です。
2. 坂道・傾斜地を避けドアの意図せぬ開閉を防ぐ
坂道や傾斜地では、重力でドアが思った以上に勢いよく開いてしまったり、逆に閉まってきたりすることがあります。できるだけ平坦な場所を選んで駐車することで、ドアの不意な動きを防ぎましょう。
3. 強風対策:風向きを考えて駐車する
風の強い日は、ドアが風にあおられて急に大きく開き、隣の車にぶつけてしまう危険があります。風向きを考え、可能であれば風上に車の側面が向かないように駐車するか、屋内の駐車場を利用するなどの工夫をしましょう。
4. ドアエッジプロテクターなどで物理的に保護する
市販のドアガード(ドアエッジプロテクター)やボディサイドモールなど、ドア開閉時の接触による傷を防ぐ保護グッズを取り付けておくのも効果的です。万一ドアが軽く当たってしまっても、こうしたクッション材があれば、相手の車と自分の車の双方の被害を最小限にできます。
5. 子どものドア開閉は大人がサポートする
小さなお子さんが同乗している場合、周囲の状況を判断せずに勢いよくドアを開けてしまわないよう、特に注意が必要です。乗り降りの際は、大人が先に降りて外からドアを開けてあげるか、子供が開ける際はしっかりドアを支えて「ゆっくり開けようね」と声をかけるなど、大人がサポートしてあげてください。
可能な限り隣に車がいない場所や、駐車枠の幅にゆとりのある場所に駐車し、ドアを開けてもぶつかりにくい環境を選びましょう。特に高級車や大切にされていることがうかがえる車の隣は、万が一の際のリスクを考え、避けた方が無難です。
2. 坂道・傾斜地を避けドアの意図せぬ開閉を防ぐ
坂道や傾斜地では、重力でドアが思った以上に勢いよく開いてしまったり、逆に閉まってきたりすることがあります。できるだけ平坦な場所を選んで駐車することで、ドアの不意な動きを防ぎましょう。
3. 強風対策:風向きを考えて駐車する
風の強い日は、ドアが風にあおられて急に大きく開き、隣の車にぶつけてしまう危険があります。風向きを考え、可能であれば風上に車の側面が向かないように駐車するか、屋内の駐車場を利用するなどの工夫をしましょう。
4. ドアエッジプロテクターなどで物理的に保護する
市販のドアガード(ドアエッジプロテクター)やボディサイドモールなど、ドア開閉時の接触による傷を防ぐ保護グッズを取り付けておくのも効果的です。万一ドアが軽く当たってしまっても、こうしたクッション材があれば、相手の車と自分の車の双方の被害を最小限にできます。
5. 子どものドア開閉は大人がサポートする
小さなお子さんが同乗している場合、周囲の状況を判断せずに勢いよくドアを開けてしまわないよう、特に注意が必要です。乗り降りの際は、大人が先に降りて外からドアを開けてあげるか、子供が開ける際はしっかりドアを支えて「ゆっくり開けようね」と声をかけるなど、大人がサポートしてあげてください。
隣の車にドアを当てたときの重要ポイント総まとめ
普段から少し気をつけるだけで、こうした「ドアパンチ事故」はかなり防げます。
それでも万が一ぶつけてしまった場合も、今回ご紹介した手順に沿って、まずは正直に、そして落ち着いて対応すれば大丈夫です。初心者の方も過度に心配しすぎず、万一の際には適切な対処を行い、日頃から安全運転と周囲への配慮を心がけましょう。
大切な愛車と周囲の車を守るために、ぜひ参考にしてみてくださいね。
それでも万が一ぶつけてしまった場合も、今回ご紹介した手順に沿って、まずは正直に、そして落ち着いて対応すれば大丈夫です。初心者の方も過度に心配しすぎず、万一の際には適切な対処を行い、日頃から安全運転と周囲への配慮を心がけましょう。
大切な愛車と周囲の車を守るために、ぜひ参考にしてみてくださいね。