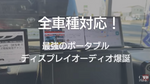クルマやバイクを芸術に高める
更新日:2024.09.09

※この記事には広告が含まれます
芸術という言葉を定義することは難しい。芸術とは精神的、感覚的な渇望を鎮める表現活動であり、個人の価値と技術によって生み出されるものだからだ。そしてその個人の表現活動が誰かを感動させ、社会に意味や価値を持たれて初めて芸術と呼べるようになる。
text:伊丹孝裕、山下敦史 [aheadアーカイブス vol.159 2016年2月号]
text:伊丹孝裕、山下敦史 [aheadアーカイブス vol.159 2016年2月号]
クルマやバイクを芸術に高める
また芸術は、それが個人的な活動であるにも関わらず、他人によって評価され、互いに影響されていくものでもある。クルマやバイクそのものが芸術か否かという課題は別として、今回はクルマやバイクを通した表現活動を行っているふたりの男に注目してみたい。
カスタムの潮流を変えたオレンジ色のBMW
text:伊丹孝裕
バイクのシートにまたがり、エンジンをかけ、スロットルをひねる。その瞬間瞬間に湧き起こる心の昂ぶりを雑誌で表現するという仕事を始めて間もない頃、その誌面を見た先輩編集者から「まだちゃんとカタチにはなってないね。でもやろうとしていることは分かる。だからがんばって」と言われたことがあった。
カタチ、形、容。
それが何気なく口から出たものだったのか、意図的なものだったのかは分からなかったが、その「カタチ」という言い回しが妙に印象に残り、しばらく心のどこかに引っ掛かったままになっていた。
そんなある日、それをスッと飲み込ませてくれた一篇のコラムに出会った。そこにはモノのカタチには良し悪しがあること、とりわけバイクはまずカタチが大切で性能はその次であること、なぜならカタチが良ければ中身もほぼ例外なく素晴らしく、そういうカタチの集合体であるバイクには美学や哲学が宿り、芸術にも成り得ること。
そんなようなことがロックとリーゼントとの関係性、ホンダCR110に搭載されていたエンジンの美しさなどを通して書かれていた。
バイクのシートにまたがり、エンジンをかけ、スロットルをひねる。その瞬間瞬間に湧き起こる心の昂ぶりを雑誌で表現するという仕事を始めて間もない頃、その誌面を見た先輩編集者から「まだちゃんとカタチにはなってないね。でもやろうとしていることは分かる。だからがんばって」と言われたことがあった。
カタチ、形、容。
それが何気なく口から出たものだったのか、意図的なものだったのかは分からなかったが、その「カタチ」という言い回しが妙に印象に残り、しばらく心のどこかに引っ掛かったままになっていた。
そんなある日、それをスッと飲み込ませてくれた一篇のコラムに出会った。そこにはモノのカタチには良し悪しがあること、とりわけバイクはまずカタチが大切で性能はその次であること、なぜならカタチが良ければ中身もほぼ例外なく素晴らしく、そういうカタチの集合体であるバイクには美学や哲学が宿り、芸術にも成り得ること。
そんなようなことがロックとリーゼントとの関係性、ホンダCR110に搭載されていたエンジンの美しさなどを通して書かれていた。
コラムの書き手は'86年にバイク専門誌『クラブマン』を創刊した初代編集長の小野かつじさん。僕に声を掛けてくれた先輩編集者というのがその創刊メンバーのひとりでもあった池田 伸さん(現『ホットバイクジャパン』編集長)である。
カタチにまつわるそのコラムに触れた時、なんとなく池田さんに言われたことの断片が分かった気がした。
当時の僕は『クラブマン』の編集長になったばかりで、素晴らしい知識と経験に基づくライターの原稿とカメラマンが切り撮ってくれる美しいバイクの写真、それらをより印象的に見せようとレイアウトしてくれる誌面デザイナーのアイデアを持て余し、自分が思い描くクラブマンの理想像の中で上手くバランスさせることができずにいた。
カスタムで言えば、ひとつひとつのブランドは一流なのに目的が異なるパーツを揃えてしまったのと同じ。それを「カタチになってない」という言葉で気づかせてくれたのだと思う。今から十数年前のことである。
カタチにまつわるそのコラムに触れた時、なんとなく池田さんに言われたことの断片が分かった気がした。
当時の僕は『クラブマン』の編集長になったばかりで、素晴らしい知識と経験に基づくライターの原稿とカメラマンが切り撮ってくれる美しいバイクの写真、それらをより印象的に見せようとレイアウトしてくれる誌面デザイナーのアイデアを持て余し、自分が思い描くクラブマンの理想像の中で上手くバランスさせることができずにいた。
カスタムで言えば、ひとつひとつのブランドは一流なのに目的が異なるパーツを揃えてしまったのと同じ。それを「カタチになってない」という言葉で気づかせてくれたのだと思う。今から十数年前のことである。
俯瞰して見れば、その頃のバイク業界とバイク雑誌そのものも混迷の時代に入っていた。'80年代には熱狂のレースブームがあり、'90年代には国産大排気量モデルのカスタムブームが到来。'00年代に入ってからそれらに取って代わる大きなムーブメントが巻き起こったかと言えば起こらなかった。あるいは作れなかった。
台頭する輸入車メーカーを前にして国産メーカーが右往左往していたのと同様、雑誌自体も迷走し、その真っただ中にいた僕はカッコいいモノだけを追求しようと'80年代に立ち上がった小野さんや池田さんの世代を眩しく、そして羨ましく思い、華飾にまみれた4気筒カスタムで'90年代を荒らした次の世代の無粋さを疎ましく思いながら過ごしていた。
だからといってそれを打破するなにかを思いつかないまま、バイクの世界から徐々に大人の粋や品のようなモノが失われていくのを感じていたのだ。
台頭する輸入車メーカーを前にして国産メーカーが右往左往していたのと同様、雑誌自体も迷走し、その真っただ中にいた僕はカッコいいモノだけを追求しようと'80年代に立ち上がった小野さんや池田さんの世代を眩しく、そして羨ましく思い、華飾にまみれた4気筒カスタムで'90年代を荒らした次の世代の無粋さを疎ましく思いながら過ごしていた。
だからといってそれを打破するなにかを思いつかないまま、バイクの世界から徐々に大人の粋や品のようなモノが失われていくのを感じていたのだ。
*
そんな中、新しいスタイルが徐々に芽生えていることを知った。それがBMWやモト・グッツィ、ドゥカティの中でもごくありふれたモデルをベースに選び、そこに秘められたスポーツバイクの資質を引き出そうとするカフェレーサーの新潮流で、その先駆けになっていたのが横浜のスタンホープ、そして当時は吉祥寺にショップを構えていたリトモ・セレーノだった。
そんなふたつのショップに共通していたのは切り捨てられるモノはすべて切り捨てようとする削ぎ落としの美学であり、'90年代の華飾のスタイルとは真逆。そこに高い美意識を感じた僕はそれぞれのカスタムを積極的に誌面で展開することで新しい流れが加速することを期待したのである。
そんな中、新しいスタイルが徐々に芽生えていることを知った。それがBMWやモト・グッツィ、ドゥカティの中でもごくありふれたモデルをベースに選び、そこに秘められたスポーツバイクの資質を引き出そうとするカフェレーサーの新潮流で、その先駆けになっていたのが横浜のスタンホープ、そして当時は吉祥寺にショップを構えていたリトモ・セレーノだった。
そんなふたつのショップに共通していたのは切り捨てられるモノはすべて切り捨てようとする削ぎ落としの美学であり、'90年代の華飾のスタイルとは真逆。そこに高い美意識を感じた僕はそれぞれのカスタムを積極的に誌面で展開することで新しい流れが加速することを期待したのである。
とりわけリトモ・セレーノの名が広く知られるようになったきっかけが、鮮やかなオレンジ色のカウリングとゼッケン46を纏ったBMWのR80レーサーの存在だろう。
その製作記を『クラブマン』にて連載してもらっていたわけだが、ボロボロの不動車だった車両がいつしか美しいレーサーへと姿を変え、しかも多くのレースで優勝するに至った過程にBMWフリークの多くが溜飲を下げ、BMWというブランドを気にも留めていなかったライダーはそのポテンシャルに目を見張った。
いつしか「オレンジのR80レーサー」はリトモ・セレーノとその代表を務めていた中嶋志朗さんの名刺代わりになり、この数年の人生において急激な転機をももたらしたのである。
予兆は'13年5月にあった。その時、BMWモトラッドのドイツ本社は創業90周年を記念したコンセプト90と呼ばれるモデルを発表。オレンジに彩られたハーフカウルを持つそれは明らかにリトモ・セレーノのR80レーサーを彷彿とさせるもので、実際本社でチーフデザイナーを務めるオラ・ステネガルド氏は「シロウのバイクに影響を受けた」と公の場で認めたのだった。
その製作記を『クラブマン』にて連載してもらっていたわけだが、ボロボロの不動車だった車両がいつしか美しいレーサーへと姿を変え、しかも多くのレースで優勝するに至った過程にBMWフリークの多くが溜飲を下げ、BMWというブランドを気にも留めていなかったライダーはそのポテンシャルに目を見張った。
いつしか「オレンジのR80レーサー」はリトモ・セレーノとその代表を務めていた中嶋志朗さんの名刺代わりになり、この数年の人生において急激な転機をももたらしたのである。
予兆は'13年5月にあった。その時、BMWモトラッドのドイツ本社は創業90周年を記念したコンセプト90と呼ばれるモデルを発表。オレンジに彩られたハーフカウルを持つそれは明らかにリトモ・セレーノのR80レーサーを彷彿とさせるもので、実際本社でチーフデザイナーを務めるオラ・ステネガルド氏は「シロウのバイクに影響を受けた」と公の場で認めたのだった。
▶︎写真の車両はBMW R100Sの1976年型がベース。前後フェンダー、ラムエアダクト、シートベース、マフラー、スイングアーム加工によるモノサス化、エンジンのフルオーバーホールまで、塗装とシート製作以外は中嶋氏自身の手による。タンクはヘインリッヒのリプロ品を加工装着。
以来、中嶋さんの人生は目まぐるしさを増していった。それからほどなくリトモ・セレーノの代表を辞し、都内を離れて八ヶ岳で新たなファクトリー「46Works(ヨンロクワークス)」を設立することになるのだが、そこへ今度はBMWジャパンからR nine Tをベースにしたカスタムバイクプロジェクトへの参加オファーが届き、これを快諾。
徹底して走りを追求したクラブマンレース仕様へと変貌を遂げたそれは瞬く間に世界に拡散して話題を集め、さらにはKTMジャパンの依頼でRC8Rをベースにしたショーモデルを完成させると「ベストヨーロピアンモーターサイクル」アワードを受賞するなど、次々と大きな成果を残し続けている。
以来、中嶋さんの人生は目まぐるしさを増していった。それからほどなくリトモ・セレーノの代表を辞し、都内を離れて八ヶ岳で新たなファクトリー「46Works(ヨンロクワークス)」を設立することになるのだが、そこへ今度はBMWジャパンからR nine Tをベースにしたカスタムバイクプロジェクトへの参加オファーが届き、これを快諾。
徹底して走りを追求したクラブマンレース仕様へと変貌を遂げたそれは瞬く間に世界に拡散して話題を集め、さらにはKTMジャパンの依頼でRC8Rをベースにしたショーモデルを完成させると「ベストヨーロピアンモーターサイクル」アワードを受賞するなど、次々と大きな成果を残し続けている。
▶︎写真はスーパースポーツのKTM RC8R(2012年型)をベースにしたカスタム車両。タンク、シートカウル、ラジエターシュラウドは、中嶋氏自らがアルミ板から叩き出したワンオフ品。エキパイの等長とバンク角を考慮したチタン製のマフラーも手曲げと輪切りにしたチタンパイプの溶接によって製作。クラシカルさを醸し出すアルミパイプを使ったシートレールも手曲げで成形されている。
そんな中嶋志朗というビルダーは才能とセンスと運に恵まれた成功者なのだろうか? それに答えを出すなら半分正解で半分は誤りかもしれない。
確かになにかを生み出すスキルとセンスが備わっていることは間違いなく、20代の頃はギタリストとして生計を立てていたかと思えば、その一方でバイクにまつわる技術をどこのショップに勤めることもなくほぼ独学でマスター。エンジンや車体の整備はもちろん、旋盤、溶接、板金に至るすべてをひとりでこなすまでになったというから驚かされる。
誰に師事するわけでも強制されたわけでもないのにそれをひとりでやろうと決め、失敗と経験と研究を重ねて今に至っていることを思えば、器用と言われる裏でどれほどの努力を要してきたのか。それを推し量ることは難しいが、RC8Rの細部を見ればその一端を窺うことはできる。
そんな中嶋志朗というビルダーは才能とセンスと運に恵まれた成功者なのだろうか? それに答えを出すなら半分正解で半分は誤りかもしれない。
確かになにかを生み出すスキルとセンスが備わっていることは間違いなく、20代の頃はギタリストとして生計を立てていたかと思えば、その一方でバイクにまつわる技術をどこのショップに勤めることもなくほぼ独学でマスター。エンジンや車体の整備はもちろん、旋盤、溶接、板金に至るすべてをひとりでこなすまでになったというから驚かされる。
誰に師事するわけでも強制されたわけでもないのにそれをひとりでやろうと決め、失敗と経験と研究を重ねて今に至っていることを思えば、器用と言われる裏でどれほどの努力を要してきたのか。それを推し量ることは難しいが、RC8Rの細部を見ればその一端を窺うことはできる。
例えば5枚のアルミ板で構成された燃料タンクの継ぎ目のない滑らかさ、等長になるように取り回し、巧みに溶接されたエキパイの躍動感、見事なアールで叩き出されたアルミのシートカウル、シンプルに整然と左右対称であるべきところはその通りに配されたコードやホース類など、そのカタチに至るまでに掛けられた手間と時間を少し想像すれば、決してそれを才能やセンスのひと言で片付けることなどできない。
いずれにしても、そこに貫かれているのは虚飾の一切を切り捨てていく引き算の手法だ。それは中嶋さんが若かりし頃に傾倒していたジャズにも通じるもので、一小節の中に音を詰め込んでいくハードロックとは対称的に、ジャズの美学は音をいかに間引き、1音に意味を持たせられるか。ある意味、それと同じことをバイクの世界で表現しようとしているのだ。
小さく、軽く、シンプルに。もうこれ以上を削ると正立しないというギリギリまですべてを追い込む機能美のカタチは、同時にスロットルを開けた時の心地よさを追求したピュアな走りのカタチと言ってもいい。今、その世界観に多くのバイクフリークが魅了され、そこに新しい芸術性を見い出しているのである。
いずれにしても、そこに貫かれているのは虚飾の一切を切り捨てていく引き算の手法だ。それは中嶋さんが若かりし頃に傾倒していたジャズにも通じるもので、一小節の中に音を詰め込んでいくハードロックとは対称的に、ジャズの美学は音をいかに間引き、1音に意味を持たせられるか。ある意味、それと同じことをバイクの世界で表現しようとしているのだ。
小さく、軽く、シンプルに。もうこれ以上を削ると正立しないというギリギリまですべてを追い込む機能美のカタチは、同時にスロットルを開けた時の心地よさを追求したピュアな走りのカタチと言ってもいい。今、その世界観に多くのバイクフリークが魅了され、そこに新しい芸術性を見い出しているのである。
中嶋志朗/Shiro Nakajima
1973年埼玉県生まれ。2001年にBMWや、モトグッツィなど’70〜’90年代ヨーロッパ車を扱うカスタムショップ「リトモ・セレーノ」を設立。2014年4月に八ヶ岳南麓に自身のファクトリー、「46ワークス」を立ち上げた。フルオーダーのカスタムバイク製作とメンテナンスを中心に、クラシックカーのパーツ製作などの創作活動を展開している。
1973年埼玉県生まれ。2001年にBMWや、モトグッツィなど’70〜’90年代ヨーロッパ車を扱うカスタムショップ「リトモ・セレーノ」を設立。2014年4月に八ヶ岳南麓に自身のファクトリー、「46ワークス」を立ち上げた。フルオーダーのカスタムバイク製作とメンテナンスを中心に、クラシックカーのパーツ製作などの創作活動を展開している。
-----------------------------------------
text:伊丹孝裕/Takahiro Itami
1971年生まれ。二輪専門誌『クラブマン』の編集長を務めた後にフリーランスのモーターサイクルジャーナリストへ転向。レーシングライダーとしても活動し、これまでマン島TTやパイクスピーク、鈴鹿八耐を始めとする国内外のレースに参戦してきた。国際A級ライダー。
text:伊丹孝裕/Takahiro Itami
1971年生まれ。二輪専門誌『クラブマン』の編集長を務めた後にフリーランスのモーターサイクルジャーナリストへ転向。レーシングライダーとしても活動し、これまでマン島TTやパイクスピーク、鈴鹿八耐を始めとする国内外のレースに参戦してきた。国際A級ライダー。
クルマの芸術性を引き出す 「Octane」日本版
極論してしまえば、「自分の好きなものが芸術だ」で済む話なのかもしれない。
だがその想いを誰かに伝えようとすると、強い信念と努力が必要となる。もしかして、その行為こそを芸術と呼ぶのだろう。この取材を通して感じたのは、そんなことだった。
クラシック&パフォーマンスカーマガジン「Octane(オクタン)」日本版編集長を務める堀江史朗さんに、その誌面作りに懸ける情熱の一端をうかがった。堀江氏は「カーセンサー」などを手掛ける名編集長として活躍した後、独立。新たな紙メディアを持ちたいと模索していたとき、「Octane」に出会う。
2003年に英国で創刊された同誌は、「一番新しい〝旧い〟クルマの雑誌」と銘打ち、旧いクルマを〝ロードムービーのような〟美しくストーリー性のあるビジュアルで扱う斬新な誌面構成と、良質なテキストで人気を高め、今では欧州で最も人気のあるクラシック&ビンテージカーマガジンとして認められている。
「従来のクルマ誌って、どうしてもハードやパフォーマンスがまっ先に来ていたんですよ。でもOctaneは人がメインなんです。それはクルマのオーナーという意味ではなくて、〝誰がそのクルマを作ったのか〟〝どんな人がどうやってそのクルマ愛したのか〟といった、クルマの奥にある人のストーリーを描く。それがおもしろいし、そういうことを知ることで、もっとクルマに対する理解が深まっていくものだと思うんです」
このOctaneを日本で出版できないかと動き始めた堀江氏だが、簡単に事が進んだわけではなかったという。
「最初向こうが提示してきた条件はかなり厳しかったんです。ロイヤリティもえらく高かったし、本国と同じ月刊で出せとか、使用していい英国版のコンテンツは過去1年以内に掲載されたものに限る、とか。到底実現できるものではなかったんです」
それでも、堀江氏は現地スタッフと粘り強く交渉を続けた。
「それこそ、膝をつき合わせるようにして話し合いました。契約に関することだけでなく、『Octane』としてやっていいこと、やってほしくないこと。それからどんなクルマが好きだとか、いろんなことを。結果、とにかく1回出させてほしい、それを見て最終的な判断を下してほしい、といういうところにこぎ着けたんです」
こうして2013年3月26日、「Octane日本版」が創刊される。それは単に英国版を翻訳したというだけのものではなく、まずテーマを日本の読者に合ったものに設定し、それに沿って英国版から記事を選択して再構成、さらに日本版独自のコンテンツも加えるといったオリジナリティあふれるものだった。それでいて、もちろんOctaneらしさは失われていない。
「雑誌というより本を作っている感覚なんです。だからいつ読み返してもいいように『昨年』とか『今年』とは書かないですし、年式やスペックの間違いも絶対にできない。記事を翻訳する場合も、あえて最初は直訳に近い形で逐一日本語にして、クルマやその歴史に詳しいスタッフが記述に間違いがないか丹念にチェックした上で文章を整えるんです」
英文で例えば1ページの記事を日本語にした場合、活字の大きさや語彙の関係で、どうしても文字スペースはより多く必要となってしまう。その場合も元の記事のイメージを崩さないよう写真の大きさやレイアウトを変更し、時には独自に新たな写真を手配して追加することもあるという。元の記事があるから楽どころか、より手間のかかる編集作業が必要なのだ。
だがその苦労が奏功し、「Octane日本版」は日本の読者に受け入れられたのみならず、完成度の高さで本国のスタッフとの信頼関係も強めることになった。
「本国としても最初はあんまり古い記事を使われるのはいやだったんでしょうが、こいつら(日本版スタッフ)なら大丈夫だと思われたんですかね、(創刊から)これまでの10年分の記事のどれでも好きなの使っていいよって」
だがその想いを誰かに伝えようとすると、強い信念と努力が必要となる。もしかして、その行為こそを芸術と呼ぶのだろう。この取材を通して感じたのは、そんなことだった。
クラシック&パフォーマンスカーマガジン「Octane(オクタン)」日本版編集長を務める堀江史朗さんに、その誌面作りに懸ける情熱の一端をうかがった。堀江氏は「カーセンサー」などを手掛ける名編集長として活躍した後、独立。新たな紙メディアを持ちたいと模索していたとき、「Octane」に出会う。
2003年に英国で創刊された同誌は、「一番新しい〝旧い〟クルマの雑誌」と銘打ち、旧いクルマを〝ロードムービーのような〟美しくストーリー性のあるビジュアルで扱う斬新な誌面構成と、良質なテキストで人気を高め、今では欧州で最も人気のあるクラシック&ビンテージカーマガジンとして認められている。
「従来のクルマ誌って、どうしてもハードやパフォーマンスがまっ先に来ていたんですよ。でもOctaneは人がメインなんです。それはクルマのオーナーという意味ではなくて、〝誰がそのクルマを作ったのか〟〝どんな人がどうやってそのクルマ愛したのか〟といった、クルマの奥にある人のストーリーを描く。それがおもしろいし、そういうことを知ることで、もっとクルマに対する理解が深まっていくものだと思うんです」
このOctaneを日本で出版できないかと動き始めた堀江氏だが、簡単に事が進んだわけではなかったという。
「最初向こうが提示してきた条件はかなり厳しかったんです。ロイヤリティもえらく高かったし、本国と同じ月刊で出せとか、使用していい英国版のコンテンツは過去1年以内に掲載されたものに限る、とか。到底実現できるものではなかったんです」
それでも、堀江氏は現地スタッフと粘り強く交渉を続けた。
「それこそ、膝をつき合わせるようにして話し合いました。契約に関することだけでなく、『Octane』としてやっていいこと、やってほしくないこと。それからどんなクルマが好きだとか、いろんなことを。結果、とにかく1回出させてほしい、それを見て最終的な判断を下してほしい、といういうところにこぎ着けたんです」
こうして2013年3月26日、「Octane日本版」が創刊される。それは単に英国版を翻訳したというだけのものではなく、まずテーマを日本の読者に合ったものに設定し、それに沿って英国版から記事を選択して再構成、さらに日本版独自のコンテンツも加えるといったオリジナリティあふれるものだった。それでいて、もちろんOctaneらしさは失われていない。
「雑誌というより本を作っている感覚なんです。だからいつ読み返してもいいように『昨年』とか『今年』とは書かないですし、年式やスペックの間違いも絶対にできない。記事を翻訳する場合も、あえて最初は直訳に近い形で逐一日本語にして、クルマやその歴史に詳しいスタッフが記述に間違いがないか丹念にチェックした上で文章を整えるんです」
英文で例えば1ページの記事を日本語にした場合、活字の大きさや語彙の関係で、どうしても文字スペースはより多く必要となってしまう。その場合も元の記事のイメージを崩さないよう写真の大きさやレイアウトを変更し、時には独自に新たな写真を手配して追加することもあるという。元の記事があるから楽どころか、より手間のかかる編集作業が必要なのだ。
だがその苦労が奏功し、「Octane日本版」は日本の読者に受け入れられたのみならず、完成度の高さで本国のスタッフとの信頼関係も強めることになった。
「本国としても最初はあんまり古い記事を使われるのはいやだったんでしょうが、こいつら(日本版スタッフ)なら大丈夫だと思われたんですかね、(創刊から)これまでの10年分の記事のどれでも好きなの使っていいよって」
▶︎英国BBC「TopGear」で司会のジェレミー・クラークソンが絶賛した究極のジャガーEタイプといえる「イーグル 」も誌面に登場。 日本では情報が少ない希少なクルマの記事も多い。ちなみに写真の「イーグル・ロードラッグGT」は、4.7ℓの直列6気筒エンジンにインジェクションを組み合わせて346馬力を発揮。アルミボディを採用し、車両重量は1,038kgしかない。
季刊という刊行ペースを認めてもらえたことも大きかったという。発行して読者の反応を見ながら次号を作るという好循環が生まれた。過去の良質コンテンツを選ぶ自由度が上がったこともあって、日本版はいわば〝Octaneベスト版〟と呼ぶべきものとなったのだ。
現在では、日本版の完成度に引っ張られたのか、本国版も紙質をより上質な物に変えたり、記事や表紙の構成に日本版を参考にしたであろうことが見受けられるなど、互いにいい影響を与え合う存在になっているという。
一方で堀江氏は「こんな本をやりながらも、クラシックカーってところに軸足を置かないようにしているんですよ」と語る。
「懐古趣味にはしたくないんです。旧い時代のあのクルマが好きとか、それは当然あっていいんですけど、それだけになると骨董になっちゃうんです。旧いクルマを通じて今のクルマも楽しむというところにつなげていきたい」
戦前から現代まで、スポーツカーからラグジュアリーカーまで。軸足はあくまでも全時代、全ジャンルの〝ただのクルマ好き〟でありたい。「今のクルマも超好き」だからこそ、堀江氏は「〝今〟がどこからやってきたのかを知ってほしい。旧いクルマがあって、それが今のクルマに変わっていっていることを理解してほしいんです」と強調する。
「Octane」に載る美しい名車たち。その美しさとは何なのか、どこから来るのか。堀江氏は「この手の旧いクルマってもう作り出せないじゃないですか。僕たちのやっていることは、結局終わりゆくものを下支えしているだけなのかっていう危惧はあるんですよね」と前置きしながらも、「パワーがあるとか、コーナリング性能だとかの絶対的なパフォーマンスよりも、実際に走ってみたときの体感的なフィーリングの方が重要だと思う。
デザインひとつ取っても人が実際に触れた時のボディラインの感触とか、コンピュータが作らないであろうユニークな形であるだとか、何で今はできないんだろうってことに気付くべきじゃないでしょうか」と語る。
堀江氏が「Octane日本版」を作るきっかけとなった「人がメイン」にクルマ作りは立ち返るべきだと。
高級車は最初から高級だったかもしれないが、名車は最初から名車だったわけではない。そのクルマを生み出した人々、レースでの勝利に尽力した人々、そして愛して乗り継いだ人々、多くの人間が紡いできた伝説が、物語が、そのクルマを名車へと、芸術へと高めていったのだ。「Octane日本版」がやろうとしていることは、そんな物語を伝えていくということなんだと思う。
そしてそれこそが、芸術活動の本質なんじゃないだろうか。知らなくたってクルマは楽しめるけど、その奥に蓄えられた歴史や人や物語を知れば、もっとクルマを好きになれる。もっと豊かになれる。好きという気持ちそのものは個人的なものだけど、誰かに伝えることで共感を呼び、一つ一つが寄り集り、大げさに言えば社会をも動かしていくのだ。
季刊という刊行ペースを認めてもらえたことも大きかったという。発行して読者の反応を見ながら次号を作るという好循環が生まれた。過去の良質コンテンツを選ぶ自由度が上がったこともあって、日本版はいわば〝Octaneベスト版〟と呼ぶべきものとなったのだ。
現在では、日本版の完成度に引っ張られたのか、本国版も紙質をより上質な物に変えたり、記事や表紙の構成に日本版を参考にしたであろうことが見受けられるなど、互いにいい影響を与え合う存在になっているという。
一方で堀江氏は「こんな本をやりながらも、クラシックカーってところに軸足を置かないようにしているんですよ」と語る。
「懐古趣味にはしたくないんです。旧い時代のあのクルマが好きとか、それは当然あっていいんですけど、それだけになると骨董になっちゃうんです。旧いクルマを通じて今のクルマも楽しむというところにつなげていきたい」
戦前から現代まで、スポーツカーからラグジュアリーカーまで。軸足はあくまでも全時代、全ジャンルの〝ただのクルマ好き〟でありたい。「今のクルマも超好き」だからこそ、堀江氏は「〝今〟がどこからやってきたのかを知ってほしい。旧いクルマがあって、それが今のクルマに変わっていっていることを理解してほしいんです」と強調する。
「Octane」に載る美しい名車たち。その美しさとは何なのか、どこから来るのか。堀江氏は「この手の旧いクルマってもう作り出せないじゃないですか。僕たちのやっていることは、結局終わりゆくものを下支えしているだけなのかっていう危惧はあるんですよね」と前置きしながらも、「パワーがあるとか、コーナリング性能だとかの絶対的なパフォーマンスよりも、実際に走ってみたときの体感的なフィーリングの方が重要だと思う。
デザインひとつ取っても人が実際に触れた時のボディラインの感触とか、コンピュータが作らないであろうユニークな形であるだとか、何で今はできないんだろうってことに気付くべきじゃないでしょうか」と語る。
堀江氏が「Octane日本版」を作るきっかけとなった「人がメイン」にクルマ作りは立ち返るべきだと。
高級車は最初から高級だったかもしれないが、名車は最初から名車だったわけではない。そのクルマを生み出した人々、レースでの勝利に尽力した人々、そして愛して乗り継いだ人々、多くの人間が紡いできた伝説が、物語が、そのクルマを名車へと、芸術へと高めていったのだ。「Octane日本版」がやろうとしていることは、そんな物語を伝えていくということなんだと思う。
そしてそれこそが、芸術活動の本質なんじゃないだろうか。知らなくたってクルマは楽しめるけど、その奥に蓄えられた歴史や人や物語を知れば、もっとクルマを好きになれる。もっと豊かになれる。好きという気持ちそのものは個人的なものだけど、誰かに伝えることで共感を呼び、一つ一つが寄り集り、大げさに言えば社会をも動かしていくのだ。
▶︎1、2枚目の2冊はOctane日本版。表紙に日本の自動車専門誌では珍しい背景のない写真を組み合わせている。3枚目は本家であるイギリス版の表紙。2枚目の日本版と同じアストンマーティンDB6を特集しているが、日本版は独自のテーマで特集を展開している。本国と使用する写真が異なっているのもOctane 日本版の特徴である。4枚目の表紙はOctaneイギリス版を定期購読契約している読者向けに製作されたもの。このように表紙だけを見てもOctaneがクルマの美しさにこだわっていることが分かる。
堀江史朗/Shiro Horie
リクルートにて長く『カーセンサー』『カーセンサーEDGE』の編集長を務めた後、独立。株式会社ボストンを設立し、各種メディアやサイトの制作編集の他、自動車業界のマーケティングやイベント運営など多方面で活躍。2013年、『Octane』日本版を発行。現在は株式会社CCCカーライフラボ代表取締役。カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社ライフスタイル創造本部カーライフ研究所所長も兼任。
リクルートにて長く『カーセンサー』『カーセンサーEDGE』の編集長を務めた後、独立。株式会社ボストンを設立し、各種メディアやサイトの制作編集の他、自動車業界のマーケティングやイベント運営など多方面で活躍。2013年、『Octane』日本版を発行。現在は株式会社CCCカーライフラボ代表取締役。カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社ライフスタイル創造本部カーライフ研究所所長も兼任。