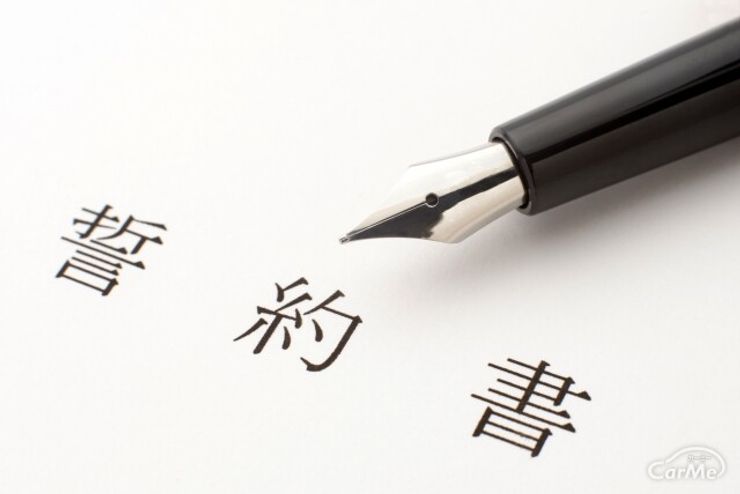車の共同購入とは?仕組みとメリット・デメリット、手続きやリスク対策までやさしく解説
更新日:2025.08.12

※この記事には広告が含まれます
車を買いたいけれど、購入費用や維持費の高さに悩んでいませんか?
車の共同購入は、そんな悩みを解決できる選択肢の一つです。友人や家族と一台の車をお金を出し合って共同で所有すれば、経済的負担を大きく減らすことができます。ただ、「本当にうまくいくの?」「トラブルにならない?」と心配になりますよね。
この記事では、初心者の方にもわかるように、車の共同購入の仕組み、メリット・デメリット、手続きの流れやリスク対策まで丁寧に解説します。共同購入を検討している方が安心して一歩を踏み出せるよう、よくある疑問にもQ&A形式でお答えします。それでは一緒に見ていきましょう。
車の共同購入は、そんな悩みを解決できる選択肢の一つです。友人や家族と一台の車をお金を出し合って共同で所有すれば、経済的負担を大きく減らすことができます。ただ、「本当にうまくいくの?」「トラブルにならない?」と心配になりますよね。
この記事では、初心者の方にもわかるように、車の共同購入の仕組み、メリット・デメリット、手続きの流れやリスク対策まで丁寧に解説します。共同購入を検討している方が安心して一歩を踏み出せるよう、よくある疑問にもQ&A形式でお答えします。それでは一緒に見ていきましょう。
車の共同購入とは?仕組みをやさしく解説
車の共同購入とは、複数人が資金を出し合って1台の車を共同で所有することです。一人では手が届かない車を友人同士で費用を分担して購入し、みんなでシェアして使うようなイメージです。
最近では「カーシェアリング」(車の共同利用)も一般化していますが、共同購入は、事業者が所有する車を単にレンタルやリースするのではなく、実際に自分たちが「所有者」となる点が大きな特徴です。
法律的には、自動車を複数人の名義で登録する「共有名義」も可能です。その場合、譲渡証明書や委任状などの登録書類には、共有者となる全員の氏名・住所を記載し、それぞれが実印を押印する必要があります。 また、税金の扱いも単独所有とは異なります。
例えば、毎年の自動車税(種別割)や軽自動車税(種別割)は、法律上、共有者全員が連帯して納税する義務を負います。ただし、実際の納税通知書は、行政上の便宜から、共有者の代表者(通常は車検証の所有者欄の筆頭者)1名にまとめて送付されるのが一般的です。
この点を「税金は筆頭者一人の責任」と誤解していると、万が一の滞納時に他の共有者へ請求が及ぶなど、後々のトラブルの原因にもなりかねません。
共同購入のスタイルは様々です。家族や信頼できる友人同士でプライベートに行うケースもあれば、過去には共同所有を仲介するプラットフォームサービスを利用し、見ず知らずの人同士がマッチングして共同オーナーになるというユニークな方法も登場した例があります。
こうしたサービスでは、事業者が間に入って車の管理やスケジュール調整を代行してくれるため、手軽に始められるというメリットが謳われています。(※ただし、2025年6月現在、日本国内で広く普及しているサービスは限定的です。)
最近では「カーシェアリング」(車の共同利用)も一般化していますが、共同購入は、事業者が所有する車を単にレンタルやリースするのではなく、実際に自分たちが「所有者」となる点が大きな特徴です。
法律的には、自動車を複数人の名義で登録する「共有名義」も可能です。その場合、譲渡証明書や委任状などの登録書類には、共有者となる全員の氏名・住所を記載し、それぞれが実印を押印する必要があります。 また、税金の扱いも単独所有とは異なります。
例えば、毎年の自動車税(種別割)や軽自動車税(種別割)は、法律上、共有者全員が連帯して納税する義務を負います。ただし、実際の納税通知書は、行政上の便宜から、共有者の代表者(通常は車検証の所有者欄の筆頭者)1名にまとめて送付されるのが一般的です。
この点を「税金は筆頭者一人の責任」と誤解していると、万が一の滞納時に他の共有者へ請求が及ぶなど、後々のトラブルの原因にもなりかねません。
共同購入のスタイルは様々です。家族や信頼できる友人同士でプライベートに行うケースもあれば、過去には共同所有を仲介するプラットフォームサービスを利用し、見ず知らずの人同士がマッチングして共同オーナーになるというユニークな方法も登場した例があります。
こうしたサービスでは、事業者が間に入って車の管理やスケジュール調整を代行してくれるため、手軽に始められるというメリットが謳われています。(※ただし、2025年6月現在、日本国内で広く普及しているサービスは限定的です。)
車の共同購入メリット3選|コスト削減から憧れ実現まで
購入費・維持費を大幅カット
車の共同購入における最大のメリットは、経済的な負担を軽減できる点です。車両本体の購入費用はもちろん、毎年の自動車税(種別割)や任意保険料、駐車場代、車検費用といった維持費を複数人で分担できるため、一人あたりのコストを大幅に減らすことができます。
例えば、高額な車でも数人で共同出資すれば、各自の負担はぐっと現実的な金額になります。
例えば、高額な車でも数人で共同出資すれば、各自の負担はぐっと現実的な金額になります。
手が届かなかった高級車にも乗れる
購入費用を分担できるため、一人では予算的に難しかった高級車や特殊なキャンピングカー、最新のEV(電気自動車)などに乗る夢を実現できるチャンスが生まれます。
過去には、月額数万円という比較的手頃な負担でポルシェなどの高級車を共同所有できる仲介サービスも登場しましたが、現在、国内で広く利用できる同様のサービスは非常に限定的です。しかし、個人間で信頼できるグループを作れば、憧れの車を所有するという選択肢がより身近になるでしょう。
過去には、月額数万円という比較的手頃な負担でポルシェなどの高級車を共同所有できる仲介サービスも登場しましたが、現在、国内で広く利用できる同様のサービスは非常に限定的です。しかし、個人間で信頼できるグループを作れば、憧れの車を所有するという選択肢がより身近になるでしょう。
週末しか乗らない人に最適な効率運用
「車は週末や長期休暇にしか使わない」というライフスタイルの人同士でグループを組めば、一台の車を無駄なくシェアすることで、非常に効率的に車を運用できます。駐車場所の確保や定期的なメンテナンスといった車の所有に伴う手間や負担もみんなで分散できるため、一人で所有するよりも気軽に、かつライフスタイルに合わせて柔軟にカーライフを楽しむことが可能です。
車の共同購入デメリット&注意点|利用制限や手続き負担をチェック
予約が被ると乗りたい日に使えない
複数人で一台の車を共有する以上、利用したい日が他の人と重なってしまう可能性があります。特に週末やゴールデンウィーク、お盆、年末年始などの連休期間は予約が集中し、乗りたい日に使えないという事態も起こり得ます。
あらかじめ利用スケジュールの調整方法に関する明確なルールを決めておかないと、不満やトラブルの原因になります。
あらかじめ利用スケジュールの調整方法に関する明確なルールを決めておかないと、不満やトラブルの原因になります。
お金・ルールの食い違いでトラブル発生リスク
「車内での喫煙や飲食の可否」「ペットの同乗ルール」「ガソリンの給油タイミング」「事故や故障時の修理費の負担割合」など、お金の価値観や車の使い方に関する考え方の違いから、共同オーナー間で衝突が起こるかもしれません。
また、共同オーナーの一人が支払いを滞らせたり、人間関係が悪化したりすると、車の利用そのものを巡って深刻なトラブルに発展する恐れもあります。
また、共同オーナーの一人が支払いを滞らせたり、人間関係が悪化したりすると、車の利用そのものを巡って深刻なトラブルに発展する恐れもあります。
名義変更や売却時の手続きが複雑
複数人で所有(共有名義)する分、単独所有に比べて各種手続きが煩雑になります。例えば、車を売却して共有関係を解消するには、民法上、共有者全員の合意が必要となり、必要書類にも全員分の署名・押印が求められます。
このように、一人の意向だけでは自由に車を処分できないという制約があります。
このように、一人の意向だけでは自由に車を処分できないという制約があります。
車を共同購入する手順ガイド|名義・保険・契約書まで
実際に車を共同購入する際の大まかな流れと、法的な手続きのポイントを説明します。
まず、何よりも信頼できる相手とグループを組み、購入する車種や予算、利用頻度、費用分担の割合などを、全員が納得するまで十分に話し合っておくことが重要です。購入資金は、現金で出し合うのが最もシンプルですが、自動車ローンを利用する場合は、一般的に代表者1名が契約者となり、金融機関の審査によっては他の共同購入者が連帯保証人になるといった形が考えられます。
車の登録は、希望すれば共有者全員の「共有名義」にすることができます。この場合、自動車税(種別割)などの税金は、法律上、共有者全員が連帯して納税する義務を負います。
ただし、納税通知書は行政上の便宜から、代表者である筆頭者1名に送付されるのが一般的です。 また、車庫証明(自動車保管場所証明書)は、1台の車につき1か所の主たる保管場所でしか取得できません。
任意保険は、共有者のうちの1名を主たる使用者(記名被保険者)として契約するのが一般的です。その際、最も重要なのは、補償される運転者の範囲を、共同購入者全員が含まれるように正しく設定することです。例えば、友人同士で共同購入する場合は、運転者を限定しないプラン(限定なし)を選ぶ必要があります。
また、運転者の年齢条件も、運転する可能性のある人の中で最も若い人に合わせて設定しないと、万が一の際に補償が受けられなくなるため注意が必要です。保険料にも大きく影響する部分なので、保険会社や代理店とよく相談して決定しましょう。
そして、共同購入で最も重要なのが、事前に利用ルールを細かく決めて「契約書」を交わすことです。利用スケジュールの管理方法(予約システムの導入など)、ガソリン代や高速道路料金の精算ルール、車内での禁止事項(喫煙など)、洗車や定期点検の分担、事故や故障時の費用負担の割合など、あらゆるケースを想定して全員で合意し、必ず書面に残しておきましょう。
共同所有の期間や、誰かが途中で抜けたいと希望した場合の条件(他のメンバーによる持分の買い取り方法や、車両を売却して清算する手順など)も事前に決めて、契約書に明記しておくことで、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。
まず、何よりも信頼できる相手とグループを組み、購入する車種や予算、利用頻度、費用分担の割合などを、全員が納得するまで十分に話し合っておくことが重要です。購入資金は、現金で出し合うのが最もシンプルですが、自動車ローンを利用する場合は、一般的に代表者1名が契約者となり、金融機関の審査によっては他の共同購入者が連帯保証人になるといった形が考えられます。
車の登録は、希望すれば共有者全員の「共有名義」にすることができます。この場合、自動車税(種別割)などの税金は、法律上、共有者全員が連帯して納税する義務を負います。
ただし、納税通知書は行政上の便宜から、代表者である筆頭者1名に送付されるのが一般的です。 また、車庫証明(自動車保管場所証明書)は、1台の車につき1か所の主たる保管場所でしか取得できません。
任意保険は、共有者のうちの1名を主たる使用者(記名被保険者)として契約するのが一般的です。その際、最も重要なのは、補償される運転者の範囲を、共同購入者全員が含まれるように正しく設定することです。例えば、友人同士で共同購入する場合は、運転者を限定しないプラン(限定なし)を選ぶ必要があります。
また、運転者の年齢条件も、運転する可能性のある人の中で最も若い人に合わせて設定しないと、万が一の際に補償が受けられなくなるため注意が必要です。保険料にも大きく影響する部分なので、保険会社や代理店とよく相談して決定しましょう。
そして、共同購入で最も重要なのが、事前に利用ルールを細かく決めて「契約書」を交わすことです。利用スケジュールの管理方法(予約システムの導入など)、ガソリン代や高速道路料金の精算ルール、車内での禁止事項(喫煙など)、洗車や定期点検の分担、事故や故障時の費用負担の割合など、あらゆるケースを想定して全員で合意し、必ず書面に残しておきましょう。
共同所有の期間や、誰かが途中で抜けたいと希望した場合の条件(他のメンバーによる持分の買い取り方法や、車両を売却して清算する手順など)も事前に決めて、契約書に明記しておくことで、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。
共同購入で失敗しない!リスク管理とトラブル防止策
共同購入で特に気を付けたいのは、人間関係とお金のトラブルです。親しい間柄であっても、車の使い方や出費のことで意見が食い違う可能性があります。
本項で解説したように、事前に契約書を交わして細かなルールを明確にしておくことで、多くのトラブルは防ぐことができます。
また、一人が支払い不能になった場合に備えて、あらかじめグループで共通の積立金を用意しておいたり、会計アプリなどを使って日頃から収支を透明化し、共有したりしておくと安心です。万一の事態を想定した取り決めを怠らないようにしましょう。
本項で解説したように、事前に契約書を交わして細かなルールを明確にしておくことで、多くのトラブルは防ぐことができます。
また、一人が支払い不能になった場合に備えて、あらかじめグループで共通の積立金を用意しておいたり、会計アプリなどを使って日頃から収支を透明化し、共有したりしておくと安心です。万一の事態を想定した取り決めを怠らないようにしましょう。
車の共同購入Q&Aまとめ|よくある疑問を一気に解決
Q1. 共有名義の仕組みと税金は?
A. 希望すれば、車検証の所有者欄に複数人の名前を記載する「共有名義」で登録することが可能です。手続きには、通常の譲渡証明書や委任状に共有者全員の氏名・住所を記載し、それぞれが実印を押印する必要があります。 税金については特に注意が必要です。毎年の自動車税(種別割)などは、法律上、共有者全員が連帯して納税する義務を負います。
ただし、実際の納税通知書は、行政上の便宜から、共有者の代表者(通常は車検証の筆頭者)1名にまとめて送付されるのが一般的です。もし筆頭者が納税を怠った場合、他の共有者に支払い義務が及ぶため、事前に納税のルールを明確に決めておくことが非常に重要です。
Q2. 任意保険はどう加入すればいい?
A. 任意保険は、共有者のうち1名を主たる使用者(記名被保険者)として契約するのが一般的です。その上で、実際に運転する可能性のある人全員が補償の対象となるように、運転者の範囲(例:運転者限定をつけない「限定なし」など)や、最も若い人に合わせた年齢条件を正しく設定する必要があります。
単に「運転者限定を外す」だけでは、年齢条件によっては補償されないケースもあるため注意が必要です。保険料にも大きく関わる部分なので、契約前に保険会社や代理店に共同所有である旨を伝え、最適なプランをよく相談して決めるようにしましょう。全員が別々に保険に加入する必要はありません。
Q3. 途中で抜けたいときの清算方法は?
A. まずは、事前に作成した契約書の定めに従うのが大原則です。一般的には、残りのオーナーがその人の持分(出資比率に応じた権利)を買い取るか、あるいは全員の合意のもとで車を売却し、売却額を持分に応じて分配して精算する方法があります。トラブルを未然に防ぐため、共同購入を開始する際に、何をもって共同所有を解消とするか、そして解消時の具体的な清算方法を明確に決めておくことが不可欠です。
Q4. 知らない人と組むならサービス利用が安全?
A. 個人間で見ず知らずの人と共同購入を行うのは、金銭トラブルや利用ルールの不徹底、人間関係の悪化など、非常に高いリスクを伴うため、基本的にはおすすめできません。信頼関係の構築が何よりも重要です。
どうしても個人間以外で相手を探したい場合は、共同所有を仲介するサービスの利用も考えられますが、前述の通り、現在国内で広く利用できるサービスは非常に限定的です。 もしそのようなサービスを利用する場合は、運営会社の信頼性や契約内容、トラブル発生時のサポート体制などを慎重に確認する必要があります。
A. 希望すれば、車検証の所有者欄に複数人の名前を記載する「共有名義」で登録することが可能です。手続きには、通常の譲渡証明書や委任状に共有者全員の氏名・住所を記載し、それぞれが実印を押印する必要があります。 税金については特に注意が必要です。毎年の自動車税(種別割)などは、法律上、共有者全員が連帯して納税する義務を負います。
ただし、実際の納税通知書は、行政上の便宜から、共有者の代表者(通常は車検証の筆頭者)1名にまとめて送付されるのが一般的です。もし筆頭者が納税を怠った場合、他の共有者に支払い義務が及ぶため、事前に納税のルールを明確に決めておくことが非常に重要です。
Q2. 任意保険はどう加入すればいい?
A. 任意保険は、共有者のうち1名を主たる使用者(記名被保険者)として契約するのが一般的です。その上で、実際に運転する可能性のある人全員が補償の対象となるように、運転者の範囲(例:運転者限定をつけない「限定なし」など)や、最も若い人に合わせた年齢条件を正しく設定する必要があります。
単に「運転者限定を外す」だけでは、年齢条件によっては補償されないケースもあるため注意が必要です。保険料にも大きく関わる部分なので、契約前に保険会社や代理店に共同所有である旨を伝え、最適なプランをよく相談して決めるようにしましょう。全員が別々に保険に加入する必要はありません。
Q3. 途中で抜けたいときの清算方法は?
A. まずは、事前に作成した契約書の定めに従うのが大原則です。一般的には、残りのオーナーがその人の持分(出資比率に応じた権利)を買い取るか、あるいは全員の合意のもとで車を売却し、売却額を持分に応じて分配して精算する方法があります。トラブルを未然に防ぐため、共同購入を開始する際に、何をもって共同所有を解消とするか、そして解消時の具体的な清算方法を明確に決めておくことが不可欠です。
Q4. 知らない人と組むならサービス利用が安全?
A. 個人間で見ず知らずの人と共同購入を行うのは、金銭トラブルや利用ルールの不徹底、人間関係の悪化など、非常に高いリスクを伴うため、基本的にはおすすめできません。信頼関係の構築が何よりも重要です。
どうしても個人間以外で相手を探したい場合は、共同所有を仲介するサービスの利用も考えられますが、前述の通り、現在国内で広く利用できるサービスは非常に限定的です。 もしそのようなサービスを利用する場合は、運営会社の信頼性や契約内容、トラブル発生時のサポート体制などを慎重に確認する必要があります。
まとめ
車の共同購入は、費用を抑えながらマイカーのある生活を実現できる魅力的な方法です。特に、普段あまり車を使わない人同士や、個人では手の届きにくい憧れの車に乗ってみたい場合には、有力な選択肢となるでしょう。
メリットが多い一方で、共同購入には入念な話し合いと強固な信頼関係、そして万一の事態に備えるリスク管理が欠かせません。
大切なのは、事前に利用や費用負担、トラブル時の対応に関するルールを細かく決めて全員合意の上で書面(契約書)に残しておくことと、価値観や金銭感覚が近い、信頼できる相手と組むことです。 準備を怠らず冷静に取り組めば、きっと快適な共同カーライフを送れるはずですよ。
最初は不安もあるかもしれませんが、しっかり対策をしておけば共同購入は決して難しいことばかりではありません。
この記事が皆さんの疑問解消に役立ち、新しい一歩を踏み出す後押しになれば幸いです。経済的な負担を減らしつつ、ぜひ充実したカーライフを楽しんでくださいね。
メリットが多い一方で、共同購入には入念な話し合いと強固な信頼関係、そして万一の事態に備えるリスク管理が欠かせません。
大切なのは、事前に利用や費用負担、トラブル時の対応に関するルールを細かく決めて全員合意の上で書面(契約書)に残しておくことと、価値観や金銭感覚が近い、信頼できる相手と組むことです。 準備を怠らず冷静に取り組めば、きっと快適な共同カーライフを送れるはずですよ。
最初は不安もあるかもしれませんが、しっかり対策をしておけば共同購入は決して難しいことばかりではありません。
この記事が皆さんの疑問解消に役立ち、新しい一歩を踏み出す後押しになれば幸いです。経済的な負担を減らしつつ、ぜひ充実したカーライフを楽しんでくださいね。