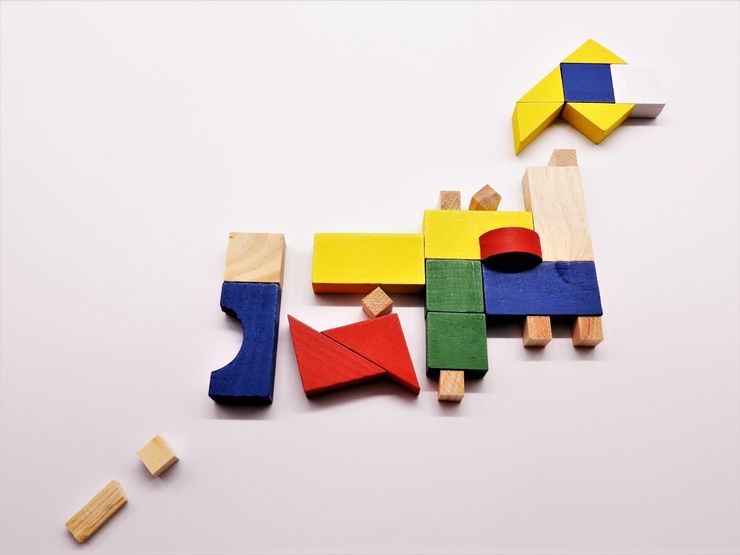和服で運転すると違反になる?交通ルールと安全運転のポイント
更新日:2025.08.12

※この記事には広告が含まれます
2018年、福井県で僧侶が僧衣(お坊さんの衣装)を着て車を運転していた際に「運転に支障を及ぼすおそれがある」として交通違反切符を切られたというニュースが話題になりました。
こうした出来事もあり、「振袖や紋付き袴など和服で運転したら違反になるの?」と心配する方もいるでしょう。結論からいえば、和服で運転しただけで直ちに法律違反になるわけではありません。しかし、状況によっては交通違反とみなされるケースもあるため注意が必要です。
こうした出来事もあり、「振袖や紋付き袴など和服で運転したら違反になるの?」と心配する方もいるでしょう。結論からいえば、和服で運転しただけで直ちに法律違反になるわけではありません。しかし、状況によっては交通違反とみなされるケースもあるため注意が必要です。
着物や振袖で運転しても違反にならない?
まず、国の法律である道路交通法には服装や履物に関する明確な規定がなく、着物で車を運転してもそれだけで違反に問われることはありません。
ただし、各都道府県の公安委員会が定める道路交通法施行細則(地域の条例)で服装・履物に関する細則が設けられている場合があります。
実際、福井県の僧衣の件ではこのルールに基づき「運転操作に支障のおそれがある衣服」と判断され、違反として切符を切られました。つまり、和服でも運転操作の妨げになる状態であれば取り締まりの対象になり得るのです。
要するに、和服で運転すること自体は直ちに違法ではないものの、着物の袖や裾がハンドルやペダルに引っかかるなど「運転に支障を及ぼす恐れ」がある場合には違反と見なされる可能性があるということです。
振袖や袴だからといって必ず違反になるわけではありませんが、運転前に自分の服装が安全な運転操作を妨げないか十分確認する必要があります。
ただし、各都道府県の公安委員会が定める道路交通法施行細則(地域の条例)で服装・履物に関する細則が設けられている場合があります。
実際、福井県の僧衣の件ではこのルールに基づき「運転操作に支障のおそれがある衣服」と判断され、違反として切符を切られました。つまり、和服でも運転操作の妨げになる状態であれば取り締まりの対象になり得るのです。
要するに、和服で運転すること自体は直ちに違法ではないものの、着物の袖や裾がハンドルやペダルに引っかかるなど「運転に支障を及ぼす恐れ」がある場合には違反と見なされる可能性があるということです。
振袖や袴だからといって必ず違反になるわけではありませんが、運転前に自分の服装が安全な運転操作を妨げないか十分確認する必要があります。
和服で運転する際に注意すべきポイント
袖は「たすき掛け」で固定する
袖の長い着物を着る場合は、運転前に袖をたくし上げてひも等で留め(たすき掛け)、ハンドル操作の邪魔にならないようにします。
運転中も袖が落ちてこないか、ときどき目視で確認するとさらに安心です。
運転中も袖が落ちてこないか、ときどき目視で確認するとさらに安心です。
裾を踏まない工夫をする
着物や袴の裾が長いと、ブレーキやアクセルの操作中に足に絡む恐れがあります。
和服の下にズボンやもんぺを履いて裾を押さえる、クリップで裾を留める等、裾さばきを良くする工夫をしましょう。乗り降りの際も裾を踏まないよう、ドア周りで裾が引っ掛からないか注意してください。
和服の下にズボンやもんぺを履いて裾を押さえる、クリップで裾を留める等、裾さばきを良くする工夫をしましょう。乗り降りの際も裾を踏まないよう、ドア周りで裾が引っ掛からないか注意してください。
履物は運転しやすい靴に履き替える
下駄や草履など和装履物は踵が固定されず脱げやすいため、ペダル操作には不向きです。
運転時はスニーカーなどかかとまでホールドできる靴に履き替えましょう(サンダルやハイヒールも避けるのが無難です)。あらかじめ運転用の履き慣れた靴を車内に用意しておくと、急な移動もスムーズに対応できます。
運転時はスニーカーなどかかとまでホールドできる靴に履き替えましょう(サンダルやハイヒールも避けるのが無難です)。あらかじめ運転用の履き慣れた靴を車内に用意しておくと、急な移動もスムーズに対応できます。
以上の対策を取れば、和服でもかなり運転はしやすくなります。それでも長距離や高速道路の運転など不安がある場合は、無理をせず公共交通機関を利用するか家族に送迎をお願いすることも検討しましょう。
道路交通法との関係とは?
「和服で運転すると違反になる場合がある」というのは、道路交通法そのものではなく各都道府県の細則によるものです。
道路交通法第71条6号で、各都道府県の公安委員会が定めた事項を運転者の遵守事項とすると規定されており、それに基づき地域ごとに服装や履物に関するルールが存在します。
その内容は地域によって様々ですが、運転時の服装規定を設けている県は全国で15県程度あります。例えば岩手県では「衣服の袖・裾によって運転の障害となるような和服等」を着て運転することを禁止し、逆に袖や裾をたくし上げ、ズボンやもんぺを履けば対象外と明記しています。
一方、ほとんどの県では「運転の障害となるような身なり」など抽象的な表現に留まっており、実際の運用は警察官の判断に委ねられているのが現状です。地域によって規定が異なるため、和服で運転する際は走行する地域の細則を確認することが大切です。
道路交通法第71条6号で、各都道府県の公安委員会が定めた事項を運転者の遵守事項とすると規定されており、それに基づき地域ごとに服装や履物に関するルールが存在します。
その内容は地域によって様々ですが、運転時の服装規定を設けている県は全国で15県程度あります。例えば岩手県では「衣服の袖・裾によって運転の障害となるような和服等」を着て運転することを禁止し、逆に袖や裾をたくし上げ、ズボンやもんぺを履けば対象外と明記しています。
一方、ほとんどの県では「運転の障害となるような身なり」など抽象的な表現に留まっており、実際の運用は警察官の判断に委ねられているのが現状です。地域によって規定が異なるため、和服で運転する際は走行する地域の細則を確認することが大切です。
警察に止められるケースがある?
和服で運転していて警察に止められるケースは実際に起こり得ます。
前述の福井県の例では、実際に青切符(反則金6000円)が交付されています。
警察官が「危険な状態だ」と判断すれば、条例の有無にかかわらず違反として処理される可能性があります。
特に安全運転義務違反(道路交通法第70条)が適用されると、違反点数2点・普通車で反則金9000円というペナルティとなるため注意が必要です。
もちろん、きちんと安全に運転できていれば必ずしも取り締まりを受けるわけではありません。しかし万一を考えれば、和服で運転する際は警察に注意されるリスクもあることを念頭に置き、安全運転を徹底すべきでしょう。
前述の福井県の例では、実際に青切符(反則金6000円)が交付されています。
警察官が「危険な状態だ」と判断すれば、条例の有無にかかわらず違反として処理される可能性があります。
特に安全運転義務違反(道路交通法第70条)が適用されると、違反点数2点・普通車で反則金9000円というペナルティとなるため注意が必要です。
もちろん、きちんと安全に運転できていれば必ずしも取り締まりを受けるわけではありません。しかし万一を考えれば、和服で運転する際は警察に注意されるリスクもあることを念頭に置き、安全運転を徹底すべきでしょう。
和服での運転が安全なシーンと危険なシーン
和服であっても比較的安全に運転できる場面と、和服だと特に危険が増す場面があります。
例えば、袖や裾をきちんと処理し、短距離かつ低速で走行するような状況であれば、和服でも大きな支障なく運転できるでしょう。男性の着物など袖丈の短い和服や、普段から運転に慣れている人が慎重に運転する場合も、リスクは抑えられます。
一方で、振袖や袴を着たまま高速道路を走るような場面では危険度が増します。長い袖や裾がハンドル操作やペダル操作の妨げとなり、咄嗟の対応ができなくなる恐れが高いからです。
急ブレーキや急ハンドルが必要な場面で衣服が動きを制限すると重大な事故につながりかねません。また、運転に不慣れな人が和服で運転するのも注意力が散漫になりやすく危険です。
実際、着物業界の専門家も「着物を着ている時は運転を控えるべき」と指摘しており、安全のためには和服での運転は可能な限り避けたほうが良いでしょう。
例えば、袖や裾をきちんと処理し、短距離かつ低速で走行するような状況であれば、和服でも大きな支障なく運転できるでしょう。男性の着物など袖丈の短い和服や、普段から運転に慣れている人が慎重に運転する場合も、リスクは抑えられます。
一方で、振袖や袴を着たまま高速道路を走るような場面では危険度が増します。長い袖や裾がハンドル操作やペダル操作の妨げとなり、咄嗟の対応ができなくなる恐れが高いからです。
急ブレーキや急ハンドルが必要な場面で衣服が動きを制限すると重大な事故につながりかねません。また、運転に不慣れな人が和服で運転するのも注意力が散漫になりやすく危険です。
実際、着物業界の専門家も「着物を着ている時は運転を控えるべき」と指摘しており、安全のためには和服での運転は可能な限り避けたほうが良いでしょう。
よくある質問(FAQ)
Q: 振袖で運転すると捕まりますか?
A: 振袖を着ただけで直ちに違反になることはありません。
ただ、袖がハンドルに引っかかるなど運転操作に支障が出た場合は違反に問われる可能性があります。
ただ、袖がハンドルに引っかかるなど運転操作に支障が出た場合は違反に問われる可能性があります。
Q: 和服での運転を禁止している地域はどこですか?
A: 道路交通法で全国一律に禁止されているわけではありませんが、都道府県ごとに服装に関する規定を設けている地域があります。
例えば岩手県や栃木県では和服に言及した細則があり、秋田県や愛知県、滋賀県などにも「運転操作の妨げとなる服装をしないこと」という規定があります。
居住地だけでなく、旅行先でも規制がある場合がありますので、運転前に各地域のルールを確認しましょう。
例えば岩手県や栃木県では和服に言及した細則があり、秋田県や愛知県、滋賀県などにも「運転操作の妨げとなる服装をしないこと」という規定があります。
居住地だけでなく、旅行先でも規制がある場合がありますので、運転前に各地域のルールを確認しましょう。
Q: サンダルや草履で車を運転してもいいのでしょうか?
A: サンダルや草履での運転は避けるべきです。
多くの県で「下駄やサンダル等、運転操作に支障のある履物」での運転を禁止する細則があります。
条例がない場合でも、踵が固定されない履物はブレーキ操作中に脱げて事故を招く恐れがあり、安全運転義務違反に問われる可能性があります。運転時はスニーカーなど安全な靴に履き替えましょう。
多くの県で「下駄やサンダル等、運転操作に支障のある履物」での運転を禁止する細則があります。
条例がない場合でも、踵が固定されない履物はブレーキ操作中に脱げて事故を招く恐れがあり、安全運転義務違反に問われる可能性があります。運転時はスニーカーなど安全な靴に履き替えましょう。
Q: 浴衣で運転するのは大丈夫ですか?
A: 浴衣も和服の一種ですから基本的な注意点は同じです。
袖は振袖ほど長くありませんが、裾が足に巻き付く恐れがありペダル操作の妨げになり得ます。
違反になるかどうかは状況によりますが、袖や裾が邪魔にならないよう帯に挟むなど工夫し、履物も含め安全な状態で運転してください。
袖は振袖ほど長くありませんが、裾が足に巻き付く恐れがありペダル操作の妨げになり得ます。
違反になるかどうかは状況によりますが、袖や裾が邪魔にならないよう帯に挟むなど工夫し、履物も含め安全な状態で運転してください。
Q: 万が一警察に止められたらどうすればいいですか?
A: 落ち着いて指示に従いましょう。
違反切符を切られた場合、内容に不服があれば後日正式に意見を述べる場もありますが、現場では感情的にならず安全運転への改善点を受け止めることが肝心です。
和服で運転していた事情があれば丁寧に説明してください。最初からトラブルを避けるには、やはり和服での運転はできるだけ控えるのが無難です。
違反切符を切られた場合、内容に不服があれば後日正式に意見を述べる場もありますが、現場では感情的にならず安全運転への改善点を受け止めることが肝心です。
和服で運転していた事情があれば丁寧に説明してください。最初からトラブルを避けるには、やはり和服での運転はできるだけ控えるのが無難です。
安全運転のためにはリスクを高める服装や履物は避けるのが望ましいとされています。和服でハンドルを握る際は十分に注意を払い、いつも以上に「安全第一」で運転しましょう。
まとめ
和服で運転する行為自体は道路交通法に違反しませんが、各都道府県の道路交通法施行細則では「運転操作の妨げとなる服装・履物」を禁じている場合があります。
袖や裾がハンドルやペダルに絡むなど「運転に支障を及ぼすおそれ」があると警察官に判断されれば、違反切符を切られる可能性があります。
運転前には袖をたすき掛けで固定し、裾を踏まない工夫をし、下駄や草履ではなくかかとまでホールドできる靴に履き替えることが大切です。
また、長距離や高速道路の運転が必要な場合は公共交通機関や送迎を検討し、走行する地域の細則も事前に確認しましょう。安全運転の基本は「操作を妨げない服装と履物」を選ぶことに尽きます。
袖や裾がハンドルやペダルに絡むなど「運転に支障を及ぼすおそれ」があると警察官に判断されれば、違反切符を切られる可能性があります。
運転前には袖をたすき掛けで固定し、裾を踏まない工夫をし、下駄や草履ではなくかかとまでホールドできる靴に履き替えることが大切です。
また、長距離や高速道路の運転が必要な場合は公共交通機関や送迎を検討し、走行する地域の細則も事前に確認しましょう。安全運転の基本は「操作を妨げない服装と履物」を選ぶことに尽きます。