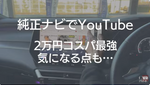ネグローニ・スパイダー物語
更新日:2024.09.09

※この記事には広告が含まれます
自動車というのは道具である。それに異論はない。けれど、これほどまでに人の暮らしの中で人の心にハッキリと作用を及ぼすエモーショナルな道具は他にないと思うし、もっと言うならこれほどまでに人生というやつに密着し、人が紡いでゆく物語を豊かに彩ってくれる道具というのもそう多くはないんじゃないかと思う。
text:嶋田智之 photo:長谷川徹、菅原康太 [aheadアーカイブス vol.130 2013年9月号]
text:嶋田智之 photo:長谷川徹、菅原康太 [aheadアーカイブス vol.130 2013年9月号]
ネグローニ・スパイダー物語
何せ関わる人のそこから先の生き様を、時としてガラッと変えてしまうことだって少なからずあるのだ。しかもそれらの物語は、大抵の場合はアンハッピーな結末を見せることなく、聞き手の心をジンワリと温めてくれるものである。「クルマって、いったい何なんだろう」なんて不思議な気分になる瞬間だ。
今回はそんなお話をひとつ皆さんに御紹介したい。とあるドライビングシューズのブランドにまつわるお話であり、それを生み出し、世に送り出し、支え、これからも進化させ続けていく、ひとつの家族のお話だ。そしてその真ん中に佇んでいるのが、1台のクルマなのである。
今回はそんなお話をひとつ皆さんに御紹介したい。とあるドライビングシューズのブランドにまつわるお話であり、それを生み出し、世に送り出し、支え、これからも進化させ続けていく、ひとつの家族のお話だ。そしてその真ん中に佇んでいるのが、1台のクルマなのである。
〝カーキチ〟な靴屋のせがれ
「ネグローニ」というブランドのドライビングシューズを御存知だろうか。─日本人が日本人のために作るイタリアンテイストのドライビングシューズ─として、今や数少なくなった靴職人さんの手でひとつひとつ、丁寧にハンドメイドされている。
甲高幅広ぎみの日本人の足型に合わせた設計、ファッショナブルだけど飽きのこないデザイン、上質な革づかい、そして何より運転のしやすさは当然のことながら、従来のドライビングシューズと違い、街歩きがしやすい。プロのレーシングドライバーや自動車メディアの関係者が日常的に愛用することからも、出来栄えの素晴らしさの一端を察していただけるだろう。
そのブランドを立ち上げたのは、東京の南千住という下町にあるシューズメーカー、「マルミツ」の当主である宮部修一さんだ。父上がはじめた靴のOEMメーカーを受け継ぎ、並行して〝ネグローニ〟というオリジナルのブランドをスタートさせた。1954年生まれの修一さんは、ちゃきちゃきの下町っ子として育った。話し言葉にも、微妙にべらんめえ口調が混じっていて歯切れがいい。
「ぷらっぷらしててもしょうがねえから」と父上の会社に入った修一さんだが、当時、会社は靴の卸業者から靴の製造業者へと転身を図るタイミング。それまで未知だった〝靴を作る〟ということについては、それこそ靴の構造から、素材から、製造理論から、職人さん達との付き合い方から、流通から、とゼロからのスタート。
「教えてもらえば誰だってできるってもんじゃない。職人のほとんどが〝見て覚えろ〟っていう時代でもあったんで、自分で工場に入って手を動かしてもみたんですけど、いい靴ができなくってね」と振り返る。
この頃に身についたことは、試行錯誤して思いついたものはやってみるという姿勢。これが後に活きることになる。そんな中、出張と勉強を兼ねて渡ったイタリアで、修一さんは1台のクルマに出逢って衝撃を受けた。
石畳に佇む、黒の「フェラーリ・デイトナ・スパイダー」である。1978年か79年か、その辺りだったという。「本気で欲しいって思いましたね」。修一さんは若い頃からのクルマ好きで、それまでも「フェアレディZ」に乗ったりなどしていたが、この出来事がまた、少しばかり人生を変えた。
「黒のフェラーリが欲しくて欲しくて。給料も全部貯めて、穴の開いた靴下履いて、3年後ぐらいになってやっと買ったんですよ。308のGT4。金があって買ったわけじゃないから、個人輸入してね。できることは全部自分でやってさ。乗ってるときだって壊したら金がかかるって、もうおっかなビックリでしたよ」
ちょうどその頃、修一さんにはおつきあいしている女性がいた。今では「マルミツ」の常務として会社を切り盛りしている、奥様の明美さんだ。「迎えに行くよってフェラーリで向かってて、途中でクラッチワイヤーが切れて立ち往生したことがあったんですよ。今みたいに携帯電話もなかった時代だし、待ち合わせは外だから公衆電話も使えない。5時間も待たせたからさすがにいないだろうなと思って待ち合わせ場所に行ったら、待ってたんですよ。いやいや、そんなこともありましたね」
ちゃきちゃきらしく自分のクチからは言わないが、その出来事が結婚を考える大きな原動力になったことは想像に難くない。そして1984年、現在は跡継ぎとして奮闘している修平さんを授かることになる。
その頃の「マルミツ」はOEMメーカーとして成長を遂げ、時代の後押しもあって徐々に生産も拡大。1990年代後半まで右肩上がりで生産量を拡大していく。全てが順調に思えた。「上場企業でもないのに先代がベンツ、私がAMGなんて贅沢をしてましてね。息子が成長して、さすがにフェラーリじゃ無理になって乗り換えたんです」
ところがそんな折、番頭役だった先代の常務が亡くなり、その数ヵ月後には先代の社長までもが突如倒れて亡くなってしまう。さらに数ヵ月後には最大の発注元が倒産した。そのあおりで半年近くも工場をほぼストップしなければならないという事態に追い込まれる。ミレニアムに湧く2000年を前に、最大の危機が訪れたのだ。
甲高幅広ぎみの日本人の足型に合わせた設計、ファッショナブルだけど飽きのこないデザイン、上質な革づかい、そして何より運転のしやすさは当然のことながら、従来のドライビングシューズと違い、街歩きがしやすい。プロのレーシングドライバーや自動車メディアの関係者が日常的に愛用することからも、出来栄えの素晴らしさの一端を察していただけるだろう。
そのブランドを立ち上げたのは、東京の南千住という下町にあるシューズメーカー、「マルミツ」の当主である宮部修一さんだ。父上がはじめた靴のOEMメーカーを受け継ぎ、並行して〝ネグローニ〟というオリジナルのブランドをスタートさせた。1954年生まれの修一さんは、ちゃきちゃきの下町っ子として育った。話し言葉にも、微妙にべらんめえ口調が混じっていて歯切れがいい。
「ぷらっぷらしててもしょうがねえから」と父上の会社に入った修一さんだが、当時、会社は靴の卸業者から靴の製造業者へと転身を図るタイミング。それまで未知だった〝靴を作る〟ということについては、それこそ靴の構造から、素材から、製造理論から、職人さん達との付き合い方から、流通から、とゼロからのスタート。
「教えてもらえば誰だってできるってもんじゃない。職人のほとんどが〝見て覚えろ〟っていう時代でもあったんで、自分で工場に入って手を動かしてもみたんですけど、いい靴ができなくってね」と振り返る。
この頃に身についたことは、試行錯誤して思いついたものはやってみるという姿勢。これが後に活きることになる。そんな中、出張と勉強を兼ねて渡ったイタリアで、修一さんは1台のクルマに出逢って衝撃を受けた。
石畳に佇む、黒の「フェラーリ・デイトナ・スパイダー」である。1978年か79年か、その辺りだったという。「本気で欲しいって思いましたね」。修一さんは若い頃からのクルマ好きで、それまでも「フェアレディZ」に乗ったりなどしていたが、この出来事がまた、少しばかり人生を変えた。
「黒のフェラーリが欲しくて欲しくて。給料も全部貯めて、穴の開いた靴下履いて、3年後ぐらいになってやっと買ったんですよ。308のGT4。金があって買ったわけじゃないから、個人輸入してね。できることは全部自分でやってさ。乗ってるときだって壊したら金がかかるって、もうおっかなビックリでしたよ」
ちょうどその頃、修一さんにはおつきあいしている女性がいた。今では「マルミツ」の常務として会社を切り盛りしている、奥様の明美さんだ。「迎えに行くよってフェラーリで向かってて、途中でクラッチワイヤーが切れて立ち往生したことがあったんですよ。今みたいに携帯電話もなかった時代だし、待ち合わせは外だから公衆電話も使えない。5時間も待たせたからさすがにいないだろうなと思って待ち合わせ場所に行ったら、待ってたんですよ。いやいや、そんなこともありましたね」
ちゃきちゃきらしく自分のクチからは言わないが、その出来事が結婚を考える大きな原動力になったことは想像に難くない。そして1984年、現在は跡継ぎとして奮闘している修平さんを授かることになる。
その頃の「マルミツ」はOEMメーカーとして成長を遂げ、時代の後押しもあって徐々に生産も拡大。1990年代後半まで右肩上がりで生産量を拡大していく。全てが順調に思えた。「上場企業でもないのに先代がベンツ、私がAMGなんて贅沢をしてましてね。息子が成長して、さすがにフェラーリじゃ無理になって乗り換えたんです」
ところがそんな折、番頭役だった先代の常務が亡くなり、その数ヵ月後には先代の社長までもが突如倒れて亡くなってしまう。さらに数ヵ月後には最大の発注元が倒産した。そのあおりで半年近くも工場をほぼストップしなければならないという事態に追い込まれる。ミレニアムに湧く2000年を前に、最大の危機が訪れたのだ。
それを救ったのは、まずは先代の常務の仕事をほとんど引き継ぎなしで丸ごと担うことになった、新常務の明美さんだったという。修一さんは「ほとんど何も知らない状態でいきなりだったのに、私がいうのも変だけど、よくやってくれたと思いますよ」というが、まさしくその通り。
在庫量と工場の稼働スケジュール、材料の発注、取引先との打ち合わせ、そして営業と多岐にわたる業務を、学びながら即戦力として回していかなければならない状況だったのだ。そしてあるとき、大量受注に備えた見込み生産によって凄まじい量の在庫を抱えてることに疑問を感じ、それをなくすことを決意する。
「全くの素人だったので、業務や家事以外の時間には、ずっと本を読んで勉強したり考えたりしてましたね。大変だったような記憶はありますけど、でも……細かいことは忘れてしまいました。私、楽しいことしか覚えてないんですよ」明美さんはとても控えめなようで、御自身の功績や苦労話をとくとくと語ったりはしないけれど、その時の英断がなければ、発注元の倒産に引き摺られていただろうことは、容易に想像がつく。
そして従来の少品種大量生産だけに依存するのをヤメて、望まれたら1足からでもいいから作ろう、OEMだけではなくオリジナルブランドも立ち上げよう、と仕事をそれまでと違った軌道に乗せるべく動き始めたのだ。ところがその頃、修一さんは端から見たらとんでもないと言われそうなことを、いきなり思いついた。「色々あって気持ちの穴を埋めたかったようなところもあるんですけど、昔から好きだったイタリア車にまた乗りたくなってね。ちょうどそんなときにイタリアっぽさを前面に出した『カセルタ』っていうクルマを見つけて、これでも買ってみようかなって思って」
「カセルタ」というのは、トヨタの関連会社である「モデリスタ」が、ミドシップ2シーターの「MR-S」をベースに、イタリアンテイストなボディを被せて作り上げた限定販売のコンプリートカーだ。
「その頃に私達が始めた『ネグローニ』っていうブランドは、─日本人の足型に合わせたイタリアンテイストの靴─っていうのがコンセプトだったんです。ちょうどクルマ好きが高じてドライビングシューズを作り始めた時期でもあって、いろんな意味でピッタリでしょ。だから『ネグローニ』のイメージカーにしようかなって考えたんですよ。でもね、ボディカラーが赤だったから『ネグローニ』のイメージカラーのグリーンにしたいとか、内装がちっともイタリアンな雰囲気じゃないから革張りにしたいとか、デザインにはもっと流麗さが欲しいとか、買うって決めたら、色んなアイデアが湧いてきて止まらなくなっちゃって…」
会社が危機に陥ってる時である。価格はツルシでも350〜388万円と、決して安いものではなかった。
修一さんは、毎週のようにモデリスタに通ってデザイナーやメカニックと対話を繰り返し、当初はボディカラーの変更すら受け付けてもらえなかったにも関わらず、自分の熱意だけで彼らの情熱にパチンとスイッチを入れ、そこから2年もかけて自分の理想に近いクルマをワンオフで仕立てあげるようなとんでもないことを始めてしまったのだ。常務でもある奥様は反対しなかったのだろうか。
「私は賛成でした。余裕があったわけじゃないですけど、私達がやろうとしていることにとても合っているように感じました。ブランドを引っ張ってくれるような何かが必要だと思っていましたし。社長(修一さん)がクルマ作りから刺激を受けて、次々と靴作りに活かせる発想を持ち込んでくれるのも面白かったんです。社長は昔から発想が豊かな人で、それにいつも前向きだから、好きなことをしてもらってるのが一番いいと考えてましたから」と、驚くべき内助の功である。けれど、その言葉が正しいことは、後の出来事が証明していくのだった。
在庫量と工場の稼働スケジュール、材料の発注、取引先との打ち合わせ、そして営業と多岐にわたる業務を、学びながら即戦力として回していかなければならない状況だったのだ。そしてあるとき、大量受注に備えた見込み生産によって凄まじい量の在庫を抱えてることに疑問を感じ、それをなくすことを決意する。
「全くの素人だったので、業務や家事以外の時間には、ずっと本を読んで勉強したり考えたりしてましたね。大変だったような記憶はありますけど、でも……細かいことは忘れてしまいました。私、楽しいことしか覚えてないんですよ」明美さんはとても控えめなようで、御自身の功績や苦労話をとくとくと語ったりはしないけれど、その時の英断がなければ、発注元の倒産に引き摺られていただろうことは、容易に想像がつく。
そして従来の少品種大量生産だけに依存するのをヤメて、望まれたら1足からでもいいから作ろう、OEMだけではなくオリジナルブランドも立ち上げよう、と仕事をそれまでと違った軌道に乗せるべく動き始めたのだ。ところがその頃、修一さんは端から見たらとんでもないと言われそうなことを、いきなり思いついた。「色々あって気持ちの穴を埋めたかったようなところもあるんですけど、昔から好きだったイタリア車にまた乗りたくなってね。ちょうどそんなときにイタリアっぽさを前面に出した『カセルタ』っていうクルマを見つけて、これでも買ってみようかなって思って」
「カセルタ」というのは、トヨタの関連会社である「モデリスタ」が、ミドシップ2シーターの「MR-S」をベースに、イタリアンテイストなボディを被せて作り上げた限定販売のコンプリートカーだ。
「その頃に私達が始めた『ネグローニ』っていうブランドは、─日本人の足型に合わせたイタリアンテイストの靴─っていうのがコンセプトだったんです。ちょうどクルマ好きが高じてドライビングシューズを作り始めた時期でもあって、いろんな意味でピッタリでしょ。だから『ネグローニ』のイメージカーにしようかなって考えたんですよ。でもね、ボディカラーが赤だったから『ネグローニ』のイメージカラーのグリーンにしたいとか、内装がちっともイタリアンな雰囲気じゃないから革張りにしたいとか、デザインにはもっと流麗さが欲しいとか、買うって決めたら、色んなアイデアが湧いてきて止まらなくなっちゃって…」
会社が危機に陥ってる時である。価格はツルシでも350〜388万円と、決して安いものではなかった。
修一さんは、毎週のようにモデリスタに通ってデザイナーやメカニックと対話を繰り返し、当初はボディカラーの変更すら受け付けてもらえなかったにも関わらず、自分の熱意だけで彼らの情熱にパチンとスイッチを入れ、そこから2年もかけて自分の理想に近いクルマをワンオフで仕立てあげるようなとんでもないことを始めてしまったのだ。常務でもある奥様は反対しなかったのだろうか。
「私は賛成でした。余裕があったわけじゃないですけど、私達がやろうとしていることにとても合っているように感じました。ブランドを引っ張ってくれるような何かが必要だと思っていましたし。社長(修一さん)がクルマ作りから刺激を受けて、次々と靴作りに活かせる発想を持ち込んでくれるのも面白かったんです。社長は昔から発想が豊かな人で、それにいつも前向きだから、好きなことをしてもらってるのが一番いいと考えてましたから」と、驚くべき内助の功である。けれど、その言葉が正しいことは、後の出来事が証明していくのだった。
内装は「カセルタ」のものでは無く、全てがオリジナル。決定的に異なるのは、全てが美しいレザー張りになること。革を扱うシューズメーカーとして、どうしても妥協できなかった部分。施工には本業で付き合いのある専門業者に依頼した。
フェラーリ308GTBやベルリネッタ・ボクサーなど70年代生まれのフェラーリが履いた星形ホイールと同様のデザインの、クロモドラ製ホイール。イタリアンブランドのものであり、雰囲気と実用のバランスで選んで探し出したもの。
いうまでもなく『negroni』のエンブレムもワンオフだ。シューズのブランドイメージを背負うクルマであるがゆえ、ステッカーやカッティングシートで誤魔化すわけにはいかない。手間もコストもかかった“意思の力”がここにある。
ハードトップは「MR-S」のものを流用しながらも、ルーフのラインを変更し、同時にイタリアの老舗カロッツェリアである「ザガート」を思い起こさせるダブルバブル形状に変更。ちなみに室内側は総レザー張りという手間のかかり方だ。
「ランチア・ストラトス」にも流用された、「フィアット850」用のテールランプをチョイス。旧き佳きイタリア車のムードをカタチにするために、丸型の愛らしいデザインのものを探したのだ。往時のフェラーリにイメージは重なる。
電動調整式という利便性を捨てて、チョイスしたのは「ヴィタローニ」の“カリフォルニアン”というタイプ。汎用品ではあるが、フェラーリはもちろんランチアやフィアットにも純正採用されたのと同一の物だ。
ボディの素材はFRP、ウエットカーボン、アルミと箇所によって異なり、描くラインは「MR-S」とも「カセルタ」とも大幅に異なる。ウエストラインにあるエアインテークは機能も満たさねばならず、空気の流れを考えることも必須だった。
ドアを開けるためのアウターハンドルは、何と「アルファ・ロメオ156」のモノを削って整形して使っている。薄く、そして余分なエッジを落とすよう加工したことで、クラシカルな雰囲気に。これも考えに考え抜いた末のアイデアだった。
ヘッドランプはヴィンテージな雰囲気を重視して、すでにブランドとしては消滅しているイタリアの「キャレロ」のものをチョイス。ヘッドランプのプレクシ製カバーとそのアルミ製のフレームは、いうまでもなくワンオフで製作している。
シートはレカロの調整式バケットをベースにするが、ヘッドレストの形状をクルマの雰囲気に合わせて変更し、同時にこちらも総レザー張りに。「ネグローニ」のシューズはツルシの革では作らない。もちろんこれも特別誂えのレザーである。
ワンオフの悦びを売ってみたい
修一さんがモデリスタのスタッフを巻き込むかたちでスタートしたカスタマイズは、〝改造〟というレベルを遥かに超越していた。ボディは修一さんの想いをデザイナーに伝え、数えきれないくらいデザイン修正を繰り返したうえで、使うパーツは不可能なものを除けば全てワンオフ。
内装は総革張り。それら一連を書き連ねるだけで1冊の本ができるほど。やりとりも作業も多岐に渡った。結果、世界に1台だけのスポーツカー「ネグローニ・スパイダー」が完成したのだ。そのモデリスタとのやりとりの中で、修一さんはひとつ思いつく。
「私がワガママを言って、それがカタチになっていくのが凄く嬉しかったんですよ。だったら逆に、私達がお客様のワガママを聞いてカタチにするようなことを、靴作りの中でできないかってね」そうして出来上がったのが、カラーオーダーシステムである。パソコンの画面の中ではなく、靴の俯瞰図と側面図に様々な色や種類の革、透明なビニールにステッチだけ施したもの、そして靴紐を、実際に配置することのできるパズルのようなもので、完成状態を色・質感ともに確認しながらフルオーダーができるという仕組みだ。
簡単なようだが、この仕組みをカタチにするだけでも相当な手間がかかる。けれど客の立場からすれば、これほど出来上がりをイメージしやすいものはない。当時、「ネグローニ」を著名な百貨店で売りたいと考えていたが、認知度の高いものしか取り扱わないのが百貨店。
間口は恐ろしく狭い。ところが、「ネグローニ・スパイダー」と一緒に商品を展示するというアイデアと、明美常務の熱意ある営業努力もあって、このカラーオーダーシステムは百貨店のバイヤーを惹きつけた。「ネグローニ」は〝どちらも人を軽やかに移動させるもの〟という共通項を武器に壁を打ち破ったのだ。良品を見極める目を持つ人や、クルマの玄人筋を発信元にして評判が広がりを見せていった。
内装は総革張り。それら一連を書き連ねるだけで1冊の本ができるほど。やりとりも作業も多岐に渡った。結果、世界に1台だけのスポーツカー「ネグローニ・スパイダー」が完成したのだ。そのモデリスタとのやりとりの中で、修一さんはひとつ思いつく。
「私がワガママを言って、それがカタチになっていくのが凄く嬉しかったんですよ。だったら逆に、私達がお客様のワガママを聞いてカタチにするようなことを、靴作りの中でできないかってね」そうして出来上がったのが、カラーオーダーシステムである。パソコンの画面の中ではなく、靴の俯瞰図と側面図に様々な色や種類の革、透明なビニールにステッチだけ施したもの、そして靴紐を、実際に配置することのできるパズルのようなもので、完成状態を色・質感ともに確認しながらフルオーダーができるという仕組みだ。
簡単なようだが、この仕組みをカタチにするだけでも相当な手間がかかる。けれど客の立場からすれば、これほど出来上がりをイメージしやすいものはない。当時、「ネグローニ」を著名な百貨店で売りたいと考えていたが、認知度の高いものしか取り扱わないのが百貨店。
間口は恐ろしく狭い。ところが、「ネグローニ・スパイダー」と一緒に商品を展示するというアイデアと、明美常務の熱意ある営業努力もあって、このカラーオーダーシステムは百貨店のバイヤーを惹きつけた。「ネグローニ」は〝どちらも人を軽やかに移動させるもの〟という共通項を武器に壁を打ち破ったのだ。良品を見極める目を持つ人や、クルマの玄人筋を発信元にして評判が広がりを見せていった。
継承されていくクルマと仕事
以来、「ネグローニ・スパイダー」はブランドの象徴として現在に至る。張本人の修一さんは「遊びで作ったわけじゃないから、あちこち乗り回してるわけにはいかない」と、調子を保つためにときどき走らせる程度。
明美さんに至っては「ブランドそのもののイメージリーダーなのだから、私が乗ってイメージを壊すわけにはいかないんです。だから私は一度も乗ったことがないの」である。そして、いずれ会社やブランドと共にこのクルマを受け継ぐことになるのが、「マルミツ」の3代目となる修平さんだ。
修平さんは職業としての靴作りにもクルマにも全く関心のないまま少年時代を過ごし、学校を卒業してからはファッション雑誌の編集者になった。そして3年前、決意を父親にも母親にも語らないままいつの間にか家業を手伝い始め、今では「マルミツ」の中核となってバリバリ仕事をこなしている。父親の修一さんがしたのと同じようにゼロからのスタート。修一さんも立派な下町の頑固親父だから、優しく手ほどきをしたりなんかしない。
「今の仕事をちょっと囓ってみたら、すごく面白かったんですよ。それにドライビングシューズを扱ってるのにクルマを知らないのはダメだと思って積極的に運転するようになったら、クルマの面白さにも気付きました。マニュアル車に慣れてないのとマニアの人の話題についていけないときがあるのが、少しコンプレックスに感じるくらい」
そうしたクルマ好きのルーキーであり、息子であり、後を継ぐ職業人としての修平さんにとって、「ネグローニ・スパイダー」の存在はどう映るのだろうか。「正直いって、重たいです。社長である父と、それを支えてきた常務である母が大切にしてきたものであり、『ネグローニ』というブランドの原点ともいえる存在であり、世界にたった1台しかないクルマであり…と。だから最初は見ないふりをしてました。
でも、こうして靴作りに携わって何年か経って、クルマにも興味が出てきて、父や母がなぜこのクルマに拘るのかというのも理解できるようになってきました。気付くと〝いつか走らせてみたい〟って思うようになっていたんです。神輿みたいなものだから、普段から乗りたいっていうわけじゃなくて、このクルマを時々走らせることで、『ネグローニ』がどうあるべきかという原点に立ち返ることができるんじゃないかと思うんです」
「ネグローニ・スパイダー」だけではなく、クルマにはそういうところがある。修平さんの言葉に、これからの「ネグローニ」の行く先が見えてくるような気がする。
自動車というのは道具である。けれど、それは人が人との間に紡ごうとする物語を強く温かいものに育てていく、魔法の道具なのだ。
-----------------------------------------------
text:嶋田智之/Tomoyuki Shimada
1964年生まれ。エンスー系自動車雑誌『Tipo』の編集長を長年にわたって務め、総編集長として『ROSSO』のフルリニューアルを果たした後、独立。現在は自動車ライター&エディターとして活躍。
明美さんに至っては「ブランドそのもののイメージリーダーなのだから、私が乗ってイメージを壊すわけにはいかないんです。だから私は一度も乗ったことがないの」である。そして、いずれ会社やブランドと共にこのクルマを受け継ぐことになるのが、「マルミツ」の3代目となる修平さんだ。
修平さんは職業としての靴作りにもクルマにも全く関心のないまま少年時代を過ごし、学校を卒業してからはファッション雑誌の編集者になった。そして3年前、決意を父親にも母親にも語らないままいつの間にか家業を手伝い始め、今では「マルミツ」の中核となってバリバリ仕事をこなしている。父親の修一さんがしたのと同じようにゼロからのスタート。修一さんも立派な下町の頑固親父だから、優しく手ほどきをしたりなんかしない。
「今の仕事をちょっと囓ってみたら、すごく面白かったんですよ。それにドライビングシューズを扱ってるのにクルマを知らないのはダメだと思って積極的に運転するようになったら、クルマの面白さにも気付きました。マニュアル車に慣れてないのとマニアの人の話題についていけないときがあるのが、少しコンプレックスに感じるくらい」
そうしたクルマ好きのルーキーであり、息子であり、後を継ぐ職業人としての修平さんにとって、「ネグローニ・スパイダー」の存在はどう映るのだろうか。「正直いって、重たいです。社長である父と、それを支えてきた常務である母が大切にしてきたものであり、『ネグローニ』というブランドの原点ともいえる存在であり、世界にたった1台しかないクルマであり…と。だから最初は見ないふりをしてました。
でも、こうして靴作りに携わって何年か経って、クルマにも興味が出てきて、父や母がなぜこのクルマに拘るのかというのも理解できるようになってきました。気付くと〝いつか走らせてみたい〟って思うようになっていたんです。神輿みたいなものだから、普段から乗りたいっていうわけじゃなくて、このクルマを時々走らせることで、『ネグローニ』がどうあるべきかという原点に立ち返ることができるんじゃないかと思うんです」
「ネグローニ・スパイダー」だけではなく、クルマにはそういうところがある。修平さんの言葉に、これからの「ネグローニ」の行く先が見えてくるような気がする。
自動車というのは道具である。けれど、それは人が人との間に紡ごうとする物語を強く温かいものに育てていく、魔法の道具なのだ。
-----------------------------------------------
text:嶋田智之/Tomoyuki Shimada
1964年生まれ。エンスー系自動車雑誌『Tipo』の編集長を長年にわたって務め、総編集長として『ROSSO』のフルリニューアルを果たした後、独立。現在は自動車ライター&エディターとして活躍。