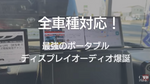45歳からの原点回帰
更新日:2024.09.09

※この記事には広告が含まれます
年齢を重ねるごとに、「感じること」が段々難しくなってくる。クルマやオートバイに対する情熱も以前のようには持てなくなってくるものだ。クルマやオートバイに乗り始めた頃のことを覚えているだろうか。自転車のように自分の足で漕がなくても前に進む歓びや、スピードという快感を初めて身体で感じたときのことを。そして、その頃に描いた夢のことを。今月は、50歳という年齢が見えてきたにも関わらず、もう一度、自分の原点に立ち戻って動き出した2人のストーリーを紹介しよう。
text:大鶴義丹、伊丹孝裕 photo:長谷川徹、渕本智信 [aheadアーカイブス vol.138 2014年6月号]
text:大鶴義丹、伊丹孝裕 photo:長谷川徹、渕本智信 [aheadアーカイブス vol.138 2014年6月号]
- Chapter
- 10代の頃のときめき
- 夢の原点を叶える 佐藤渉
10代の頃のときめき
text:大鶴義丹 photo:長谷川徹
いくつになっても忘れられない感覚がある。オートバイに乗り始めたころに覚えたカウンターを切る快感。いつの間にか大人になり、遊びまでも理屈で考えるようになっていった。結果、失ってしまったものは大きい。でも今ならまだ取り戻せる。要らないものを捨て去れば10代の頃のときめきが見えてくる。
いくつになっても忘れられない感覚がある。オートバイに乗り始めたころに覚えたカウンターを切る快感。いつの間にか大人になり、遊びまでも理屈で考えるようになっていった。結果、失ってしまったものは大きい。でも今ならまだ取り戻せる。要らないものを捨て去れば10代の頃のときめきが見えてくる。
50歳が見えて来た私たち世代の男子にとって、若い頃バイクを始めることに、きっかけや理由などは要らなかった。アマゾンの原住民の少年が大人になるために滝つぼに飛び込むのと同じことだ。ある種の民族的通過儀礼に過ぎない。
私がそんな滝つぼに飛び込んでから30年の時が流れた。16歳からほぼ途切れずにバイクに乗り続けている私がアラフォーからアラフィフになって気付いたことは、好きなことを好きにすればいいということだった。
20代30代、男の行動原理は分かり易い。そこにあるのは覇権のみである。出来る出来ないに関わらず全てのモノを手に入れよう、すべてのモノを飲み込んでしまおうと悪戦苦闘する。そのためには仲間も利用するし、犠牲だって恐れない。
しかしアラフィフになると分かりだす。その野望は普通の人間である限りは絶対に不可能だと。だが、普通の人間でも努力と情熱によっては、限られたものは手に入れられるし飲み込むこともできる。残された時間を有効に使うために、的を幾つかに絞る方が得策なのは分かり切ったことだった。
その結果、バイクに関して、私は何故か昔辞めたはずのオフロードバイクに回帰した。今までのバイクの乗り方を否定した訳ではなく、やっぱりオフロードが好きだったのだと思い出しただけである。
30代はバイク雑誌の仕事を始めたおかげで、300万円以上の外国製バイクにも散々乗り、国産の世界最速バイクをエンジンチューニングしたりした。筑波サーキットでタイムを縮めるレーサーごっこにもムキになり、40代になってからは映像化不可能と言われていた原作のバイク映画も作った。さらに劇中登場する500万円以上も改造費がかかった改造カタナやニンジャも自分のオモチャのように乗り回していた。
そんな私がである、アラフィフになった途端、再びオフロードに戻りたいと肉体が叫び始めているのに気付いた。滝つぼに飛び込んだのと同じだ、きっかけや理由などない。ある朝起きたらオフロードを走りたくなっていた。
そこで出会ったのがホンダ「CRF250L」だった。最新のマシンでありながら、どこか懐かしい匂いに溢れている。
調べてみると、少しの期間、中型オフロードモデルを欠番状態にしていたホンダが、満を持して発売したワールドワイドなマシンであるという。生粋のレーサー「CRF」の称号を持つこのマシン、オフロード版レーサーレプリカかと思いきや、実はこのマシンはある世界観を強く主張していたのだ。それは私たちの時代には当たり前に存在していた「トレール」という言葉を理解する必要がある。
まだ「エンデューロマシン」などという言葉が普通ではなかった頃、それは入手不可能な輸出モデルで高嶺の花でしかなかった。私たちのとっての二輪のオフロードマシンとは「トレール」と呼ばれているバイクのことだったのだ。
街も高速道路もガンガン走れて2人乗りも楽ちんにでき、山に行けば林道でも獣道でも雪道でも怖いものなし。河原でのモトクロスごっこも可能、少しくらいは転んでも壊れず、やりたいことがなんでもできた万能マシン。それこそが「トレール」であった。
ホンダはスタイルと称号こそレーサーCRFを強く意識したが、その実は「トレール」にしかない真価を復権させたかったのではないだろうか。40万円と少しで買えるという値段設定がその証拠でもある。
昨今の外車も含めた最新のエンデューロマシンは凄い。ほとんどが無改造で国際レースに出られるようなスペックである。当然のように値段も100万円オーバーはざら。そんなのものを「転んで当然」の感覚で乗れる訳がない。メンテナンスも数千キロでオーバーホールが必要な代物である。
砂漠を含めた大自然の中を全開で走ることが大前提の設計であるエンデューロレーサーを街乗りや通勤に使えるはずもなく、林道を楽しく走り回るにも持て余すだろう。結局レースに出る以外は使いようがないモンスターなのだ。
しかしあの頃の「トレール」は違ったはずだ。思い出すとあの時代にはすべての国産メーカーから素晴らしく使い勝手の良い「トレール」がラインアップされていた。
私がそんな滝つぼに飛び込んでから30年の時が流れた。16歳からほぼ途切れずにバイクに乗り続けている私がアラフォーからアラフィフになって気付いたことは、好きなことを好きにすればいいということだった。
20代30代、男の行動原理は分かり易い。そこにあるのは覇権のみである。出来る出来ないに関わらず全てのモノを手に入れよう、すべてのモノを飲み込んでしまおうと悪戦苦闘する。そのためには仲間も利用するし、犠牲だって恐れない。
しかしアラフィフになると分かりだす。その野望は普通の人間である限りは絶対に不可能だと。だが、普通の人間でも努力と情熱によっては、限られたものは手に入れられるし飲み込むこともできる。残された時間を有効に使うために、的を幾つかに絞る方が得策なのは分かり切ったことだった。
その結果、バイクに関して、私は何故か昔辞めたはずのオフロードバイクに回帰した。今までのバイクの乗り方を否定した訳ではなく、やっぱりオフロードが好きだったのだと思い出しただけである。
30代はバイク雑誌の仕事を始めたおかげで、300万円以上の外国製バイクにも散々乗り、国産の世界最速バイクをエンジンチューニングしたりした。筑波サーキットでタイムを縮めるレーサーごっこにもムキになり、40代になってからは映像化不可能と言われていた原作のバイク映画も作った。さらに劇中登場する500万円以上も改造費がかかった改造カタナやニンジャも自分のオモチャのように乗り回していた。
そんな私がである、アラフィフになった途端、再びオフロードに戻りたいと肉体が叫び始めているのに気付いた。滝つぼに飛び込んだのと同じだ、きっかけや理由などない。ある朝起きたらオフロードを走りたくなっていた。
そこで出会ったのがホンダ「CRF250L」だった。最新のマシンでありながら、どこか懐かしい匂いに溢れている。
調べてみると、少しの期間、中型オフロードモデルを欠番状態にしていたホンダが、満を持して発売したワールドワイドなマシンであるという。生粋のレーサー「CRF」の称号を持つこのマシン、オフロード版レーサーレプリカかと思いきや、実はこのマシンはある世界観を強く主張していたのだ。それは私たちの時代には当たり前に存在していた「トレール」という言葉を理解する必要がある。
まだ「エンデューロマシン」などという言葉が普通ではなかった頃、それは入手不可能な輸出モデルで高嶺の花でしかなかった。私たちのとっての二輪のオフロードマシンとは「トレール」と呼ばれているバイクのことだったのだ。
街も高速道路もガンガン走れて2人乗りも楽ちんにでき、山に行けば林道でも獣道でも雪道でも怖いものなし。河原でのモトクロスごっこも可能、少しくらいは転んでも壊れず、やりたいことがなんでもできた万能マシン。それこそが「トレール」であった。
ホンダはスタイルと称号こそレーサーCRFを強く意識したが、その実は「トレール」にしかない真価を復権させたかったのではないだろうか。40万円と少しで買えるという値段設定がその証拠でもある。
昨今の外車も含めた最新のエンデューロマシンは凄い。ほとんどが無改造で国際レースに出られるようなスペックである。当然のように値段も100万円オーバーはざら。そんなのものを「転んで当然」の感覚で乗れる訳がない。メンテナンスも数千キロでオーバーホールが必要な代物である。
砂漠を含めた大自然の中を全開で走ることが大前提の設計であるエンデューロレーサーを街乗りや通勤に使えるはずもなく、林道を楽しく走り回るにも持て余すだろう。結局レースに出る以外は使いようがないモンスターなのだ。
しかしあの頃の「トレール」は違ったはずだ。思い出すとあの時代にはすべての国産メーカーから素晴らしく使い勝手の良い「トレール」がラインアップされていた。
16歳になって私が初めて手に入れたバイクはまさにその「トレール」だった。本当はオンロードの400㏄で峠に行きたかったのだが、スピードが出過ぎるからダメだと親に言われた。つまり本意ではない選択だったのだ。値段は33万円だったと記憶している。
運良く同じ車種に乗っている年上の方と知り合いになり、当時は半分合法だった多摩川の仮設モトクロス場に行くことになった。当然最初は上手く走れるはずもなく、すぐに転んで新車は傷だらけ。おまけにハンドルを曲げて半べそをかいていた。
しかしその後、練習の成果か、強引に直したハンドルで、一瞬だがリアタイヤを滑らせカウンターを切った状態で走ることが出来た。今考えると一秒かそこいらだが、その感覚が頭の中でスパークした。それからはカウンターばかり練習した。徐々にカウンターを当てる時間は長くなり、取り憑かれたようにそれを繰り返した。
当時から「逆ハン」という言葉は漫画「サーキットの狼」で知っていた。それは漫画の中の世界でのみ存在していた魔法と同義語である。その入り口に自分が立っていることに震えたのだ。麻薬のようにその感覚が脳の奥に染みわたっていくのを16歳の少年はひとり静かに感じていた。小学校、中学校とサッカーをやっていたが、球技の世界では一度も味わったことのない快感だった。
神奈川県の川崎市に住んでいたことから、次の日からひとりでも多摩川の土手に通い始めた。バイクの傷は増えていき、砂の上に投げ出されて息が出来なくなるのも日常的になった。小学生の頃からモトクロッサーに乗り、本格的なモトクロスをやっているような連中の走りのレベルには敵う訳もなかったが、若さ故にあっという間にそれなりに走れるようになっていったのだ。
次に私が向かったのは、当時は未舗装路で溢れていた丹沢の林道だった。そこに行くと「林道暴走族」と呼べるような連中とたくさん知り合いになった。インターネットという情報源がない時代である。その手の出会いは物事を大きく動かした。
相模原にあるオフロード専門のバイク屋にも出入りするようになったのだ。この店の存在は大きく、この店からオフロードのコアな情報を手に入るようになっていく。モトクロスの真似事も適当にはやったが、私が一番惹かれたのは、エンデューロと呼ばれる長距離のオフロードレースであった。その最高峰こそが、かの「パリ・ダカールラリー」だった。
運良く同じ車種に乗っている年上の方と知り合いになり、当時は半分合法だった多摩川の仮設モトクロス場に行くことになった。当然最初は上手く走れるはずもなく、すぐに転んで新車は傷だらけ。おまけにハンドルを曲げて半べそをかいていた。
しかしその後、練習の成果か、強引に直したハンドルで、一瞬だがリアタイヤを滑らせカウンターを切った状態で走ることが出来た。今考えると一秒かそこいらだが、その感覚が頭の中でスパークした。それからはカウンターばかり練習した。徐々にカウンターを当てる時間は長くなり、取り憑かれたようにそれを繰り返した。
当時から「逆ハン」という言葉は漫画「サーキットの狼」で知っていた。それは漫画の中の世界でのみ存在していた魔法と同義語である。その入り口に自分が立っていることに震えたのだ。麻薬のようにその感覚が脳の奥に染みわたっていくのを16歳の少年はひとり静かに感じていた。小学校、中学校とサッカーをやっていたが、球技の世界では一度も味わったことのない快感だった。
神奈川県の川崎市に住んでいたことから、次の日からひとりでも多摩川の土手に通い始めた。バイクの傷は増えていき、砂の上に投げ出されて息が出来なくなるのも日常的になった。小学生の頃からモトクロッサーに乗り、本格的なモトクロスをやっているような連中の走りのレベルには敵う訳もなかったが、若さ故にあっという間にそれなりに走れるようになっていったのだ。
次に私が向かったのは、当時は未舗装路で溢れていた丹沢の林道だった。そこに行くと「林道暴走族」と呼べるような連中とたくさん知り合いになった。インターネットという情報源がない時代である。その手の出会いは物事を大きく動かした。
相模原にあるオフロード専門のバイク屋にも出入りするようになったのだ。この店の存在は大きく、この店からオフロードのコアな情報を手に入るようになっていく。モトクロスの真似事も適当にはやったが、私が一番惹かれたのは、エンデューロと呼ばれる長距離のオフロードレースであった。その最高峰こそが、かの「パリ・ダカールラリー」だった。
だがそんなレースに出られるのは夢のまた夢で、高校生の頃は埼玉県などで行われるモトクロス場を何周もするような「草エンデューロ」と呼ばれる草レースに同年代の仲間と年に一回くらい参加するのが精いっぱいだった。
成績は80台くらい参加の35位くらいだったが、大人たちのお金のかかっている逆輸入マシンに混じっての結果なので、若さとは大したものである。結局その勢いで22歳までオフロード一色のバイクライフであった。最終的にはアメリカから逆輸入したホンダの「XR250」のレース仕様を持つまでになり、それをボロボロのイスズの「ファーゴ」にトランポして色々な場所に遠征していった。
しかし「ファーゴ」に罪はないが、このトランポを持つことが原因となり、私のバイクライフは一度終止符打つことになる。極論かもしれないがバイク乗りは、レースをしないならトランポを持ってはいけない。レースとバイクに乗るという作業は全く別のことなのだ。その二つは似ているようだが、乗っている人間の気持ちは全く別だ。
それを理解せず、競技場に行くならまだしも、関東近郊の山などに走りに行くにも、オフロードバイクをトランポするようになってしまった。エアコン付きで色々な道具も積めるので確かに楽である。空母で楽に移動して現地で小型戦闘機を発進させるというようなもので、確実に合理的である。
しかしそれを繰り返した挙句、結局バイクに乗りたいのか、オフロードバイクでアマチュア競技をしたいのかが分からなくなってしまったのだ。バイクに乗るということは不合理なことであり、合理性を追求する四輪とは絶対に相まみえることはないのである。
結果、競技にもバイクに乗ること自体にも興味をなくしてしまい、四輪の改造やレースに気持ちは移っていってしまった。
繰り返す、絶対にバイクをクルマで運んでは駄目だ。それをすると、バイク本来の意味や、バイクに乗ると言う目的の本質をあっという間に忘れてしまう。雨が降ろうが、暑くても寒くてもバイクで走ることがバイクと付き合う正しい姿なのである。最高のトレール車であるホンダ
「CRF250L」に乗るということは、その失敗を繰り返すまいと誓ったアラフィフの私が出した答えなのだ。
当時は、神話の中にしか存在しなかったエンデューロレーサーも、今では簡単に手に入れることができる。だがそれを今の私は必要としていない。私はレースをしたい訳ではない。街でも山でも、誰からも束縛されずに走り回りたいだけだ。私と同じような輩は沢山いるはずだ。30年間バイクに乗り続けた結果、得た答えはこんな簡単なことだった。だからこのマシンでスーパーに行って買い物もするし、オフロードでは、これからも土煙を上げてカウンターを切る。
成績は80台くらい参加の35位くらいだったが、大人たちのお金のかかっている逆輸入マシンに混じっての結果なので、若さとは大したものである。結局その勢いで22歳までオフロード一色のバイクライフであった。最終的にはアメリカから逆輸入したホンダの「XR250」のレース仕様を持つまでになり、それをボロボロのイスズの「ファーゴ」にトランポして色々な場所に遠征していった。
しかし「ファーゴ」に罪はないが、このトランポを持つことが原因となり、私のバイクライフは一度終止符打つことになる。極論かもしれないがバイク乗りは、レースをしないならトランポを持ってはいけない。レースとバイクに乗るという作業は全く別のことなのだ。その二つは似ているようだが、乗っている人間の気持ちは全く別だ。
それを理解せず、競技場に行くならまだしも、関東近郊の山などに走りに行くにも、オフロードバイクをトランポするようになってしまった。エアコン付きで色々な道具も積めるので確かに楽である。空母で楽に移動して現地で小型戦闘機を発進させるというようなもので、確実に合理的である。
しかしそれを繰り返した挙句、結局バイクに乗りたいのか、オフロードバイクでアマチュア競技をしたいのかが分からなくなってしまったのだ。バイクに乗るということは不合理なことであり、合理性を追求する四輪とは絶対に相まみえることはないのである。
結果、競技にもバイクに乗ること自体にも興味をなくしてしまい、四輪の改造やレースに気持ちは移っていってしまった。
繰り返す、絶対にバイクをクルマで運んでは駄目だ。それをすると、バイク本来の意味や、バイクに乗ると言う目的の本質をあっという間に忘れてしまう。雨が降ろうが、暑くても寒くてもバイクで走ることがバイクと付き合う正しい姿なのである。最高のトレール車であるホンダ
「CRF250L」に乗るということは、その失敗を繰り返すまいと誓ったアラフィフの私が出した答えなのだ。
当時は、神話の中にしか存在しなかったエンデューロレーサーも、今では簡単に手に入れることができる。だがそれを今の私は必要としていない。私はレースをしたい訳ではない。街でも山でも、誰からも束縛されずに走り回りたいだけだ。私と同じような輩は沢山いるはずだ。30年間バイクに乗り続けた結果、得た答えはこんな簡単なことだった。だからこのマシンでスーパーに行って買い物もするし、オフロードでは、これからも土煙を上げてカウンターを切る。
-----------------------------------------
text:大鶴義丹/Gitan Ohtsuru
1968年生まれ。俳優・監督・作家。知る人ぞ知る“熱き”バイク乗りである。本人によるブログ「不思議の毎日」はameblo.jp/gitan1968
text:大鶴義丹/Gitan Ohtsuru
1968年生まれ。俳優・監督・作家。知る人ぞ知る“熱き”バイク乗りである。本人によるブログ「不思議の毎日」はameblo.jp/gitan1968
夢の原点を叶える 佐藤渉
text:伊丹孝裕 photo:渕本智信
50歳が見えてくる年齢になっても消せない夢がある。〝いずれ〟も〝そのうち〟も待っているだけではやって来ない。本当にやりたいことや、持っていたはずの夢を完全に忘れてしまう前に、今こそ動き出そう。人生とは自分に与えられた時間なのだから。やってしまった後悔は取り戻せても、やらなかった後悔は取り戻せない。
50歳が見えてくる年齢になっても消せない夢がある。〝いずれ〟も〝そのうち〟も待っているだけではやって来ない。本当にやりたいことや、持っていたはずの夢を完全に忘れてしまう前に、今こそ動き出そう。人生とは自分に与えられた時間なのだから。やってしまった後悔は取り戻せても、やらなかった後悔は取り戻せない。
クルマのことが大好きだと分かりきっている相手に、いささか直球が過ぎると思われたが、前置きなしに「クルマに興味を持ったのはいつでしたか?」と切り出してみた。おそらく幼稚園や小学生時代のエピソードから始まることを予想して。
その相手が佐藤 渉さんだ。現在ルノー・ジャポンの広報グループに所属し、会社設立当社から携わってきた最古参のメンバーのひとりである。
「立場上マズイと思うんですが、免許すら要らないと思っていたくらい興味の対象外でした。大学生の時に、免許くらい持っていないと就職にも困る、と親に諭されて渋々教習所に通ったものの自転車で十分満足でした。多少自覚していますが、どうも周りの人とは時間の感覚がズレているらしく、ブームや通過すべきことがいつも人より5年か10年くらい遅れて来るんです」と申し訳なさそうに笑う。
実際、自転車に関してもそうで、友人達は当然のように小学生で乗り回していたものの、佐藤さんが初めてそれを手に入れたのは高校生になってからのこと。その頃、友人達の興味はとっくにバイクへと移っていたにもかかわらずだ。
ただし、今回のテーマにもつながる妙な入れ込み具合いが、ここで少し顔を覗かせる。というのも自転車に乗り始めた途端、いきなり北海道へのツーリングを敢行し、やがて大学に進み、みんながクルマに乗り始めた頃にようやくバイクに目がいくようになったかと思えば、今度はツーリングではなく、サーキットでバイクレースのオフィシャルのアルバイトを始めるなど、一度興味を持った後の振り幅がちょっと異質な人なのだ。そうした独特の間合いは、いざ就職が迫ってきた時も如何なく発揮された。
「何をしたいか考えているうちに就職よりもレースがしたくなったんですね」と、サラリと言う。
年齢的なことはさておいて、例えばそこから一念発起して本気でレーシングドライバーを目指した、というなら話はまだストレートで分かりやすい。佐藤さんがやはり独特なのは、「だからと言って、プロになりたかったわけじゃないんです」と付け加えたことだ。
かいつまんで書くと、「クルマが好きというよりもモータースポーツが好き。だから、自分もレーサーのように上手く操れるようになりたい。そのために正しいドライビングを学びたい。それにはちゃんと指導を受けられる環境が必要だ。しかし日本ではなかなか難しい。だったら海外へ行こう」と、自分の中でそういう結論に至ったらしい。
そして、本当に就職活動を辞め、大学卒業後はアルバイトしながら貯金。並行してモータースポーツにまつわる海外の情報を集め、いくつかの候補の中から、イギリスの名門ジム・ラッセル・レーシングスクールのカナダ校の門を叩くことに決めたという。ちなみに本国イギリスのジム・ラッセル・レーシングスクールの卒業生には、アイルトン・セナやジェンソン・バトンといったF1ドライバーも名を連ねている。
「ここはスクールの中で働きながらプログラムを受けられるんです。だから走っていないときも、常にクルマとの関わりを持っていられる。住む場所も光熱費もただなんです。そんな環境の中で、1年くらい居たでしょうか。使われるクルマはいわゆるフォーミュラカーです。スクール内は基本的に英語でしたが、場所がケベックだったため外に出ると公用語はフランス語。どちらにしてもまともに話せないので最初は苦労しましたね。もちろん、ドライビングに関してはもっと大変で、ただ普通に加速するだけでも何度もスピンする始末。それでもあの刺激や爽快感は他では代えの効かない世界でした」
この時、佐藤さんは24歳。言わば、このカナダでの1年こそが、今の佐藤さんに至る原点になったと言えるだろう。
その相手が佐藤 渉さんだ。現在ルノー・ジャポンの広報グループに所属し、会社設立当社から携わってきた最古参のメンバーのひとりである。
「立場上マズイと思うんですが、免許すら要らないと思っていたくらい興味の対象外でした。大学生の時に、免許くらい持っていないと就職にも困る、と親に諭されて渋々教習所に通ったものの自転車で十分満足でした。多少自覚していますが、どうも周りの人とは時間の感覚がズレているらしく、ブームや通過すべきことがいつも人より5年か10年くらい遅れて来るんです」と申し訳なさそうに笑う。
実際、自転車に関してもそうで、友人達は当然のように小学生で乗り回していたものの、佐藤さんが初めてそれを手に入れたのは高校生になってからのこと。その頃、友人達の興味はとっくにバイクへと移っていたにもかかわらずだ。
ただし、今回のテーマにもつながる妙な入れ込み具合いが、ここで少し顔を覗かせる。というのも自転車に乗り始めた途端、いきなり北海道へのツーリングを敢行し、やがて大学に進み、みんながクルマに乗り始めた頃にようやくバイクに目がいくようになったかと思えば、今度はツーリングではなく、サーキットでバイクレースのオフィシャルのアルバイトを始めるなど、一度興味を持った後の振り幅がちょっと異質な人なのだ。そうした独特の間合いは、いざ就職が迫ってきた時も如何なく発揮された。
「何をしたいか考えているうちに就職よりもレースがしたくなったんですね」と、サラリと言う。
年齢的なことはさておいて、例えばそこから一念発起して本気でレーシングドライバーを目指した、というなら話はまだストレートで分かりやすい。佐藤さんがやはり独特なのは、「だからと言って、プロになりたかったわけじゃないんです」と付け加えたことだ。
かいつまんで書くと、「クルマが好きというよりもモータースポーツが好き。だから、自分もレーサーのように上手く操れるようになりたい。そのために正しいドライビングを学びたい。それにはちゃんと指導を受けられる環境が必要だ。しかし日本ではなかなか難しい。だったら海外へ行こう」と、自分の中でそういう結論に至ったらしい。
そして、本当に就職活動を辞め、大学卒業後はアルバイトしながら貯金。並行してモータースポーツにまつわる海外の情報を集め、いくつかの候補の中から、イギリスの名門ジム・ラッセル・レーシングスクールのカナダ校の門を叩くことに決めたという。ちなみに本国イギリスのジム・ラッセル・レーシングスクールの卒業生には、アイルトン・セナやジェンソン・バトンといったF1ドライバーも名を連ねている。
「ここはスクールの中で働きながらプログラムを受けられるんです。だから走っていないときも、常にクルマとの関わりを持っていられる。住む場所も光熱費もただなんです。そんな環境の中で、1年くらい居たでしょうか。使われるクルマはいわゆるフォーミュラカーです。スクール内は基本的に英語でしたが、場所がケベックだったため外に出ると公用語はフランス語。どちらにしてもまともに話せないので最初は苦労しましたね。もちろん、ドライビングに関してはもっと大変で、ただ普通に加速するだけでも何度もスピンする始末。それでもあの刺激や爽快感は他では代えの効かない世界でした」
この時、佐藤さんは24歳。言わば、このカナダでの1年こそが、今の佐藤さんに至る原点になったと言えるだろう。
●佐藤 渉
1967年生まれの47歳。ルノー・ジャポン広報最古参のメンバー。控えめな性格ながら、クルマへの情熱は人一倍。各方面から強い信頼を得ている。
1967年生まれの47歳。ルノー・ジャポン広報最古参のメンバー。控えめな性格ながら、クルマへの情熱は人一倍。各方面から強い信頼を得ている。
「実家には『ちょっと運転の勉強をしてくる』と言って出て行ったんですけど、本当にその通りになりました。スクールの中には生まれついてのドライバーみたいな連中がウヨウヨいて、そういうのを目の当たりにするとちょっとかなわないと。つまりそれは、血筋だったり、経済環境だったりも含めてのことです。最初からステージが違う感じでしたね。プロへの憧れはどこかにありましたが、わりと早い段階で、環境も含めた自分の能力を知れたのは良かったかもしれません」
とは言え、クルマへの情熱は以前よりも確実に強いものになっていた。「日本に戻ってきてからは家業を手伝いながらも、せっかくの経験を中途半端に持て余していたというか、なんとなく悶々としていたのは事実です。ある時ふいにこのままでは駄目だと、どうにも我慢ができなくなって、実家のあった仙台から東京に出てきたところ、後にルノー・ジャポンの前身にもなる会社と縁ができ、その手伝いをするようになったことが現在の仕事に就くきっかけでした」
その過程で、佐藤さんはドライビングレッスンの講師も何度か務めている。クルマは、操作を少し誤るだけでいとも簡単にクラッシュし、時には死に至ることもある。それは緩慢な操作を許さないフォーミュラの経験からくるもので、乗用車の場合は単にクルマがドライバーのミスを許容してくれているだけ。
そのことを一般ドライバーに伝えることに意義を見出していた。その一方でルノーの仕事も忙しくなり、悩んだ末、後者を選択する。そして正式に設立されたルノー・ジャポンに入社。働き盛りの30代を過ごす中で、佐藤さんの中にあったフォーミュラへの想いは薄らいでいったかのようにも思えた。
とは言え、クルマへの情熱は以前よりも確実に強いものになっていた。「日本に戻ってきてからは家業を手伝いながらも、せっかくの経験を中途半端に持て余していたというか、なんとなく悶々としていたのは事実です。ある時ふいにこのままでは駄目だと、どうにも我慢ができなくなって、実家のあった仙台から東京に出てきたところ、後にルノー・ジャポンの前身にもなる会社と縁ができ、その手伝いをするようになったことが現在の仕事に就くきっかけでした」
その過程で、佐藤さんはドライビングレッスンの講師も何度か務めている。クルマは、操作を少し誤るだけでいとも簡単にクラッシュし、時には死に至ることもある。それは緩慢な操作を許さないフォーミュラの経験からくるもので、乗用車の場合は単にクルマがドライバーのミスを許容してくれているだけ。
そのことを一般ドライバーに伝えることに意義を見出していた。その一方でルノーの仕事も忙しくなり、悩んだ末、後者を選択する。そして正式に設立されたルノー・ジャポンに入社。働き盛りの30代を過ごす中で、佐藤さんの中にあったフォーミュラへの想いは薄らいでいったかのようにも思えた。
「40代に差し掛かった頃、仕事やプライベートでたまたまサーキットに顔を出す機会が増えたんです。体はウズウズしていましたが、クルマもないので現実的に自分で走るのは難しい。ただその一方で『いつかそういう日が来てもいいように準備だけはしておこう』と、なぜかそんな風にも思っていました」
それからというもの、佐藤さんは少しずつ行動を開始する。まずはライセンスを取り、次にレーシングスーツを買い、次にシューズを揃え、そしてヘルメット…とここまでで数年を掛けてクルマ以外の一切を揃えていったのだ。
となれば、あとはクルマを手に入れるタイミングやふんぎりである。最後のひと押しになったのは、そばで長い間準備をする様を見せつけられてきた奥さんの「一体、いつになったら買うの?」という発破を掛けるひと言だった。自身の気持ちや物理的な条件、家族の理解、仕事との兼ね合い…そんな諸々がいい流れとして重なり、佐藤さんは「今を逃したら一生乗れない」という思いに駆られ、本国のルノー・スポールにこう打診する。「フォーミュラ・ルノーを探している」と。
もちろん、選択肢は他にもあった。通常のラインアップにもRS(=ルノー・スポール)の名を冠するホットバージョンがあったし、一時はクリオV6やメガーヌR 26.Rといったスペシャルモデルも検討した。しかし、やはり佐藤さんはフォーミュラならではのソリッドな感覚が忘れられなかった。
「純粋なレーシングマシンですから、操作には高い精度が要求されます。だからこそ一瞬でも、たったひとつのコーナーでも上手くこなせた時の快楽は他に代えがたいものがあるのです。その時に得られるギリギリ感や『次はもっと上手く』という欲求こそが私の中にあるクルマの原点。妥協したら絶対につまらなくなる。そんな一心でした」
やがて、ヨーロッパの選手権を走っていた状態のいい個体が何台か見つかったという知らせが送られてきた。手に入れることに迷いはない。あとは価格や程度とのバランスを踏まえて、その中から1台を選び、日本へ運ぶ手続きを済ませた。ちょうど1年程前のことである。
それからというもの、佐藤さんは少しずつ行動を開始する。まずはライセンスを取り、次にレーシングスーツを買い、次にシューズを揃え、そしてヘルメット…とここまでで数年を掛けてクルマ以外の一切を揃えていったのだ。
となれば、あとはクルマを手に入れるタイミングやふんぎりである。最後のひと押しになったのは、そばで長い間準備をする様を見せつけられてきた奥さんの「一体、いつになったら買うの?」という発破を掛けるひと言だった。自身の気持ちや物理的な条件、家族の理解、仕事との兼ね合い…そんな諸々がいい流れとして重なり、佐藤さんは「今を逃したら一生乗れない」という思いに駆られ、本国のルノー・スポールにこう打診する。「フォーミュラ・ルノーを探している」と。
もちろん、選択肢は他にもあった。通常のラインアップにもRS(=ルノー・スポール)の名を冠するホットバージョンがあったし、一時はクリオV6やメガーヌR 26.Rといったスペシャルモデルも検討した。しかし、やはり佐藤さんはフォーミュラならではのソリッドな感覚が忘れられなかった。
「純粋なレーシングマシンですから、操作には高い精度が要求されます。だからこそ一瞬でも、たったひとつのコーナーでも上手くこなせた時の快楽は他に代えがたいものがあるのです。その時に得られるギリギリ感や『次はもっと上手く』という欲求こそが私の中にあるクルマの原点。妥協したら絶対につまらなくなる。そんな一心でした」
やがて、ヨーロッパの選手権を走っていた状態のいい個体が何台か見つかったという知らせが送られてきた。手に入れることに迷いはない。あとは価格や程度とのバランスを踏まえて、その中から1台を選び、日本へ運ぶ手続きを済ませた。ちょうど1年程前のことである。
ところで、一般的にはフォーミュラカーを所有し、それを走らせることなどあまり実感が湧かないだろう。特にコストがそうだ。そのあたりのことを、佐藤さんは実に忌憚なく答えてくれた。
「フォーミュラカーは決して遠い存在ではありません。私の場合、車両の購入価格は3万ユーロ(約350万円強)程でしたし、保管や運搬、走行に関しては、富士スピードウェイ近くにガレージを構えるノバエンジニアリングさんにお願いしています。もちろん1回あたりの走行代は少々掛かりますが、走らせるのはせいぜい2~3か月に一度。都内でクルマを所有し、日々ガソリン代や駐車場代、保険代等を払うことを思えば年間の維持費はそれほど大差なく、極めて現実的と言えるでしょう。スーパーカーと呼ばれるような車両を購入するよりも断然安く、それでいて刺激的な時間が過ごせると思うのです」
事実、佐藤さんは「メーカーの広報としては大変申し上げづらいのですが…」と前置きした上で、現在乗用車は所有せず、その分の維持費をフォーミュラ・ルノーとの時間に費やしているのだという。
ルノーは、カングーやキャプチャーといった日常に密着したモデルで知られる一方、その対極とも呼べるフォーミュラカーを世界で最も生産しているメーカーでもある。F1でのシェア(全11チーム中4チームがルノーエンジンを搭載)からも分かる通り、むしろこちらがルノーの真骨頂と言っていいのかもしれない。言わば、その根幹を支えているフォーミュラ・ルノーを操り、その魅力に浸っている佐藤さんは、最も自社製品への愛に溢れた広報マンと呼ばれるべきだろう。
最初のフォーミュラ体験から20年以上の時が過ぎたが、佐藤さんは再び原点へと戻ったのだ。あの頃のときめきを忘れない限り、いつかそこへ還り、時間を巻き戻すことができる。佐藤さんは静かにそのことを教えてくれている。
「フォーミュラカーは決して遠い存在ではありません。私の場合、車両の購入価格は3万ユーロ(約350万円強)程でしたし、保管や運搬、走行に関しては、富士スピードウェイ近くにガレージを構えるノバエンジニアリングさんにお願いしています。もちろん1回あたりの走行代は少々掛かりますが、走らせるのはせいぜい2~3か月に一度。都内でクルマを所有し、日々ガソリン代や駐車場代、保険代等を払うことを思えば年間の維持費はそれほど大差なく、極めて現実的と言えるでしょう。スーパーカーと呼ばれるような車両を購入するよりも断然安く、それでいて刺激的な時間が過ごせると思うのです」
事実、佐藤さんは「メーカーの広報としては大変申し上げづらいのですが…」と前置きした上で、現在乗用車は所有せず、その分の維持費をフォーミュラ・ルノーとの時間に費やしているのだという。
ルノーは、カングーやキャプチャーといった日常に密着したモデルで知られる一方、その対極とも呼べるフォーミュラカーを世界で最も生産しているメーカーでもある。F1でのシェア(全11チーム中4チームがルノーエンジンを搭載)からも分かる通り、むしろこちらがルノーの真骨頂と言っていいのかもしれない。言わば、その根幹を支えているフォーミュラ・ルノーを操り、その魅力に浸っている佐藤さんは、最も自社製品への愛に溢れた広報マンと呼ばれるべきだろう。
最初のフォーミュラ体験から20年以上の時が過ぎたが、佐藤さんは再び原点へと戻ったのだ。あの頃のときめきを忘れない限り、いつかそこへ還り、時間を巻き戻すことができる。佐藤さんは静かにそのことを教えてくれている。
-----------------------------------------
text:伊丹孝裕/Takahiro Itami
1971年生まれ。二輪専門誌『クラブマン』の編集長を務めた後にフリーランスのモーターサイクルジャーナリストへ転向。レーシングライダーとしても活動し、これまでマン島TTやパイクスピーク、鈴鹿八耐を始めとする国内外のレースに参戦してきた。国際A級ライダー。
text:伊丹孝裕/Takahiro Itami
1971年生まれ。二輪専門誌『クラブマン』の編集長を務めた後にフリーランスのモーターサイクルジャーナリストへ転向。レーシングライダーとしても活動し、これまでマン島TTやパイクスピーク、鈴鹿八耐を始めとする国内外のレースに参戦してきた。国際A級ライダー。