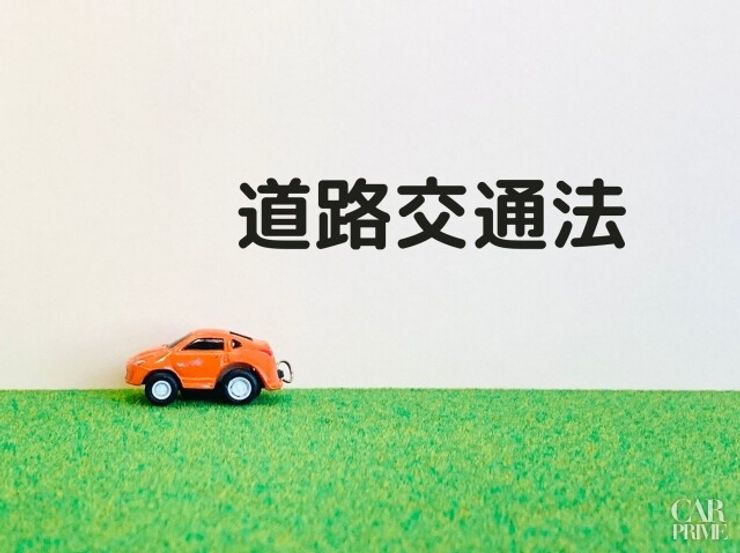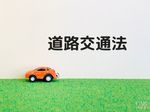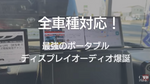キャタピラ車両は一般道を走行できるのか?規制と許可、リスクと対策
更新日:2025.08.07

※この記事には広告が含まれます
建設・土木・農業などで活躍するキャタピラ(無限軌道)車両は、現場から現場へどのように移動させるべきか。
本記事では、法律・許可・損傷リスク を網羅し、違反や高額な補修費を回避するためのチェックポイントを解説します。
本記事では、法律・許可・損傷リスク を網羅し、違反や高額な補修費を回避するためのチェックポイントを解説します。
キャタピラ車両は一般道を走行できる?基本ルールと例外
建設重機や戦車など、無限軌道(クローラー、通称キャタピラ)で走行する車両が一般道を自走することは原則として禁止されています。
日本の道路交通法では、公道を走行する車両は基本的にタイヤ装着が前提とされ、クローラー車両は「大型特殊自動車」など特殊な区分に分類されます。これはキャタピラが舗装路を損傷するおそれがあること、また重機はそもそも低速で公道走行に適さないことなど、安全面・道路保護の観点から定められた措置です。
したがって、キャタピラ式の建機をそのまま公道で走らせることはできず、通常はトレーラーなどに積載して現場へ輸送するのが前提となります。
もっとも、例外的にキャタピラ車両の一般道走行が認められるケースも存在します。
ただしその場合でも、車両自体が道路運送車両法の保安基準(ライトやウィンカー、ナンバー取得等)を満たし登録されていることや、運転者が適切な免許(後述)を所持していることが大前提です。登録番号の取れない重機(ナンバープレートのないバックホウ等)は、公道を走らせること自体ができません。以下では、この法規制の詳細や許可条件、そして実際に走行させる場合のリスクと対策について解説します。
日本の道路交通法では、公道を走行する車両は基本的にタイヤ装着が前提とされ、クローラー車両は「大型特殊自動車」など特殊な区分に分類されます。これはキャタピラが舗装路を損傷するおそれがあること、また重機はそもそも低速で公道走行に適さないことなど、安全面・道路保護の観点から定められた措置です。
したがって、キャタピラ式の建機をそのまま公道で走らせることはできず、通常はトレーラーなどに積載して現場へ輸送するのが前提となります。
もっとも、例外的にキャタピラ車両の一般道走行が認められるケースも存在します。
ただしその場合でも、車両自体が道路運送車両法の保安基準(ライトやウィンカー、ナンバー取得等)を満たし登録されていることや、運転者が適切な免許(後述)を所持していることが大前提です。登録番号の取れない重機(ナンバープレートのないバックホウ等)は、公道を走らせること自体ができません。以下では、この法規制の詳細や許可条件、そして実際に走行させる場合のリスクと対策について解説します。
「道路交通法」と「道路法」でわかるキャタピラ公道規制の全体像
道路交通法で求められる免許・装備
キャタピラ走行の重機や戦車は道路交通法上「大型特殊自動車」に分類され、公道を走るには大型特殊免許(キャタピラ限定)など専用の運転免許が必要です。
また、公道走行のためには方向指示器や前照灯・後写鏡など保安装備の装着も求められます。日本では、戦車でさえウインカーやブレーキランプ、ミラー等が装備されており、道路交通法を遵守できるよう改造されています。
これらを満たして初めてナンバー登録が可能となりますが、実際、「鉄製キャタピラ車は公道走行不可」が大原則であり、公道を走行できるクローラー車両はゴム製クローラーを装着した一部の小型特殊自動車などに限られます。
また、公道走行のためには方向指示器や前照灯・後写鏡など保安装備の装着も求められます。日本では、戦車でさえウインカーやブレーキランプ、ミラー等が装備されており、道路交通法を遵守できるよう改造されています。
これらを満たして初めてナンバー登録が可能となりますが、実際、「鉄製キャタピラ車は公道走行不可」が大原則であり、公道を走行できるクローラー車両はゴム製クローラーを装着した一部の小型特殊自動車などに限られます。
車両制限令が定めるキャタピラ禁止条項と3つの例外
道路法に基づく政令「車両制限令」では、道路構造を守るため特定の車両は道路通行を禁止しています。その中で第九条がキャタピラ車両に関する規定で、舗装道路上を通行する車両は以下の条件に該当する場合を除きキャタピラを有してはならないと明記されています。
上記の (1) は例えばゴム製クローラー(ゴムキャタピラ)のように舗装にダメージを与えにくい構造を指します。
(2) は冬季に自治体などが運用する除雪車(ロータリ除雪車や装軌式除雪車など)で、公の目的で特別に認められるケースです。
(3) は敷鉄板や厚板を敷いて路面を保護しながら走行する場合で、工事現場で鉄キャタの重機を一時的に道路横断させる際などに取られる措置です。
これら条件を満たせば道路管理者から通行認定や許可を受けることで走行可能ですが、それ以外の状況では舗装道路上をキャタピラ車両が走ることは認められていません。
なお、非舗装路(砂利道や未整備道路)であればこの規制は及ばず、走行自体は法律上問題ありません。とはいえ、公道である以上は他の交通や安全への配慮が必要なのは言うまでもありません。
- 路面を損傷しない構造(ゴムクローラー等)
- 除雪作業など公益目的での走行
- 敷鉄板など養生による一時的通行
上記の (1) は例えばゴム製クローラー(ゴムキャタピラ)のように舗装にダメージを与えにくい構造を指します。
(2) は冬季に自治体などが運用する除雪車(ロータリ除雪車や装軌式除雪車など)で、公の目的で特別に認められるケースです。
(3) は敷鉄板や厚板を敷いて路面を保護しながら走行する場合で、工事現場で鉄キャタの重機を一時的に道路横断させる際などに取られる措置です。
これら条件を満たせば道路管理者から通行認定や許可を受けることで走行可能ですが、それ以外の状況では舗装道路上をキャタピラ車両が走ることは認められていません。
なお、非舗装路(砂利道や未整備道路)であればこの規制は及ばず、走行自体は法律上問題ありません。とはいえ、公道である以上は他の交通や安全への配慮が必要なのは言うまでもありません。
鉄キャタ vs ゴムキャタ:公道走行への影響と選び方
「キャタピラの構造が路面を損傷するおそれがない場合」つまり路面を傷めない構造であれば、公道走行が例外的に許可され得ます。
一般的に鉄製の履帯は路面との摩擦でアスファルトを削ったりヒビ割れを起こしやすいため、この条件を満たすとは言えません。
一方、ゴム製の履帯(ゴムクローラー)は接地面がゴムで覆われており路面へのダメージが格段に小さいことから、法律上「損傷のおそれがない」構造として扱われます。実際、自衛隊の戦車も公道を走行するときは金属履帯にゴムパッドを装着し、路面を直接傷つけないようにしています。
ゴムクローラーを標準装備した農業用トラクターや不整地運搬車などはナンバー登録されて公道を走れる車両も存在し、方向指示器など必要な装備を備えれば小型特殊自動車として公道走行が可能です。
こうしたゴム履帯の車両であっても急旋回や長距離走行は避け、路面を摩耗させない慎重な運転が求められます。ゴム履帯は舗装上では摩耗も早く、製造メーカーも「舗装路での長時間走行は寿命を縮める」と注意喚起するほどです。
したがって、ゴムだからといって無制限に走ってよいわけではなく、あくまで短距離・低速かつ必要最低限に留めることが望ましいでしょう。
一方、鉄製キャタピラの場合はゴムパッドを後付けする方法があります。
重機メーカーやアフターパーツで鉄履帯用のゴムパッドが販売されており、ボルトで履帯板に装着することで路面との直接接触をゴム面にするものです。これにより簡易的にゴムクローラー化でき、舗装への攻撃性を下げることができます。
ただし、ゴムパッドを付けても車両重量が大きければ路面を押し付ける力は強大なままであり、完全に損傷リスクをゼロにできるわけではありません。
また装着に手間がかかることや、パッド自体の摩耗も進むため、やはり一時的・限定的な利用に留まります。鉄キャタピラの重機をどうしても舗装路で動かす必要がある場合は、後述するように敷鉄板などで道路を養生したうえで最徐行する、といった対応が現場では行われています。
一般的に鉄製の履帯は路面との摩擦でアスファルトを削ったりヒビ割れを起こしやすいため、この条件を満たすとは言えません。
一方、ゴム製の履帯(ゴムクローラー)は接地面がゴムで覆われており路面へのダメージが格段に小さいことから、法律上「損傷のおそれがない」構造として扱われます。実際、自衛隊の戦車も公道を走行するときは金属履帯にゴムパッドを装着し、路面を直接傷つけないようにしています。
ゴムクローラーを標準装備した農業用トラクターや不整地運搬車などはナンバー登録されて公道を走れる車両も存在し、方向指示器など必要な装備を備えれば小型特殊自動車として公道走行が可能です。
こうしたゴム履帯の車両であっても急旋回や長距離走行は避け、路面を摩耗させない慎重な運転が求められます。ゴム履帯は舗装上では摩耗も早く、製造メーカーも「舗装路での長時間走行は寿命を縮める」と注意喚起するほどです。
したがって、ゴムだからといって無制限に走ってよいわけではなく、あくまで短距離・低速かつ必要最低限に留めることが望ましいでしょう。
一方、鉄製キャタピラの場合はゴムパッドを後付けする方法があります。
重機メーカーやアフターパーツで鉄履帯用のゴムパッドが販売されており、ボルトで履帯板に装着することで路面との直接接触をゴム面にするものです。これにより簡易的にゴムクローラー化でき、舗装への攻撃性を下げることができます。
ただし、ゴムパッドを付けても車両重量が大きければ路面を押し付ける力は強大なままであり、完全に損傷リスクをゼロにできるわけではありません。
また装着に手間がかかることや、パッド自体の摩耗も進むため、やはり一時的・限定的な利用に留まります。鉄キャタピラの重機をどうしても舗装路で動かす必要がある場合は、後述するように敷鉄板などで道路を養生したうえで最徐行する、といった対応が現場では行われています。
キャタピラによる舗装損傷リスクと原因者負担の責任
キャタピラ車両が舗装道路に与える影響として見逃せないのが路面損傷のリスクです。
履帯はタイヤと比べ接地面積が広く一見すると路面への荷重は分散されますが、実際には金属製の履帯板エッジが線状の荷重を与え、アスファルトに傷を付けたり剥離を起こしたりする恐れがあります。特に旋回時や不整地から舗装への乗り上げ時には、舗装面を引っ掻くような力が働き、表層がめくれたりクラックが広がる原因となります。
こうした表面的なキズであっても放置すれば雨水の浸入や凍結で劣化を早め、道路寿命を縮める要因となります。また、たとえ小さな傷でも他人(公共)の財産である道路に損傷を与える行為そのものが問題であり、道義的にも許されません。
では万一キャタピラ車両で舗装を破損させてしまった場合、 誰がその補修費用を負担するのでしょうか?
さらに、キャタピラ車両を無許可で公道走行させれば法律違反による制裁もありえます。
道路交通法上は無登録の建設機械を走行させれば無車検運行や整備不良車両運行などの違反となり得ますし、適切な運転免許を持たない者が運転すれば無免許運転にも問われます。
事実、奈良県で無許可のパワーショベルを公道走行させた事案では、運転者が免許取り消し処分を受けています。このケースでは「パワーショベルは建設機械であって自動車ではない」と運転者が主張しましたが、裁判所は道路交通法上「戦車などと同じ大型特殊自動車に該当する」と判断し無免許運転の違反を認定しました。
このように善意や緊急対応のつもりでも法に反すれば厳しい結果を招く恐れがあり、十分な注意が必要です。
履帯はタイヤと比べ接地面積が広く一見すると路面への荷重は分散されますが、実際には金属製の履帯板エッジが線状の荷重を与え、アスファルトに傷を付けたり剥離を起こしたりする恐れがあります。特に旋回時や不整地から舗装への乗り上げ時には、舗装面を引っ掻くような力が働き、表層がめくれたりクラックが広がる原因となります。
こうした表面的なキズであっても放置すれば雨水の浸入や凍結で劣化を早め、道路寿命を縮める要因となります。また、たとえ小さな傷でも他人(公共)の財産である道路に損傷を与える行為そのものが問題であり、道義的にも許されません。
では万一キャタピラ車両で舗装を破損させてしまった場合、 誰がその補修費用を負担するのでしょうか?
これは道路法の原因者負担金制度に基づき、基本的に損傷を与えた原因者(行為者)が修繕費用を全額負担することになります。
道路法第58条では「道路管理者は、他の工事又は他の行為により生じた道路の損傷復旧費用を、その原因を生じさせた者に負担させることができる」と規定されており、これにより自治体等の道路管理者は直接損傷を与えた当事者に補修費用を請求できます。
この制度は通常の損害賠償と異なり過失の有無を問いません。故意でなくとも結果的に道路を損傷したならば請求を免れないため、安易な考えでキャタピラ車を公道に乗り入れると高額な補修費を後から請求されるリスクがあります。
実際、解体工事業者が工事中に道路を傷めてしまい、数十万円以上の原状回復費用を負担するといった事例も報告されています(※参考:埼玉県の公共物損傷対応マニュアル等)。
道路法第58条では「道路管理者は、他の工事又は他の行為により生じた道路の損傷復旧費用を、その原因を生じさせた者に負担させることができる」と規定されており、これにより自治体等の道路管理者は直接損傷を与えた当事者に補修費用を請求できます。
この制度は通常の損害賠償と異なり過失の有無を問いません。故意でなくとも結果的に道路を損傷したならば請求を免れないため、安易な考えでキャタピラ車を公道に乗り入れると高額な補修費を後から請求されるリスクがあります。
実際、解体工事業者が工事中に道路を傷めてしまい、数十万円以上の原状回復費用を負担するといった事例も報告されています(※参考:埼玉県の公共物損傷対応マニュアル等)。
さらに、キャタピラ車両を無許可で公道走行させれば法律違反による制裁もありえます。
道路交通法上は無登録の建設機械を走行させれば無車検運行や整備不良車両運行などの違反となり得ますし、適切な運転免許を持たない者が運転すれば無免許運転にも問われます。
事実、奈良県で無許可のパワーショベルを公道走行させた事案では、運転者が免許取り消し処分を受けています。このケースでは「パワーショベルは建設機械であって自動車ではない」と運転者が主張しましたが、裁判所は道路交通法上「戦車などと同じ大型特殊自動車に該当する」と判断し無免許運転の違反を認定しました。
このように善意や緊急対応のつもりでも法に反すれば厳しい結果を招く恐れがあり、十分な注意が必要です。
公道を走らせる際のリスク回避チェックリスト
回送車(トレーラー)での輸送を最優先
最も推奨されるのは、キャタピラ車両は自走させずトレーラーやセルフローダーに積載して輸送することです。これにより道路損傷や法規制の問題を回避できます。特に長距離の移動や市街地の走行は、たとえゴム履帯でも自走させず輸送した方が安全です。
事前許可取得と行政手続きのポイント
工事現場内の一部で公道を横断する、隣接する現場間を短距離だけ移動するといった場合は、事前に道路管理者や警察に相談・許可申請を行いましょう。道路法の通行許可(特殊車両通行許可や通行認定)や道路使用許可が必要になるケースがあります。
許可証を取得せずに勝手に走行すれば違法となり得ますので注意してください。
許可証を取得せずに勝手に走行すれば違法となり得ますので注意してください。
路面養生・最徐行でダメージを最小化
自走が許可される場合でも、必ず路面保護の養生措置を講じます。具体的には走路に敷鉄板や厚いゴムマットを敷く、古タイヤやゴム板で履帯と路面の間に緩衝材を入れるなどです。こうした養生の上を徐行(極めて低速)走行すれば、路面へのダメージを最小限に抑えられます。
また急な旋回や急ブレーキは厳禁で、直進と緩やかなカーブ以外の動きを避けるようにします。必要なら前後進を繰り返して方向転換し、極力路面を引きずらないよう工夫します。
また急な旋回や急ブレーキは厳禁で、直進と緩やかなカーブ以外の動きを避けるようにします。必要なら前後進を繰り返して方向転換し、極力路面を引きずらないよう工夫します。
ゴムパッド装着・代替機種の活用
前述の通り、鉄製履帯には着脱式のゴムパッドを装着できます。現場間移動の際には事前にパッドを装着しておき、走行後に取り外すなどして路面保護に努めます。
また、可能であればゴムクローラー仕様の車両を選定することも有効です。例えば同じバックホウでもホイール式(タイヤ式)のものにする、クローラークレーンではなくタイヤクレーンにするといった代替も検討してください。
最近ではホイール式建機の需要増もこうした規制背景や輸送コスト回避の流れがあります。
また、可能であればゴムクローラー仕様の車両を選定することも有効です。例えば同じバックホウでもホイール式(タイヤ式)のものにする、クローラークレーンではなくタイヤクレーンにするといった代替も検討してください。
最近ではホイール式建機の需要増もこうした規制背景や輸送コスト回避の流れがあります。
免許・保安装備の最終確認
公道を走る以上、運転手は該当車両に必要な運転免許を携帯していなければなりません。大型特殊免許(カタピラ限定)や小型特殊免許など、該当する区分を確認してください。
また車両の灯火類(ヘッドライト・ウインカー・テールランプ)やミラー、警音器など道路運送車両法の保安基準を満たす装備が備わっているかを事前に点検しましょう。ナンバー登録済みで車検が有効な車両であれば基本的基準はクリアしていますが、工事現場専用機はこれらが未装備の場合も多いため注意が必要です。
また車両の灯火類(ヘッドライト・ウインカー・テールランプ)やミラー、警音器など道路運送車両法の保安基準を満たす装備が備わっているかを事前に点検しましょう。ナンバー登録済みで車検が有効な車両であれば基本的基準はクリアしていますが、工事現場専用機はこれらが未装備の場合も多いため注意が必要です。
路面損傷が発生した場合の初動対応
走行経路上で万一路面を傷めてしまった場合、隠さず速やかに道路管理者(市区町村道なら市町村役場、都道府県道なら県土木事務所等)に連絡し、指示を仰ぎましょう。
原因者負担での補修となりますが、放置して後で発覚すれば悪質とみなされる恐れがあります。保険対応できるケースもあるため(請負業者賠償責任保険などに加入していれば対象となる可能性あり)、早めの報告と誠意ある対応が肝心です。
以上のように、キャタピラ付き車両の一般道走行には厳しい制約があり、基本は「走らせない」に越したことはないと言えます。
どうしても必要な場合に限り、法律の定める条件を満たし関係機関と調整した上で、路面を傷めない工夫と安全運転を徹底してください。
道路は公共の財産であり、適切な許可と配慮なく走行すれば違法行為となるだけでなく高額な損害負担や社会的信用の失墜に繋がります。法律の背景には道路インフラを長持ちさせ、他の車や歩行者の安全を守る目的があることを踏まえ、ルールを遵守した運用を心掛けましょう。
原因者負担での補修となりますが、放置して後で発覚すれば悪質とみなされる恐れがあります。保険対応できるケースもあるため(請負業者賠償責任保険などに加入していれば対象となる可能性あり)、早めの報告と誠意ある対応が肝心です。
以上のように、キャタピラ付き車両の一般道走行には厳しい制約があり、基本は「走らせない」に越したことはないと言えます。
どうしても必要な場合に限り、法律の定める条件を満たし関係機関と調整した上で、路面を傷めない工夫と安全運転を徹底してください。
道路は公共の財産であり、適切な許可と配慮なく走行すれば違法行為となるだけでなく高額な損害負担や社会的信用の失墜に繋がります。法律の背景には道路インフラを長持ちさせ、他の車や歩行者の安全を守る目的があることを踏まえ、ルールを遵守した運用を心掛けましょう。